バルトーク ピアノ協奏曲第2番 Sz. 95
2019 MAR 16 17:17:13 pm by 東 賢太郎

 この曲は浪人時代に聴きこんでいた「バルトークのすべて」(左の写真)に一部が収録されていて、この作曲家の音楽のうち最初に知ったもののひとつです。受験の最中でした。なぜバルトークに興味を持ったかというと、色弱で文系を受けることになったのですが文系科目は伸びしろがないと思い、数学で満点をとる作戦を決行中だったからです。どこかに「バルトークの曲は数学的だ」とあって、彼の学者然とした風貌ともども関心をもったのだったと思います。
この曲は浪人時代に聴きこんでいた「バルトークのすべて」(左の写真)に一部が収録されていて、この作曲家の音楽のうち最初に知ったもののひとつです。受験の最中でした。なぜバルトークに興味を持ったかというと、色弱で文系を受けることになったのですが文系科目は伸びしろがないと思い、数学で満点をとる作戦を決行中だったからです。どこかに「バルトークの曲は数学的だ」とあって、彼の学者然とした風貌ともども関心をもったのだったと思います。
ピアノ協奏曲第2番でまず度肝を抜かれたのは第2楽章の冒頭の弱音器付きの弦合奏の神秘的なたたずまいでした。お聴きください。
なんだこれは?とびっくりして、すぐスコアを調べます。ピアノ譜にするとこんな風になってます。
驚きでした。完全5度が積み重なって平行移動。5+5は9度を作るので常に不協和な響きを含みますが、にもかかわらず美しい!この楽章は僕の中で美のディメンションを広げてくれましたが、同時に思ったのは、しかしそれをピアノのキイから紡ぎだして選び取ったのはあくまでバルトークの耳だろうということです。
この楽譜にはあたかもメカニックな数的な摂理があるように見えますが旋律としては見当たらず、5度の平行移動はドビッシーが元祖であって誰も彼を数学的だとは言いません。何が言いたいかというと、バルトークはフィボナッチ数列や黄金分割比を意識して使用してますが、それもここの5度とおんなじだろうということです。彼は十二音技法ほど厳格かつ思想的、原理的な音選びのメカニズム(条件付け)は適用せず、葉書の縦横比が黄金比だから調和して見えるというようなエステティックな意味でこだわった人です。バルトークは数学的だというのは「モーツァルトの走る悲しみ」同様の文学的レトリックにすぎませんね。
「クラシックの作曲家は理系である」と各所に書いてきました。理系という概念は日本的で、あえてわかりやすいようにそうしてますが、数字や記号による抽象思考、論理思考に弱い人は楽譜は読めても書けないだろうという意味です。ロジカルな文章も同様です。演奏は読む側だから書く側とは違います。フィボナッチ数列の名を聞いたことがない人でもバルトークは演奏できます。コード進行という概念ができて初めて、読む側の人でも曲のようなものが書けるようになったのです。
理系が全員数字にこだわることはないでしょうが、数字に弱かったり興味がなかったりということはないでしょう。バッハ、モーツァルト、ショパン、ブルックナー、マーラー、ショスタコーヴィチ、シェーンベルクの数字へのこだわりは有名ですが、楽譜を書いて思考するという記号論理学的操作を業としている人が大なり小なり数字に関心を持ったり執着したりするのは自然です。しかし、それは単に「呪われている」「幸運を呼ぶ」など呪術的な主観であったりもするのです。数学者が必ずしも占星術師ではないように、バルトークがフィボナッチ数列を使ったと言って「数学的だ」と言ってしまうのは乱暴と思います。
僕はバルトークは「ロマンチスト」だと思ってます。後期ロマン派の分派に分類したい。そんな馬鹿なと思われるでしょうが、彼はハンガリー料理を ”おふくろの味” にしながら独仏露料理も取り入れ最後は(不本意ではあったが)ニューヨークに出ていってインターナショナル創作料理店の親父になった人です。数的素材、バーバリズム、無調、神秘主義、ピアノの打楽器的用法などはハンガリー料理のローカル臭をろ過、無機化し、インターナショナル風にする当時国際的に流行っていた食材やスパイスでありました。僕は彼の童心に帰った ”おふくろの味” である「子供のために」を弾いてそう確信したのです。初心者のころに丸呑みして「気持ちいいな」と思えた要素もそれだと思います。
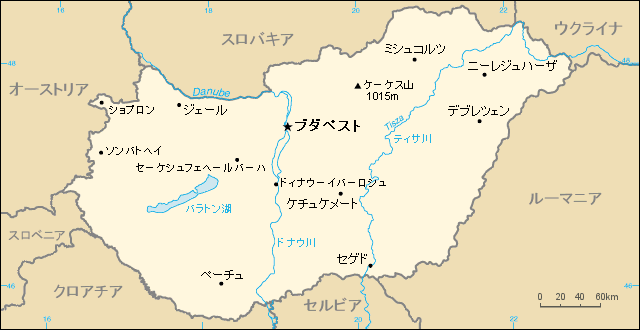 チューリヒにいたころ、ブタペスト在住の K氏がメンバーとなっているゴルフリゾートがペーチュという街の郊外にありました。どこかというとこの地図の一番下の方、ブタペストからドナウ川沿いを車で200キロほど南下したあたりで泊まってゴルフ三昧しました。車をぶっ飛ばして片道4時間もかかる長い行程でしたが、ホテルは新しくてK氏の顔が利き、クオリティの高いコースなのにすいていてやり放題なのに魅せられて4回も訪問しました。
チューリヒにいたころ、ブタペスト在住の K氏がメンバーとなっているゴルフリゾートがペーチュという街の郊外にありました。どこかというとこの地図の一番下の方、ブタペストからドナウ川沿いを車で200キロほど南下したあたりで泊まってゴルフ三昧しました。車をぶっ飛ばして片道4時間もかかる長い行程でしたが、ホテルは新しくてK氏の顔が利き、クオリティの高いコースなのにすいていてやり放題なのに魅せられて4回も訪問しました。
ハンガリーを縦断してクロアチア、セルビア近くまで下るのはなかなかの経験です。途中で食べたアイスクリームやパプリカの効いたグラーシュは美味だったし、人の当たりも柔らかく、農村の田園風景もドイツやスイスとはまた違った趣のあるものでした。ペーチは古代ローマ帝国に起源のある立派な都市ですが、リゾートのある郊外はというと畑と林と農道しかありません。ハーリ・ヤーノシュの稿に書きましたが一度大変な目にあって、夜にペーチュまで遊びに行った帰りにクルマが農道でエンストして動かなくなってしまったのです。参りました。人っ子ひとりない所で寒く、1時間待っても車は1台も通りません。男4人でしたが下手すると凍死かまで頭をよぎりました。
あのとき、ふるえながら道に立って、完全な静寂の中、真っ暗な神秘の空を見上げました。深呼吸して、かすかに田舎の香水も混じったような人懐っこさもあるハンガリーの大地の香りを嗅いで、ふとP協2番の第2楽章、上の楽譜のところが脳裏に聞こえてきたのです。バルトークの聴覚は鋭敏で、いなくなった飼い猫の誰も聞こえない声を聞いて探し当てた。ああそうか、あの音楽はこの空気から彼が聞き取ったものなのかと妙に安心してきて、心の中の音をじっくり聞いて時をやり過ごしたのを覚えています。やがてやっと通りかかった車がガス・スタンドまで2人を運び、彼らの説明でトレーラーが救援に来てくれて難を逃れました。ホテル着は午前4時でした。ハンガリーの強烈な思い出となっていますが、あの香りは一生忘れないでしょう。
バルトークの生地はこの地図の右下のほうにあるNagyszentmiklos(ナジセントミクローシュ)です。ペーチュより東側で、ご覧の通り現在はルーマニアです。
wikipediaによると、バルトークの血筋はこうです:
父・ハンガリー東北部(スロヴァキア国境に近い)の下級貴族の家系。
祖母・ブニェヴァツ人(南スラヴの少数民族集団)でハンガリーでは多くがバーチ・キシュクン県バヤ(ペーチュの隣町)に居住。
母・ドイツ系だがマジャールとスラブの血を引く。スロヴァキア生まれ。
バルトークは父が早くに病没しピアノ教師の母と現在のウクライナ、そして彼女の母国であるにスロヴァキア移住しています。
生地のナジセントミクローシュから出土した23の金工品は遺宝としてウィーン美術史美術館に展示されていますが誰が造ったのか、どこから来たのか、その由来についてはいまだに論争があるそうです。1799年にブルガリアの農民が土中から発見したというからわが国の志賀島の金印を思い起こします。この写真がそれです。
 この地域のローマ、トルコ、スラブ、マジャール(フン)、中央アジア(スキタイ)、インド、タイ、中国の文化の混交を想像させる、キリスト教文化とは異(い)なるものを感じさせないでしょうか。キリスト教でありながら十字軍に略奪され、イスラム多民族国家のオスマン帝国に服属し、カルロヴィッツ条約でハプスブルグのものとなったというヨーロッパの火薬庫バルカン半島の根本です。オスマン帝国はアチェ王国のあったインドネシアまでのあった艦隊を派遣しており、バルトークの血筋の複雑さへの想像はそう荒唐無稽でもないと思うのです。
この地域のローマ、トルコ、スラブ、マジャール(フン)、中央アジア(スキタイ)、インド、タイ、中国の文化の混交を想像させる、キリスト教文化とは異(い)なるものを感じさせないでしょうか。キリスト教でありながら十字軍に略奪され、イスラム多民族国家のオスマン帝国に服属し、カルロヴィッツ条約でハプスブルグのものとなったというヨーロッパの火薬庫バルカン半島の根本です。オスマン帝国はアチェ王国のあったインドネシアまでのあった艦隊を派遣しており、バルトークの血筋の複雑さへの想像はそう荒唐無稽でもないと思うのです。
僕はハンガリー人であるはずのバルトークがなぜ「ルーマニア民俗舞曲」を書いたり9才の作品に「ワラキア風の小品」があるのか不思議に思っていました。ワラキア公国とは15世紀に敵や貴族を串刺しにして大量に惨殺したヴラド3世(吸血鬼・ドラキュラ伯爵のモデル)が統治したルーマニア南部にあった国です。
「彼は民俗音楽の研究家だったのだ」という能天気な教科書的説明で納得されていますが、本当にそうでしょうか?仮に日本人の作曲家だったとして、韓国や中国の民謡まで採譜してそれで交響曲を書いて世に出ようと思うでしょうか。全否定はできません。しかし、まず異教徒のモンゴル人に、次いでイスラム教徒のオスマン帝国に、そしてキリスト教徒のハプスブルグ王国に「支配」された地域の民族感情は我々の想像を絶するものが在ると考えるのが実相に近いでしょう。
ナジセントミクローシュの東側にあるトランシルヴァニア地方の呼び名はルーマニア、ハンガリー、ドイツ、トルコ、スロヴァキア、ポーランド語で58種類もあって征服、被征服の血なまぐさい歴史をうかがわせます。彼は「トランシルヴァニア舞曲」を書いてます。「コントラスツ」を献呈されたヴァイオリニスト、ヨゼフ・シゲティもハンガリー人(ユダヤ系)ですが、この曲はトランシルヴァニア民謡が使われており、シゲティの出身はルーマニアの旧トランシルヴァニア公国領です。
左様にバルトークの ”おふくろの味” は一筋縄ではないと僕は考えるのです。アイデンティティは捨て去ることはできないし、彼も捨てようとはしなかったでしょう。
僕は最近、彼が後天的にdevelopしたものよりも持って生まれたもの、”おふくろの味” のほうに耳が行きます。彼は田舎料理の素朴な素材をベースにライバルのストラヴィンスキーやシェーンベルクの「新奇さ」に対抗するとんがったスパイスを頭脳で開発していきました。下のビデオでピエール・ブーレーズが「管弦楽のための協奏曲」の終楽章の弦のプレストは欧州のオーケストラでは弾けなかったろう、高性能のボストン交響楽団だから書けたのだろうと言ってますが、そうやってスパイス部分が増幅されていき、米国の管弦楽団のショーピース効果が広く称賛され、だんだんとそちらに比重がかかった解釈を良しとする風潮が世界的に醸成されたと感じます。
2番は第1楽章に弦が出てこないという稀有の曲でもあります。冒頭を飾るトランペットのファンファーレ主題は華麗ですがブラスバンドとピアノだけで作るこの楽章の世界は彼のアレグロ・バルバロのごとくに無機的で凶暴であり、ファンファーレは幻想交響曲のギロチンの首切り場面のそれに聞こえてきます(この主題は第3楽章に再現します)。
突如現れるピアノの打楽器のような強烈かつ鮮烈なリズムの連打は暴君のように無慈悲でまことに野蛮ですが、このリズム(タンタタ・タタタタ)は冒頭ファンファーレ主題に由来し、この楽譜をご覧になれば明確ですが、和声が5度+5度である、つまり例の第2楽章冒頭の静謐で神秘的な弦楽合奏の和音なのです(しかもリズムまでタンタタだ!)
これに呼応するオーケストラもティンパニ小太鼓が春の祭典並みの切れ味鋭いリズムアンサンブルを叩きつけ(後に「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」の原型となる)、ピッコロ、フルートが幻想交響曲の妖怪の半狂乱の声をあげ(練習番号115)不気味極まりなし。バルトークのこういう一面には数学者など影も形もなく、「中国の不思議なマンダリン」の役人の惨殺につながる残虐、凶暴な串刺し公(ドラキュラのモデル、ヴラド3世)もかくやというところがあるのです。トランシルヴァニアの人種のごった煮を前提としないと彼の多面性は理解できないことがお分かりいただけるでしょうか。
だからこそ第2楽章で初登場する弦合奏の夜のしじまが五感に訴えるのです。中間部で再度ピアノがパーカッシブなパッセージを強奏しますが、ティンパニのロールに乗って最後の審判の鉄槌を打つピアノがまた強烈です。ここではブラスの金色がないため暗色が支配し、楽章間でコントラストが明確につけられます。指では弾けず手のひらで抑えないと弾けない楽譜が頻出。金管が省かれるこの楽章は5年後に書かれることになる弦チェレの音がすでにしています。この楽章がであり緩ー急ー緩でシンメトリーであり、前後の楽章に挟まって急ー緩ー急ー緩ー急となる。彼ならではの形式論理です。
終楽章は5オクターヴ駆け上がるピアノで激烈に開始。続くティンパニの悪辣な短3度(ドーミ♭)の連打は明らかに春の祭典を意識しています(彼は祭典の初演直後にそのスコアを研究)。第1楽章ファンファーレが響き弦チェレの第2楽章が響き、どす黒い生地に黄金の光彩をまぶして曲は管弦楽の協奏曲の改定されたエンディングで終わります(この楽章は冒頭と終結がそれで閉じています)。僕の主観ですが、その黄金のきらめきは上掲写真のナジセントミクローシュから出土した23の金工品を強く連想させます。
ピアノ協奏曲というジャンルはバルトークにとってモーツァルトと同じ意味を持つ、つまり、自身が生きているうちは自分で弾くためのシグナチャー・ピースであると思われます。左様にフランクフルトでの1、2番の初演者はバルトーク自身であり、3番は愛する妻に弾かせる意図で書きました。だから彼はそこに彼自身の消し去れない一面を、すなわち「非キリスト教的なるもの」、もっと言うなら金の出土品のレリーフのような「オスマン帝国的なるもの」を書き込んだのではないかと思います。
この曲のピアノパートは難易度で頂点にあることで有名です。聴くだけでも想像はつきますが、実際に、していますwikipediaによるとアンドラシュ・シフが「弾き終わるとピアノが血だらけになる」と、スティーブン・ビショップ・コヴァセヴィッチが「弾いた曲の内で一番技術的に困難で練習すると手が痺れてしまう」というコメントしているそうです。それを弾けたという事実が
ゾルターン・コティッシュ / ジョルジュ・レヘル / ブタペスト交響楽団
 ピアニストは19才。彼は後に再録音していますが、何故必要があったのか解せない飛ぶ鳥落とす名演であります。このLPはフンガロトン原盤で日本ではキングから79年に出ました。コティッシュが2番、ラーンキが3番と、共産時代のハンガリー国家が売り出し中の若手2人をお国の英雄バルトークでフィーチャーしたもので、演奏もしかるべく気合が入っ
ピアニストは19才。彼は後に再録音していますが、何故必要があったのか解せない飛ぶ鳥落とす名演であります。このLPはフンガロトン原盤で日本ではキングから79年に出ました。コティッシュが2番、ラーンキが3番と、共産時代のハンガリー国家が売り出し中の若手2人をお国の英雄バルトークでフィーチャーしたもので、演奏もしかるべく気合が入っ ています。買ったのは就職した年だからあまり聴けず、じっくり味わったのは留学後のロンドンでした。もう一つ、この演奏の決定的魅力は伴奏のレヘル指揮のオーケストラがローカル色満載であることで、無用にとんがったところがなくまさにバルトークの ”おふくろの味” 路線にぴったりなこと。第2楽章の神秘もひなびた味を伴っていて、これぞ僕がペーチュで嗅いだあの大気の香りです。録音も丸みがあり米国流の名技主義とデジタル解像度を競う路線とは無縁の昔懐かしさがあります。youtubeにこのLPの音をアップしましたのでぜひお試しください。
ています。買ったのは就職した年だからあまり聴けず、じっくり味わったのは留学後のロンドンでした。もう一つ、この演奏の決定的魅力は伴奏のレヘル指揮のオーケストラがローカル色満載であることで、無用にとんがったところがなくまさにバルトークの ”おふくろの味” 路線にぴったりなこと。第2楽章の神秘もひなびた味を伴っていて、これぞ僕がペーチュで嗅いだあの大気の香りです。録音も丸みがあり米国流の名技主義とデジタル解像度を競う路線とは無縁の昔懐かしさがあります。youtubeにこのLPの音をアップしましたのでぜひお試しください。
デジェ・ラーンキ(pf) / ゾルタン・コティッシュ / ハンガリー国立管弦楽団
この曲を血管の中にもっている二人による快演。ラーンキの2番は正規録音がなくこのライブは貴重。生気ほとばしるテンポの第1楽章は最高でこれ以上のものは求め難いでしょう。終楽章のエネルギーもバルトークの意図の体現です。指揮に回った時のコティッシュの傾向で第2楽章の神秘感や翳りがいまひとつなのはマイナスですが、補って余りある美点を評価。ご一聴をお勧めします。
ゲザ・アンダ / フェレンツ・フリッチャイ / ベルリン放送交響楽団
 ピアニスト、指揮者ともブダペスト生まれ。オーケストラの深みある色彩がまことにふさわしく、曲のエッセンスをフリッチャイが完璧に伝えきって確信に満ちた演奏をしています。彼はバルトークに師事した指揮者でこの音が正調に近いかどうかはともかくも比類ない説得力があることは誰も否定できないでしょう。アンダのピアノは骨太で重量感があり、ポリーニの指の回りよりこの曲では重要なものは何を教えてくれます。技の切れ、無傷、スマートさではないのです。
ピアニスト、指揮者ともブダペスト生まれ。オーケストラの深みある色彩がまことにふさわしく、曲のエッセンスをフリッチャイが完璧に伝えきって確信に満ちた演奏をしています。彼はバルトークに師事した指揮者でこの音が正調に近いかどうかはともかくも比類ない説得力があることは誰も否定できないでしょう。アンダのピアノは骨太で重量感があり、ポリーニの指の回りよりこの曲では重要なものは何を教えてくれます。技の切れ、無傷、スマートさではないのです。
マウリツィオ・ポリーニ / クラウディオ・アバド / シカゴ交響楽団
 ピアノは技巧的に高度で速いパッセージまで微細に引き分けられますが、タッチの軽さは野蛮、凶暴さに欠けショパンのように清明。オケもスマートだが第2楽章の弦も透明で神秘のにごりがまるでなく蒸留水を飲むようであります。バルバロな部分はインテリがヤンキーを気取ったみたいで不道徳のかけらもなく、これほどバルトークの ”おふくろの味” が希薄な演奏もなし。イメージは全然ふくらまず、何を聴いたかさっぱりわからず。
ピアノは技巧的に高度で速いパッセージまで微細に引き分けられますが、タッチの軽さは野蛮、凶暴さに欠けショパンのように清明。オケもスマートだが第2楽章の弦も透明で神秘のにごりがまるでなく蒸留水を飲むようであります。バルバロな部分はインテリがヤンキーを気取ったみたいで不道徳のかけらもなく、これほどバルトークの ”おふくろの味” が希薄な演奏もなし。イメージは全然ふくらまず、何を聴いたかさっぱりわからず。
レイフ・オヴェ・アンスネス / ピエール・ブーレーズ / ベルリン・フィル
 ブーレーズの伴奏が聞きもの。リズムのメカニックな正確さで最高度にあり、それがここまで極まれば快感に転じるという彼の「春の祭典」の水準にある驚くべき演奏です。ローカル色は希薄ですが、この演奏にそれを求めても仕方なしでしょう。アンスネスのピアノも指揮に完全に同期して間然するところなく作品のイデアのようなものを築き上げています。おふくろの味を欠くバルトークもこの路線と完成度ならありというというもうひとつの多面性をもうひとつの教わります。
ブーレーズの伴奏が聞きもの。リズムのメカニックな正確さで最高度にあり、それがここまで極まれば快感に転じるという彼の「春の祭典」の水準にある驚くべき演奏です。ローカル色は希薄ですが、この演奏にそれを求めても仕方なしでしょう。アンスネスのピアノも指揮に完全に同期して間然するところなく作品のイデアのようなものを築き上げています。おふくろの味を欠くバルトークもこの路線と完成度ならありというというもうひとつの多面性をもうひとつの教わります。
イディル・ビレット / チャールズ・マッケラス / シドニー交響楽団
最高難易度の2番を女性が弾くのがどれほどのものか。ユジャ・ワンが譜面を見ながら弾いているビデオがあって、弾けるだけでも称賛はしますが、イディル・ビレットのそれは衝撃です。NAXOSレーベルで知られるようになったので廉価盤アーティストの印象になっていますがとんでもない、この人は現代のギーゼキングで何でも弾ける。そこまでいくと技術だけではなく超絶的な聴覚と記憶力の問題であって普通の人の及びのつきようもない能力の持ち主でなくてはあり得ません。ビレットはトルコ人(アンカラ生まれ)人です。音楽って面白いですね。
( 「YouTubeで見る」をクリックしてください)
(こちらへどうぞ)
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:______バルトーク








