R・シュトラウス「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」
2019 JUN 6 1:01:02 am by 東 賢太郎

僕がリヒャルト・シュトラウス(以下、R・シュトラウス)の音楽を特に愛好しているかというと、なくてはならないものというほどでもないのだからNOということになる。後期ロマン派の音楽には全般にあまり関心がないのは、その肥大したオーケストレーションに必然性を感じないからだ。音楽に哲学を求める気はないが、遊興だけの為の豪勢な音響を100名が鳴らしてバッハの一丁のヴァイオリンが与えてくれる感動にかなわないならそれは壮大な無駄であり、その無駄を愛でる感性の人びとの祭典としての価値がいくらあろうとも彼らの一員になるのは僕には無理だ。
大嫌いなマーラーでひとつだけ評価するのは、8番がサラウンドの音響効果をアチーブした点である。千人の交響曲の演奏家が五百人でもチケットが半額になる必要はないが、背面、側面配置のバンダがなければ半値未満だ。オーケストレーションのエフェクトというものは、ヴァイオリン一丁ではアチーブ不能な空気の振動、それは周波数、波形から音圧に至るまでのあらゆる手段で聞き手の鼓膜から毛穴までを刺激するものであり、サラウンド効果でそれが360度に降り注ぐ様の偉大な感興を音楽の魅力の一部から排除することなど何人たりとも許されない領域のものだろう。
教会のパイプオルガンを模したと言われるオーケストラは、音楽の世俗化とともにオルガンの音響もろとも教会を脱出していった。ワーグナーのどろどろ劇が教会を念頭に作曲されたと思う者はいないだろう。そしてオーケストラ音楽は、四方八方に反響する教会の音の模写のごときサラウンド効果によるマーラーの8番によって先祖の地に帰還してくるのだ。それは単なるマーラーの酔狂ではなく、後に現れる「シアターピース」によって客席や通路を含む劇場ぜんぶが演奏の場であるという確立した概念になる。しかし、帰還先であった教会という場は、それこそが元からサラウンドのシアターピースの場だったのである。教会と管弦楽はメビウスの輪の関係だったのだ。
オーケストレーションという技法が一つの完結した美学であるという考えには賛同する。それがなければ僕はストラヴィンスキーの3大バレエに魅了されることもなかったわけだが、一時期、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(Till Eulenspiegels lustige Streiche)のスコアを深い関心を持って眺めることになった。というのは、そのことをR・シュトラウスの作品を圏外に置いて議論するのはナンセンスだということを知ったからだ。その事を説くために僕は、本稿を、まず音楽史の教科書みたいな無機的な記述から始めなくてはならない。
絵画のことを思い起こしていただきたい。それはまず教会御用達のイコンなどのいわゆる宗教画であって、画材は神や聖人であり、貴族であれ一般の民であれ自然であれ、それ以外が描かれることはなかった。それがやがて外界に出て世俗化していった。しかし当初は貴族の占有物、肖像画どまりであって市民が画題になり民家の壁を飾るのは19世紀だ。それと同様に、音楽も教会に発し、貴族の占有を経由してオペラハウスや演奏会場へとほぼ絵画と平仄を合わせて世俗化していく。
バロック音楽は日本でいえば戦国時代から江戸前期あたりに王侯貴族の食卓のBGMや子女の嗜みとなり、江戸中期に古典派に進展し、後期から明治時代にロマン派が開花するというのが凡その流れだ。ドイツ人が書いたドイツを主流と見る音楽史であれ、モンテヴェルディはじめ初期のオペラが江戸初期から興行として劇場に出ていったイタリアであれ、世俗化というプロセスが市民革命によって加速して貴族の占有物が市民の手に拡散していったのは絵画もそうだし、ルイ王朝の食卓を飾った料理やテーブルマナーが「フランス料理」という名称で全欧州からロシアに至るまで拡散したのも同様のことだ。
では、クラシック音楽が貴族でなく純粋に市民による「マスの消費」を意識して書かれたのはいつごろか。それをコンサートホールを埋めている現実の聴衆の階級の比率というよりも作曲家の意識の中の視点ということで考えるなら、僕はR・シュトラウスこそ音楽に市民、というよりもはや「大衆」をターゲットとした、そしてその延長線上で後世が商業的利用への道筋を切り開くことになったムーヴメントのパイオニアだと思っている。つまり、彼の楽曲を得たことで音楽は完全に教会、宗教、世俗権力から離脱して真の意味で大衆のものとなったのである。
「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(以下、「ティル」)を初めて聞いたときに、なんだこれ、ディズニーの音楽じゃないか?と思った。ディズニーのアニメ映画『ファンタジア』に出てくる音楽はポール・デュカスの「魔法使いの弟子」なのだが、それを聞き分ける能力はまだなかったから「ティル」も僕の中では漫画の主題曲に位置づけられてしまい、R・シュトラウスというとなにやら二流の作曲家というイメージが抜けなくなってしまった。
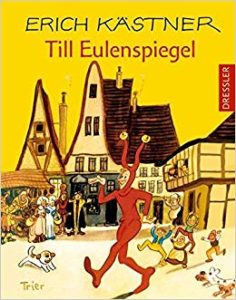 フランクフルトに赴任して会社のドイツ人たちに「ティル」とは何か尋ねた。みんな知ってる。おばあちゃんが教えてくれたわという類で、わが国ならばさしずめ日本昔話、桃太郎や一寸法師みたいなものだ。民話の主人公の名前であり愛すべきキャラで、悪戯が過ぎて処刑されてしまったことはわかったけれどもStreich(悪戯)と彼らが言うものがピンとこなかった。ましてそれが愉快(lustige)と言われても大して可笑しくない。教会や権力者をからかうとんち話で民衆が溜飲を下げられるので流行ったらしいが、それなら落語に近い。しかし八つぁん熊さんが最後に死んじまうのはどうも日本人の感性とは遠いではないか。グリムやアンデルセンの童話もエンディングが残忍であったり、こういう教訓やユーモアの側面にあって我々と西洋人は別(different)という気持ちは今も払拭できていないのが本当のところだ。
フランクフルトに赴任して会社のドイツ人たちに「ティル」とは何か尋ねた。みんな知ってる。おばあちゃんが教えてくれたわという類で、わが国ならばさしずめ日本昔話、桃太郎や一寸法師みたいなものだ。民話の主人公の名前であり愛すべきキャラで、悪戯が過ぎて処刑されてしまったことはわかったけれどもStreich(悪戯)と彼らが言うものがピンとこなかった。ましてそれが愉快(lustige)と言われても大して可笑しくない。教会や権力者をからかうとんち話で民衆が溜飲を下げられるので流行ったらしいが、それなら落語に近い。しかし八つぁん熊さんが最後に死んじまうのはどうも日本人の感性とは遠いではないか。グリムやアンデルセンの童話もエンディングが残忍であったり、こういう教訓やユーモアの側面にあって我々と西洋人は別(different)という気持ちは今も払拭できていないのが本当のところだ。
ピエロか道化か、誠に勝手解釈で恐縮だが、それを聞いて僕がイメージしたのは昭和3-40年代に流行ったハナ肇とクレージーキャッツのコントだ。「無責任男」の植木等が突拍子もなくお門違いな格好で、迷惑でお騒がせな場面でさっそうと登場してしまい、しばらくしてそれに気がついて辺りを見回して「あっ、お呼びでない?こりゃまた失礼しました!」ってやつ。あれでみんな腹抱えて笑って憂さを晴らしたのが昭和だ。笑いは人種、人生、文化、時代で異なるがあっちには毒があってこっちにはない。まあ変なオヤジが出てきて世間をかき回して笑わせるならそういうもんだと理解しておいていいんじゃないかとドイツ人の前で思ったが、説明するドイツ語力はなく断念した(お呼びでない?こりゃまた失礼しました!)。
「ティル」の曲想はまさしく写実的だ。そのまんまアニメになる。歌なしのオペラみたいに情景が浮かんでくる。シュトラウスはソナタ形式の音楽はあまり手掛けていない。リストの標題音楽の系譜にあって即物的な描写性は前例がなく、それがこれまた際立ってリッチな管弦楽法によって極彩色で生き生きと躍動する。ティルはその好例であり僕がディズニーと思ったのも故なきことではなかったかもしれない。1895年に作曲されたこれは2年後に作曲された「魔法使いの弟子」に影響し、『ファンタジア』ばかりでなく映画産業の伴奏音響の時代的ニーズにぴったりとはまり、ハリウッドの映画音楽のひな型となり『2001年宇宙の旅』にツァラトゥストラの冒頭が使われ、ジョン・ウィリアムズの『スター・ウォーズ 』にDNAがつなっがていく。ということで、クラシック音楽は完全に教会、宗教、世俗権力から離脱して真の意味で大衆のものとなる。ムーヴメントにとどめがさされたのである。
だからといってなにやら二流の作曲家というイメージが払拭されることもないが、自作の演奏会を早く終えてカードがしたくなり、指揮しながら懐中時計を眺めたR・シュトラウスという人はベートーベンの様にしかめっ面でシリアスな人生を送ることには関心がなかったのだろう。麻雀がしたくて教室を抜け出した僕としてはどうも憎めない輩であり、いくつかのオペラは実演で聴くとゴブラン織りみたいに壮麗で劇的であり、管弦楽曲は何の思想性も哲学もないけれども極上厚切りのフィレステーキみたいにやわらかくてゴージャスだ。それが細密に機能的に書かれたスコアから出てくるのは意外であり、効果は彼の楽器への深い知識に基づいている。ウォルター・ピストン著「管弦楽法」では演奏時間たかだか15分のティルから5か所の引用、解説が加えられており、僕はそれを見てその道での重要性を理解した。アメリカの作曲家がどれほどR・シュトラウスのスコアを血眼になって研究したかという一つの証だ。
こんな音を書いた人はいないのだからオンリーワンであることは疑いなく、それを一流二流と評しても言葉の遊びになってしまう。音楽は楽しいもの、それを楽しむ者に如くはなしである。
ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
 カラヤンの作る音はR・シュトラウスのスコアを豪勢に鳴らすのに欠けるものが皆無だ。あらゆる種目で満点、偏差値80。これを中身が薄いなどと貶しても意味がない、もともとシュトラウスに意味や哲学などないのだ。83年のザルツブルグ音楽祭でウィーンPOとの「ばらの騎士」を聴いたがあれは僕が人生で知る限り極上の音の御馳走だった。あれ以来ああいうクオリティのものに接したことはなく、たぶん今後もないだろう。このCDを最上のオーディオで再生するしか手はない。
カラヤンの作る音はR・シュトラウスのスコアを豪勢に鳴らすのに欠けるものが皆無だ。あらゆる種目で満点、偏差値80。これを中身が薄いなどと貶しても意味がない、もともとシュトラウスに意味や哲学などないのだ。83年のザルツブルグ音楽祭でウィーンPOとの「ばらの騎士」を聴いたがあれは僕が人生で知る限り極上の音の御馳走だった。あれ以来ああいうクオリティのものに接したことはなく、たぶん今後もないだろう。このCDを最上のオーディオで再生するしか手はない。
オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団
 ティルに格調を求めるならこれしかない。作曲家がこういうものをイメージしたかと言われればNOの気が大いにするが、ともあれクレンペラー様のお手にかかると鉄も純金に変わるのだ。彼が振るとあの幻想交響曲もなにやら貴族的気品と高級ブランド感がにじみ出てしまうのだが似たことだ。カラヤンのBPOも只者でない上手さだが、音程の清楚感ではクレンペラーのPOの方が一枚上である。ということだけでもこの演奏の質の高さは恐るべし。アンサンブルのコク、トゥッティのボディある重みも最高。このおいしさ、何度味わっても飽きることなし。
ティルに格調を求めるならこれしかない。作曲家がこういうものをイメージしたかと言われればNOの気が大いにするが、ともあれクレンペラー様のお手にかかると鉄も純金に変わるのだ。彼が振るとあの幻想交響曲もなにやら貴族的気品と高級ブランド感がにじみ出てしまうのだが似たことだ。カラヤンのBPOも只者でない上手さだが、音程の清楚感ではクレンペラーのPOの方が一枚上である。ということだけでもこの演奏の質の高さは恐るべし。アンサンブルのコク、トゥッティのボディある重みも最高。このおいしさ、何度味わっても飽きることなし。
(ご参考に)
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:______リヒャルト・シュトラウス, 映画







