ジャイアンであるためにジャイアンな政府
2020 AUG 17 19:19:29 pm by 東 賢太郎

(1)国家の目的解釈は量子力学に似ている
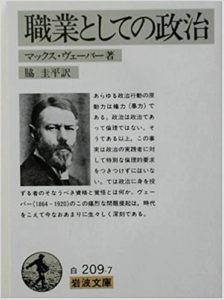 国家の目的は何かという議論をひもといていくと、だんだんわからなくなってくる。ドイツの政治学者マックス・ウェーバー(1864 – 1920)は「過去に国家がしてきたことを並べてみて、そこから国家の目的は何々だと結論することはできない」という趣旨のことを書いた(「職業としての政治」)。普通、人間であれば、その行状を調べればどういう人かは凡そわかる。しかし国はそうでないというのだ。「これが国の仕事だ、だから国の目的はこうだ」が成り立たない。有名なパラドックスに「私の言うことはウソだ」がある。こう言われた瞬間にこの人が正直者なのか嘘つきなのかは言葉から判定できなくなるがそれに似ているし、光があたると(つまり、見る前と後で)電子が動くので、見る前の物体が何という物質であったか不明だという量子力学を想起させる存在でもある。
国家の目的は何かという議論をひもといていくと、だんだんわからなくなってくる。ドイツの政治学者マックス・ウェーバー(1864 – 1920)は「過去に国家がしてきたことを並べてみて、そこから国家の目的は何々だと結論することはできない」という趣旨のことを書いた(「職業としての政治」)。普通、人間であれば、その行状を調べればどういう人かは凡そわかる。しかし国はそうでないというのだ。「これが国の仕事だ、だから国の目的はこうだ」が成り立たない。有名なパラドックスに「私の言うことはウソだ」がある。こう言われた瞬間にこの人が正直者なのか嘘つきなのかは言葉から判定できなくなるがそれに似ているし、光があたると(つまり、見る前と後で)電子が動くので、見る前の物体が何という物質であったか不明だという量子力学を想起させる存在でもある。
世界の歴史を振り返ると国家は「野獣」であり「夜警」であり「福祉提供者」であったりするが(それが「見る前」)、ではどれが正しかったのか(「見た後」)に「どれでもない」と答え、「国家は暴力行使のできる権利を持つ唯一の存在で、その独占を要求する人間共同体であり何でもできるからだ」とするのがウェーバーだ。それに対しては諸説あるが、僕は門外漢だから立ち入る資格はなく、本稿では国家の目的に対する概ねの結論は「国民に強制力のある規則を制定して維持すること」だと理解し、以下これを『国家定義』と呼び、それに従って考えてみたい。
まず、凡その歴史を俯瞰すると、すべての国とは、その地域で「俺はジャイアン」と主張する者(元首、酋長etc.)をひとりだけ認めたことにする仕組みということだ。中世まではジャイアンが腕っぷしでやりたい放題(野獣)だが、別の野獣よりましで守ってくれるジャイアンなら何をどうやってもいいという均衡が生まれた。近世になって、やりすぎはいかん、やるなら暴力行使も含めて規則でやってくれ(立憲政治)というバランスになった。やがてジャイアンは個人でなくポスト(称号)と機能(軍)になり、腕っぷしとは関係がなくなり(文民統治)、上に立つ国家はマシーン(政治装置)のような存在となる。核の抑止力によるつかの間の平和ができると、そもそもなぜ暴力行使により何でもできる権限を認めたかが明らかでなくなってきた。
「なぜジャイアンが必要なの?」
「ジャイアンはジャイアンであり続けるためにジャイアンだからだよ」
というわけのわからないことになっているのが21世紀の政治の現況である。世界国家に至る途上にあるのか、永遠に現状が続くのかは誰も知らない。もちろん政府が不要というアナキストでは僕はない。そこについては最後に述べる。
(2)真珠湾攻撃は誰が決めたのか?
国家は法律の制定によってのみ権力行使できる(国家定義)。これは市民革命で王権と闘って自由を勝ち取った欧米諸国の人は絶対に譲ることができない。アメリカ人がマスクをしないのは、国家権力に強制されるなら感染するリスクを取る方がましだからという人が多いからだ。ドイツはナチ党に無制限の立法権を与える法律(全権委任法)を認めたことでヒトラーが「何でもできる」ようにしてしまったが、国家定義どおりの手続きを踏んだからドイツ国民に責任があるといって反論するドイツ人はいない。これをドイツ赴任時代にフランクフルトの金融界の人たちに述べたところ、知恵者に「ではきくが、真珠湾攻撃は誰が決めたのか」と問い返され窮地に立ったことがある。戦争という国家権力行使の最終責任者は誰だったのかという鋭い指摘だ。
「東京裁判で首相(東条英機)とされたが直前まで攻撃を知らなかったようだ」と述べたところ一笑に付された。真偽を僕は知らないが、「首相には決定権限はなく軍を制止できなかった」とされている。スターリン、ルーズベルトの共同謀略で支那情勢が窮地となり、「国家総動員法が全権委任法であるかの如くワークしたのを誰も止められなかった」のが実態だったのではと想像するが、国家定義を満たさない決定で戦争を始めたという発言は国際社会ではナンセンスと反論され、宣戦布告問題以前のガバナンスの根源に触れる問題なのだと思い知った。ちなみに戦後唯一の武力を伴った戦争であるフォークランド “紛争” (実質は戦争である)で英国サッチャー首相は自らを首班とする戦時内閣を設置して意思決定を行った。ドイツは意思決定者を法律で処断した(ナチ礼賛は刑法130条違反になる)ことで国家定義に則って戦争責任を特定し戦後70年をしのいでいる。事の重みをかみしめるしかない。
(3)需要喚起など国家の仕事ではない
国家の目的が経済活動への関与を含むかという点にも問題がある。論点は、関与を①すべきかどうか②する意味があるかどうかの2つである。①については1970年代に国対国の経済戦争をしていた時代は米国との自動車、半導体の交渉を通産省(当時)が担ったことは大いに国益上の意味があった。がん保険を大蔵省(当時)が開放して自動車交渉を有利にする等の業際バーターは民間では困難だったこともある。しかし、現代においては、グローバル企業は多国籍サプライチェーンによる効率化、タックスマネジメントを重要な競争の要素とする時代になり、徴税者である国家が需要サイドに有意に関与する余地は激減した。安倍政権の当初の戦略に第3の矢(成長戦略)があったが、何ら出なかったし、いつのまにか誰も口にしなくなった。当然だろう。需要なき処に成長はなく、需要は国が作れない証拠だ。異次元緩和(第1の矢)と財政出動(第2の矢)の延長線上に成長戦略が自然に出てくるわけではないのである。
②については内在的な限界がある。有意なる関与は物資やサービスの「供給側」(サプライサイド)では可能かもしれないが、消費する「需要側」へは実態的にも法技術的にも困難である。馬を川に連れて行くことはできるが水を飲ませることはできないからだ。例えば少額投資における税制優遇制度であるニーサ(NISA)である。「税金をおまけしますから株式・投資信託等に投資しませんか」という趣旨だが、税金の心配は「お金がもうかってから」でいい。「株や投信のパフォーマンスは大丈夫なの?」「はい、それは自分で考えてください、自己責任で」ということだ。それで川まで行く馬は、元から喉が渇いた馬だ。そうでない馬が多いから投資による資産形成が進まないという根本的原因の解決には無力というしかない。
「少子化担当大臣」にいたっては何ができるのだろう。要は、子供をたくさん産んでもらおうというのである。しかし子供を持ちたいという「需要」を法律の制定という手法で促すのは、北欧のような公務員が多い高税率、高福祉国家でないと難しい。女性の社会進出を促進しながら子供を産んでもらうのは矛盾という統計もある。子供を成人させるには相応のお金がかかるわけで、30代の男性の所得が少ないという根本問題を解決せず子育て支援しますと言われても、その心配は「結婚できてからでいい」のはニーサとまったく同じである。「お金が不安です」「はい、ご自分で頑張って稼いでください」「相手がいません」「ご自分で見つけてください、自己責任で」。そりゃそうだ。うるさい、ほっといてくれ、だろう。国家がどうしてそこまでやるのの一言だ。
ここまでお読みいただいた読者には「代金は税金で補填しますから旅行に行きませんか?」「コロナは大丈夫なの?」「はい、それは自分で気をつけてください、自己責任で」の、今を時めくGoToキャンペーンも実質はまったく同じであることはもう説明の必要もないだろう。票になるから予算がついているが、コロナ下での旅行需要喚起の根本的解決にはならない点も同じである。できもしないことに税金を使うべきでないし、それとケインジアン政策を混同してはいけない。需要喚起は国家の仕事ではない。
(4)驚いたマーガレット・サッチャーの覚悟
冒頭に述べたように、政府は何でもできる。戦争でも売春宿の経営でも民間人大量殺戮用施設の設営でも。それも「仕事である」と主張する政府を人道的に間違っていると批判はできるが否定する理屈はないという困ったことが冒頭にややこしいことをあえて述べた意図だ。阻止するならその政治家を選挙で落とすしかない。日本国は現実に電信・電話事業、郵便事業、鉄道・航空事業の一部を独占的に “経営” していたが、雇用は創出できていても英国と同様の理由で事業経営という観点では失敗して財政赤字を増やし、すべてを株式上場し「民営化」してしまったという歴史がある。その流れを国際的に引き起こした背景は知っておくに値すると思う。経験からご説明しておきたい。
民営化の判断は日本国が考えついたのではなく、英国の第71代目首相マーガレット・サッチャー(1925 – 2013)が世界にその時流を生み出したムーヴメントに追従した結果だ。当時(1980年代)の英国は七つの海を制した大英帝国の斜陽が国民を悲観させ、活力をなくした若者が昼間からパブで飲んだくれ、犯罪、IRAのテロ等でロンドンにもすさんだ空気が流れていた。第二次大戦後に労働党政権がとった社会福祉重視、主要産業国営化の政策が財政逼迫を招き、相次ぐ労働組合のストライキを引き起こして国民生活の活力を削いで、いわゆる「英国病」を蔓延させていた。
84年にロンドンに着任してまず感じたのは、学校で習った英国の姿とはかけ離れた根深い退廃ムードだ。失業率は12%ぐらいでしかもインフレだった(フィリップス曲線が崩壊)。シティのエリートバンカーすら国の未来は暗いと口々に語った。逆に日本は、今や死語である “ハイテク産業” と呼ばれた電機、自動車、半導体、電子部品産業らの大躍進で世界の寵児の地位をほしいままにした黄金の10年間だった。その結末にはバブル崩壊がやってきたが、世界の金融市場の要衝だったロンドンのシティで日本、日本人のプレゼンスがうなぎ登りになる最後の数年の高揚感は忘れ難い。あの時をもって我々は世界の一等国民の仲間に入ったのだと断言できる。
サッチャーの民営化構想の背景が「英国病」だったことは確実だが、それだけではない、よりリアリスティックなお手本として日本経済の大躍進があったことは体感できた。 おりしも80年代初頭に米国でもエズラ・ヴォーゲルの著書「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」が警鐘として話題となり、ウォートン・スクールの授業で話題になったこともあった。父島で日本軍に撃墜された父ブッシュは10年後に大統領に就任すると日本の金融・証券業潰しの大逆襲を仕掛けてきたが、サッチャーはそれをせず86年にロンドン証券取引所を規制緩和する “ビッグバン” で活力ある外資(頭にあったのは間違いなく日系証券だ)を積極的に取り込み、ユーロドル市場取引を急拡大させシティの歳入を大幅に増加させた。
相手を叩き潰す米国と真逆の政策はテニスになぞらえて「ウィンブルドン現象」(英国主催だが選手は外人ばかりという意味。命名者は当時ノムラ・ロンドン社長だった外村である)と揶揄もされたが、ロンドンの税収の半分をシティがあげ るに至る。その外人選手のうち最大勢力だったのが日本の証券会社で、日本の話題が日々注目され、野村の現地での求人がオックスフォード、ケンブリッジ卒なのは当たり前という時代になった。80年代前半に数件しかなかったロンドンの日本食レストランが激増したのはその頃だ。最大の証券会社だった野村はサッチャー政権と良好な関係を築き、1990年にシティのチープサイドにある17世紀の郵便事業(郵政省)の古跡である巨大な “オールド・ポスト・オフィス”(写真)に移転して“ノムラ・ハウス” とする栄誉を得た。サッチャー首相が来賓でオープニング・スピーチの予定だったが前日に「代理にジョン・メージャー大蔵大臣を送るのでよろしく」と連絡があった。何事かと思ったら翌日にサッチャー辞任、メージャーの第72代目イギリス首相就任が発表された。ロンドンから帰国したばかりの僕は、野村の社内テレビ放送で美人の女子アナとキャスターを務めさせてもらった。
るに至る。その外人選手のうち最大勢力だったのが日本の証券会社で、日本の話題が日々注目され、野村の現地での求人がオックスフォード、ケンブリッジ卒なのは当たり前という時代になった。80年代前半に数件しかなかったロンドンの日本食レストランが激増したのはその頃だ。最大の証券会社だった野村はサッチャー政権と良好な関係を築き、1990年にシティのチープサイドにある17世紀の郵便事業(郵政省)の古跡である巨大な “オールド・ポスト・オフィス”(写真)に移転して“ノムラ・ハウス” とする栄誉を得た。サッチャー首相が来賓でオープニング・スピーチの予定だったが前日に「代理にジョン・メージャー大蔵大臣を送るのでよろしく」と連絡があった。何事かと思ったら翌日にサッチャー辞任、メージャーの第72代目イギリス首相就任が発表された。ロンドンから帰国したばかりの僕は、野村の社内テレビ放送で美人の女子アナとキャスターを務めさせてもらった。
サッチャーの強い決意を象徴するものとして、英国民営化省での会議で聞いたギネス大臣の言葉が忘れ難い。1991年に英国電力株式の日本での公募に関わらせていただいた際のことだった。
「組合運動に明け暮れ能力もやる気もなくした公務員に公的事業を任せておくことは輝かしい大英帝国の没落を意味する」
自身が公務員であった大臣が我々に、はっきりとそういう趣旨のことを言った。これぞ、労働党の負の遺産を一掃するコミットメントの表明だった。サッチャー政権にはガス、電力、石油、鉄道、航空、鉄鋼、水道、テレコムなど公共財・サービスの提供に関わる国家の屋台骨の産業において、国営企業のままに放置しておくと効率や技術革新で米国、日本の水準に大きく水をあけられてしまうという強烈な危機感があった。民間企業に伍するモチベーションで経営させなくては大赤字が累積して国家財政が破綻し、未来の国富を生む研究開発(R&D)も米国や日本に劣後し、国の屋台骨が朽ち果てて二等国に没落する。それには新自由主義的な競争原理を注入するしかない。その結論として、公共財・サービスの提供を行う国営企業を民営企業にして株式公開し、新たな株主の国民の厳しい目に叶う経営をさせようという荒療治が選択されたのである。
証券界の人間なら誰もが記憶しているが、90年代前半にこのムーヴメントは同様に公共セクターの非効率を抱えていた世界各国に瞬く間に波及して株式のグローバル・オファリングという引受業務の新領域を開拓することになり、我々野村の海外部門はそこで台頭してきたゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーと真正面から激突し、熾烈なマンデート取得戦争を繰り広げた。英国電力公募の日本でのマンデートは我々が取った。スコットランドはたしか大和が取った。メキシコの国営テレコム会社、テルメックスも同じ流れで民営化するとなって国際金融部の課長として即座にメキシコシティーに飛んだが、マンデートは既にゴールドマン・サックスの戦利品だった。勝ちも負けもあったが、世界の金融のど真ん中でトップ・プレーヤーとして戦った、我が人生でも最高にエキサイティングな時代だった。世界的に澱んでいた公的セクターに強烈な喝を入れた「鉄の女」サッチャーは、もとより最も資本主義的である証券界にまで電撃的なインパクトを与えたのである。
(5)金融市場から目撃した首相の重み
サッチャーは中間階級下層の出である。英国議会にはピューリタン革命で市民(クロムウェル)が絶対王政維持を主張する王族派と闘いチャールズ1世を処刑した血なまぐさい歴史が投影されている。王室、貴族は貴族院(参議院に相当)に封じ込め、庶民院(衆議院に相当)が実質的に国政を切り盛りするが、それでも雑貨商の娘が大英帝国の首相とは新鮮だった。中流階級、女性という政治的ハンディからだろう、自助努力をモットーとしてオックスフォードでは化学専攻ながら弁護士の資格を取り財政、税制も学び、エスタブリッシュメント(既得権益勢力)への徹底反抗が「小さな政府」への動機となっていたともいわれる。こういう人が現れれば男か女かなど矮小な議論である。
規制緩和、民営化への伏線が、前述した82年に英国領であるフォークランド諸島をアルゼンチン軍が武力で奪取した戦争だ。同諸島はグレートブリテン島からはるか離れた、異国人にはどう見てもアルゼンチンの領土に見える海域に位置している。それもあって英国病で萎えた世論の一部は奪回に否定的であり、米国や国連が仲裁を申し出もしたが、サッチャーは「侵略者が得をすることはあってはならない」と断固として英国陸海軍による武力奪還を曲げず、アンドリュー王子ら王室、貴族も出兵した。本件は当面のところ第2次大戦後の唯一の本格的武力衝突であるが、現在の我が国が尖閣諸島で直面しかねない事態への対応として示唆に富む。これに勝利して奪還成功したことで国民は沸き、それまで不人気だった政権支持率は保守層のみならず大衆においても急上昇したのである。
サッチャー政権はたまたま僕が社会人になった1979年に始まり、米国留学した82年にフォークランド紛争があり、ロンドンに着任した84年に中国に97年の香港返還を約束し、ロンドンから帰国した90年に政権は終焉した。そして香港返還の年に僕は香港に着任したのである。これだけ節目の年が一致しているのは不思議なほどだ。11年の政権期間中にこちらは社会人としてのすべての基礎ができ、そのうちの6年は彼女の治世下のロンドンにおいて洗礼を受けていたのであり、自由化と金融ビッグバンで英国が徐々に誇りと活気を取り戻すのをまのあたりにした。格別の自覚はないが、サッチャリズムの思想的影響を受けていて不思議ではないし、尊敬する政治家を一人だけあげるなら彼女である。
(6)サッチャリズムとハイエク
サッチャリズムは成功の代償に失業率を上げた。万事がうまくいったわけではないが、国の急場を救った象徴的ケースとして評価されるべきだ。彼女はまず壊滅的だった国家財政の改革に着手し、身を切る緊縮財政(社会保障費、教育費の削減)を断行して国民の大不評を買った。フォークランド戦争がなければ短命政権に終わっただろうといわれたほどだ。そこで踏み切った開戦は事後の巨大かつ不測の歳出を伴い、やろうとしたことの真逆の方向に舵を切ったわけだが、その一手が結果的には大当たりだった。もし彼女がケインジアン政策的な当たり前の手を打ってしまっていたら、財政問題が是々非々の判断の大きな足かせになって舵が切れなかった可能性がある。運もあった。
サッチャーは「共産主義、社会主義が本質的にファシズムやナチズムと同根であり、更に悪いものであり、むしろスーパーファシズム・全体主義である」と説く経済学者フリードリヒ・ハイエク(1899 – 1992)に傾倒しており、反ケインズ的政策を採ったのは当然だ。民営化とは政府部門経済を削ぎ落して「小さな政府」とする政策であり、国民はみな勤勉に倹約して自分で健康に生きて行けということであり、政府の役割は規制緩和して外国人も入れて自由に競わせ、それを監督することだから「大きな政府」は無駄である。労働党の「ゆりかごから墓場まで」政策が財政破綻を招いていたから高福祉国家のカードは捨てざるを得なかったのであり、むしろ治癒には不可避の政策だった。その効果は僕が着任した84年に日常茶飯事たったロンドン地下鉄のストが後になくなったことでも体感された。
たまたま僕はハイエクの
「自由主義」と「保守主義」が混同されるのは両者が反共産主義だからであるが、共通点はただそれだけである。保守主義は現状維持の立場であり、進歩的思想に対する「代案」を持たず、たかだか「進歩」を遅らせることが望みである
という思想に深く賛同しており、以前に書いたように、
人間は現存の秩序をすべて破壊しまったく新しい秩序を建設できるほど賢明ではなく、「自然発生的秩序」が重要で、理性の傲慢さは人類に危険をもたらす
というイギリス経験論者である。サッチャリズムにそれは投影されている。彼女はシティという「英国のドル箱」で、衰退する自国業者を救うのではなく、出る杭だった日系を叩くのでもなく、新たな自然発生的秩序を科学者のような冷静な眼で観察し、手数料、ライセンス自由化を始めとする徹底した開放政策を採った。似非愛国者がどこかの国のように騒いで「弱者切り捨てだ」などと潰さなかったのもさすが大人の国だった。
ハイエクは日本でも人気だが、それを現実の政治にリアライズした希少なケース・スタディとして、マーガレット・サッチャーの業績を若者にぜひ学んでほしいと切に思う。
我が国に目を向けよう。
安倍政権に限らず自民党政治は代々程度の差こそあれ財政で景気を浮揚するケインジアンである。国会議員、公務員の人口比は低く、選良の「公」が「民」を統治する明治以来の考えが根強いため、国家が徴税して全国にバラまく政治にこそ親和性が高い。ハイエクもエリートの方が賢明と考えてはいたが、エリートの理性に頼る経済政策はうまくいかないと考えた。なぜなら、選良とはいえ「市場の参加者の情報や知識をすべて知ることは不可能」であり「参加者達が自らの利益で判断を下す市場こそが最も効率のよい経済運営の担い手である」と結論したからだ。
彼が共産主義とファシズムは同じだというのは、どちらも「理性」に至上の地位を与える合理主義だからだ。どちらも理性より市場の方が賢いとは認めない。しかし、ビル・ゲイツ、ジェフ・ベゾス、イーロン・マスクのような人材は市場におり、国家の研究所にはいない。国が総力で経営してもGAFAやテスラのような企業が生まれるわけでもない。このことこそが経験論者の学ぶべき「市場の経験」であり「自然発生的秩序」なのだと説くハイエクのしなやかな発想は実に魅力的だ。
「エリートはいつも正しい」と大本営が突っ走って戦争に負け、長老の役員が何十人もいる大企業が次々と不祥事を起こしてもまだ旧習を変えない。この頑迷ともいえる可塑性のなさこそがコロナと米中対立で不確実性が何倍にもなる今後において最大の政治リスクになる。そしてその帰趨のツケと膨大な国の借金は次世代に回る。そうであれば、長老世代は早くその世代に道を譲り、それを負うことが自己責任だと納得、理解してもらえるまで徹底した権限移譲を進めるのが彼らのため国のためである。還暦を超えた老人は全員一線から退き、過去の栄光にしがみつかず次世代のサポート役に回ることがポストコロナで日本を蘇らせる最良の政策である。
(7)大きな政府という誤謬
くりかえしになるが、政府は民意さえ得れば何をしてもいい。その民意を代表する国会議員が審議中にスマホをいじったり小説を読んでいても「国家の仕事は回っている」といわれれば、そもそも会社のような「定款」がないのだから人事評価に是も非もなく、そうですかと引きさがるしかない。回っていると主張するなら彼らは実は不要であることを認めるべきだが、業務の定義がないのをよいことに国家、官僚組織というものは組織防衛本能からそうしたスラック(たるみ、遊び)を排除せず、もっともらしい居場所(スラック組織)を作ってしまうことで批判をかわして生き延びようとする。それが贅肉として堆積することで大きい政府が完成するのである。できもしない需要サイドへの関与は高福祉政策の美名をまとって無用の税金を投入するスラック延命策に往々にして利用される。
これぞハイエクが指摘した自由主義に巣食う保守主義である。進歩的思想は歓迎せず、聞いても思考停止し、「ジャイアンはジャイアンであり続けるためにジャイアンである」という確固たる政治信条に基づいてアホな政策が次々と具現化する。仕事を作るのが仕事だから大きい政府はますます肥大化し、気がつけば中国共産党がうらやむ疑似共産主義国家ができあがるのである。自由主義に巣食う共産主義は異様だ。国民は気味の悪さにうすうす気づいている。国会議員の人口比がどうあれスラック=不要であることに変わりはなく、しかもそれが族議員という特定業界に金を回す似非ケインジアンなら百害あって一利ない。ここでもまたまたハイエクは良い事を言っていて、イギリスの保守党が信奉する「伝統」を「既得権の別名」とし「部族社会の道徳」だと批判している。このハイエクを信奉した保守党の党首サッチャーが部族の長でなかったことを特筆したい。
僕はアベノマスクのニュースを聞いた時、エイプリルフールとは思わなかったが共産主義国の政策だとは思った。結果は不評で失敗だったことになっているがそれは政権の足を引っ張りたいだけの者の言い草で、僕はそういう観点で批判的なのではない。むしろあれが供給サイドに関与するという意味で古典的な国家による経済介入政策であることは菅長官が需要抑制効果を強調していることにもうかがえる。その点に関する限り整合的で批判を受けにくい政策であり、だからこそ実は国家のスラック組織に仕事を回すという隠された目的があって、どんなに批判されようがそれは大いに達成したのではないか、政府は満足しているのではないかと考えている。僕が批判的なのはそちらである。
最後に、マックス・ウェーバーに戻ろう。彼は国家しかできない専管事項はないといっているが、近代国家において国防と外交はそれに当たるのではないか。国にあって自治体にないのは防衛省と外務省しかない。原初的国家がジャイアンを必要としたのは他国の野獣から守ってもらうためであり、最も古典的な国家の機能と思う。安倍首相のトランプ就任時の果敢な外交努力は成功であり、7年間日米関係が安定したことを僕は金融市場対策と並んで高く評価する。ここから安倍政権が求めるべきものは五輪の花道ではなく米中の狭間に立って国防と外交の道を誤らないことだと考える。
「構成員がまったく同じような思想を持つ強力で人数の多いグループは、社会の最善の人々からではなく、最悪の人々からつくられる傾向がある」(ハイエク)
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。








