シューベルト交響曲第8番ロ短調D.759「未完成」
2013 MAR 17 12:12:41 pm by 東 賢太郎

シューベルトの音楽は謎めいてエロティックである。
 1797年、モーツァルトが亡くなって6年後のウィーンに生まれた彼は貴族の奉公人になることはなく終生フリーといいますか、ほぼ音楽で食えるかどうか、経済的にはアマチュアとぎりぎりの身でした。知人、友人たちは彼の才能を知っていましたが、スターであったモーツァルトやベートーベンとはちがって大劇場での自作コンサートの機会もなく、金持ちのパトロンがなかったので出版社も特に楽譜出版に積極的ではなかったのです。彼の才能の問題ではありません。フランス革命から約10年たって貴族社会は崩壊の端緒につきました。しかしまだフリーの音楽家がショパンやリストのように自立して活躍するには10~20年早く、彼は節目の難しい時代に生まれてしまったのです。今や魔王やアヴェ・マリア等の歌曲鑑賞は音楽の授業の定番ですから聴いたことのない人は少ないでしょうが、生前の彼からすると同時代人ながら貴族社会で評判をとったべートーベンはエリック・クラプトンのような大スターです。かたや彼は、渋谷のストリートではうまくてかなり有名だけれどもCDを出すほどは売れてない、という一介のギタリストにすぎません。
1797年、モーツァルトが亡くなって6年後のウィーンに生まれた彼は貴族の奉公人になることはなく終生フリーといいますか、ほぼ音楽で食えるかどうか、経済的にはアマチュアとぎりぎりの身でした。知人、友人たちは彼の才能を知っていましたが、スターであったモーツァルトやベートーベンとはちがって大劇場での自作コンサートの機会もなく、金持ちのパトロンがなかったので出版社も特に楽譜出版に積極的ではなかったのです。彼の才能の問題ではありません。フランス革命から約10年たって貴族社会は崩壊の端緒につきました。しかしまだフリーの音楽家がショパンやリストのように自立して活躍するには10~20年早く、彼は節目の難しい時代に生まれてしまったのです。今や魔王やアヴェ・マリア等の歌曲鑑賞は音楽の授業の定番ですから聴いたことのない人は少ないでしょうが、生前の彼からすると同時代人ながら貴族社会で評判をとったべートーベンはエリック・クラプトンのような大スターです。かたや彼は、渋谷のストリートではうまくてかなり有名だけれどもCDを出すほどは売れてない、という一介のギタリストにすぎません。
サリエリという人物について
それでも短い人生のうちにオペラ、交響曲、ピアノ曲、室内楽、宗教曲などほぼすべてのジャンルに作品を残していて、そのどれもが非常にユニークな資質、すぐ先輩であるハイドンともモーツァルトとも違う種を宿しているのです。彼の才能を見抜いて熱心に 指導したのがあの映画アマデウスで犯人役にされてしまったアントン・サリエリ(右)だったというのはもう一つのドラマではないでしょうか。サリエリはモーツァルトの才能には嫉妬したがシューベルトは下に見た?そんなことはありません。 シューベルトは31歳で世を去っていますから、早死にしたモーツァルトよりさらに4年も早死にだったのです。それでいて現在モーツァルトと等しく名を知られるほどの名作をたくさん残しているのですから。サリエリにはベートーベンも教わっています。その事実だけをとっても只者の音楽家にはあるまじきことであり、事実や歴史の歪曲というものの怖さを感じてしまいます。
指導したのがあの映画アマデウスで犯人役にされてしまったアントン・サリエリ(右)だったというのはもう一つのドラマではないでしょうか。サリエリはモーツァルトの才能には嫉妬したがシューベルトは下に見た?そんなことはありません。 シューベルトは31歳で世を去っていますから、早死にしたモーツァルトよりさらに4年も早死にだったのです。それでいて現在モーツァルトと等しく名を知られるほどの名作をたくさん残しているのですから。サリエリにはベートーベンも教わっています。その事実だけをとっても只者の音楽家にはあるまじきことであり、事実や歴史の歪曲というものの怖さを感じてしまいます。
サリエリ犯人説は確かに当時からあってベートーベンも知っていたぐらいですが、動機がありません。ハプスブルグを頂点とした貴族社会が音楽としてまず求めたのは声楽曲、つまりオペラと宗教音楽です。そして当時それらは100%「イタリア語」「ラテン語」の世界だったのです。このことは音楽用語のほとんどがイタリア語であることに今も深くその痕跡を残しています。これは現代においてロックという音楽ジャンルが圧倒的に「英語」世界であるのと似ています。メジャーなレコード会社がドイツ語やスペイン語のロックバンドと契約するでしょうか?だから、いわば当時のロック界の頂点のようなものである神聖ローマ皇帝、オーストリア皇帝の「宮廷楽長」のポストはサリエリのようなイタリア人エリート音楽家以外に与えられるなどということはあり得ず、ドイツ語世界に生まれた楽士の身ではたとえハイドンであれモーツァルトであれベートーベンであれチャンスは皆無だったのです。モーツァルトは「音楽家はコックの隣で食事させられる」と憤慨してフリーの道に飛び込みました。その彼が権力の頂点にあるサリエリを才能で蹴落とす可能性というのはストーリーとしては面白いのですが、後世のモーツァルト神格化のフィクションにおいてのみ成り立つ仮定であり、少しでも権力というものを見知った者であればそれ自体が神話であると結論せざるを得ないでしょう。
モーツァルトはなぜ3大交響曲を書いたのか?
モーツァルトは39-41番のいわゆる3大交響曲を誰に頼まれたとも思えず作りました。これも何か後世に知られていないプロモーション用の動機があったと考えられます。クラプトンやジョン・レノンが女房だけに聴かせようという動機でアルバムを作ることは想像しづらいからです。僕はモーツァルトにとって、ハイドンが確立した弦楽四重奏曲、交響曲というジャンルは「よそ行き」なものであったと感じています。「ハイドンセット」の6曲のカルテット作曲過程は彼らしからぬ涙ぐましい悪戦苦闘でした。3大シンフォニーも(神話上では)彼の音楽帳に記入されている作曲日が示すように「3か月間で書かれた」とされていますが、ハイドンセット以上に簡単に書かれたと信じるに足るほど簡単な曲ではありません。システィーナ大聖堂で証明された彼の楽曲記憶力からして、頭の中で作曲されていたものを「管弦楽譜として記譜するのに3か月かかった」と考えた方が合理的と思います。レクイエムも同じプロセスで、頭にある音楽を病床で譜面に落としながら、突然彼の命が尽きることで「未完成」に終わってしまったことを我々は知っているのです。では何のために?僕の推論ですが、ハイドンがそこで成功して金持ちになった「ロンドン市場」をねらっていたのだと思います。英語も勉強していました。市民革命を経てブルジョアが台頭していたロンドンこそフリーの音楽家が生きられる可能性のある裕福な都市であり、そこのテースト審査に合格して大ヒットした先輩ハイドンの発明になるカルテット、シンフォニーという必ずしも彼の得意科目ではないジャンルで「偏差値」を上げておく必要を感じていたのだと思います。
作曲家には文系と理系がいる?
モーツァルトは不得意科目を克服したばかりか、現在は国立図書館になっている友人のスヴィーデン伯爵の館へ入りびたってバッハ、ヘンデルの楽譜研究に没頭しました。ヘンデルのメサイアの管弦楽編曲やバッハの平均律の弦楽版を作ったりもしています。ジュピター交響曲の終楽章フーガのような傑作はその成果として出てきたわけです。ド~レ~ファ~ミ~という単純な主題から大きな構造物を築くという手法はやがてベートーベンにとっては「主題労作」という彼の作曲法の根幹をなす方法論となり、彼以後のドイツの作曲家に決定的な影響を与えました。そして、わがシューベルトにとって、その主題労作につながる形式論理的な作曲技法は終生「不得意科目」のまま彼の短い人生は終わってしまったというのが僕の持論です。メタファとしてわかりやすく申し上げることに少々誤解をまねくリスクがあることをお許しいただければ、J.S.バッハは非常に高度な数学能力を持った理系作曲家であり、ヘンデルは文系であり、ハイドン、ベートーベン、ブラームス、シェーンベルグはかなり理系であり、モーツァルトは理系並みに数学ができる文系(きわめて稀)です。ショパン、リスト、ワーグナーは文系であり、メンデルスゾーンとシューマンはやや文系寄りであり、ブルックナーはかなり文系、マーラーはほぼ文系であり、そしてシューベルトは完全に文系でした。
なぜ未完成交響曲は未完成で終わったのか?
シューベルトが1822年から書きかけて結局第3楽章の途中で放り出してしまった交響曲ロ短調、のちの未完成交響曲は死後37年もたった1865年に発見されウィーンで初演されました。途中で放り出された曲というと何かわけありの感じがしてしまいますが、シューベルトはモーツァルトと同じぐらい速筆の多作家であって、それも自分のプライベートな取りまきたちによるミニ音楽発表会(シューベルティアーデ)用の歌曲やピアノ曲の作曲に多忙でした。演奏機会の与えられない交響曲に特に積極的になる理由はなく、ベートーベンへの一ファンとしてのあこがれというか、自分もクラプトン流の曲が作れるぞというアピールとして手を染めていたようにも思えます。ちなみにシューベルトは彼の最後のハ長調の交響曲、はるかのちにイギリスの出版社が同じハ長調の第6番と区別して「ザ・グレート」と呼んだものを死ぬ2年前にウィーン楽友協会に献呈しています。崇拝するベートーベンは第九をその2年前に初演していましたから、立派な交響曲を書くということが「ドイツ人作曲家」として社会的認知を得ていくためのいわば「必修科目」化しつつある空気の中を生きていたと思われます(その試験に合格することがいかに後世のドイツ人の作曲家を悩ませたかは、僕のシューマン交響曲第3番のブログをお読みいただければその一端をご理解していただけると思います)。
一種の博士論文提出であった1826年のザ・グレートの献呈の時点で、彼の頭には「未完成」のほうを完成してそれを献呈しようという気がなかったことだけは確かです。忘れるということはないでしょうから何かの理由で見捨ててしまったということです。それが何故かという点については諸説紛々であります。本もたくさん出ていますから是非お読み下い。僕の考えはもう自明と思います。「未完成」の第1,2楽章に彼が盛りこんでしまったあまりにロマンティックでエロティックで、いわば「文系的」なコンテンツ。それは理系的に処理するのが適当な素材でもなく、そうしようと思っても自分の能力がそれに未達であることも彼は自分で知っていたのではないでしょうか。モーツァルトがしたハイドンセット作曲やバッハ研究のような高度な形式論理型作曲技法の基礎技術習得はおそらく積んでいなかったし、それをしたとしても彼の資質からして大輪の花を咲かせたかどうかは疑問のように思います。(さらに余談ですが、未完成と同じロ短調で、同じような暗い闇から湧き起って最後は闇に消えていくという文脈のコンテンツを形式論理で処理した悲愴交響曲を見ると、文系的に見えるチャイコフスキーの理系能力の高さに驚きます)。
シューベルトは交響曲を少なくとも14曲作ろうと試みて6曲が未完で終わっています。6つも「未完成」なのです。なぜロ短調だけ「未完成交響曲」と呼ばれるかというと、その音楽がそれに足る個性と価値をもっているからでしょう。2楽章とも3拍子というのがそもそも常軌を逸していますし、第2楽章のアンダンテがメヌエットなどの舞曲系ではまったくなく、幻想曲というか後世の交響詩的世界を予見する音楽とでもいうようなどこか異常であぶないものを強く感じさせます。最後のページに至る部分でのバイオリンの単音に導かれる、まるであの世に連れて行かれそうな転調。マーラーの9番も遠い子孫と思われるこんなものを書いてしまったらいかにシューベルトの楽想の天才をもってしても後が続かなかったのは納得するしかありません。彼の作曲技法面の制約は措くとして、今度はロ短調交響曲の「コンテンツ」面からの制約について一考しておきたいと思います。
「即興曲」にするか「ピアノソナタ」にするか? どっちでもいいさ
一つのヒントと僕が考えるのは「即興曲」出版の折にシューベルトが「まとめてでもばらばらに別の曲としてでもいい」と出版社に指示している点です。「まとめて」というのはピアノソナタとしてということで、「即興曲D.935の第1,2,4曲はひとつのソナタになる予定だった」 とシューマンは驚くべき主張をしているのです。それほど彼のピアノソナタはベートーベンとは違ってかなり自由な形式で書かれていて、各楽章を個別に幻想曲、即興曲としてもおかしくないケースも多くあるということです。モーツァルトも、有名なトルコ行進曲を第3楽章に持つピアノソナタ第11番K.331という、「ソナタ楽章を一つも持たないピアノソナタ」を書いています。3つの小品をまとめてソナタと呼んでみただけというこのケースに、そのソナタという服が彼にとって普段着ではない「よそ行き」のものだった意識がうかがえます。それがシューベルトの場合は1回や2回ではなくほぼいつもだったということになると、彼にとってソナタやその進化形である交響曲というものは彼の潜在意識下においては単なるイメージラベル、楽譜出版社やお客がわかりやすくて人気が出ればいいというレッテルにすぎなかったのかもしれないと思えてきます。それは自分の音楽コンテンツがソナタのようなロジカルな形式になじまないことを彼が自覚していたためであり、ロ短調交響曲の2つの楽章というのは音楽にこめられたパトス(情念)がシンフォニーという容器からこぼれ落ちてしまっていることを、彼は第3楽章スケルツォを作りながら悟ってしまったのではないでしょうか。
「ソナタとして出版してもいいよ」 と彼が言った即興曲がいかに、モーツァルトのトルコ行進曲以上に、ソナタと呼ぶにはどうもふさわしくないのではないかということを耳でお確かめください。僕が好きな即興曲D.899、D.935のCDを1つご紹介します。ピアノはラドゥ・ルプーです。
 これでD.899の「第1曲ハ短調」を聴いてください。ハ短調と言ってもフラットが3つついているというだけで、ハ短調の部分はあまりなく変イ長調、変ハ長調とどんどん転調します。74小節目から変イ長調で新しい主題が出ますが、どうです、信じられないぐらい美しいでしょう? もうこれは13歳年下であるショパンの出現を予知した主題と和声と言わざるを得ません。ベートーベンの同時代人が書いたものとは到底信じがたいロマンティックの極致であり、このCDのルプーのような触れれば壊れそうなタッチで弾かれるとエロティックに感じるほどです。それから第3曲変ト長調をお聴き下さい。「天国のイメージを音楽で表せ」 と言われれば僕はあなたにこの曲をお聴かせすることになるでしょう。こういう種類の音楽がソナタという型式的な器に収まることの方が不思議なくらいではありませんか。シューベルトの天才は型破りなものであったのです。
これでD.899の「第1曲ハ短調」を聴いてください。ハ短調と言ってもフラットが3つついているというだけで、ハ短調の部分はあまりなく変イ長調、変ハ長調とどんどん転調します。74小節目から変イ長調で新しい主題が出ますが、どうです、信じられないぐらい美しいでしょう? もうこれは13歳年下であるショパンの出現を予知した主題と和声と言わざるを得ません。ベートーベンの同時代人が書いたものとは到底信じがたいロマンティックの極致であり、このCDのルプーのような触れれば壊れそうなタッチで弾かれるとエロティックに感じるほどです。それから第3曲変ト長調をお聴き下さい。「天国のイメージを音楽で表せ」 と言われれば僕はあなたにこの曲をお聴かせすることになるでしょう。こういう種類の音楽がソナタという型式的な器に収まることの方が不思議なくらいではありませんか。シューベルトの天才は型破りなものであったのです。
未完成交響曲は、これらの即興曲とは見かけの曲想こそまったく違いますが、2つの楽章に盛りこまれたロマン的な楽想や和声の自由な変化においてはほぼ比肩しえるシューベルティアンな濃い内容を持っています。それは、まさに即興曲がそうであったように、同時代人であったベートーベンのどの交響曲とも異なるものでした。結局これが放置されたのは、通説が言うようにここで満足してしまったのか、書くつもりがうまく書けなくなってしまったのか、それとも忘れてしまったのか既に誰かに売却済だったのか・・・。真相は闇の中ですが、交響曲としては行き詰ってしまったまま引き出しにしまっているうちに人生の灯が消えてしまったというところではないでしょうか。ここでのシューベルトの行き詰まり感を起点として、新しい交響曲へ弁証法的発展を果たした作曲家こそブルックナーであったと僕は考えています。
この交響曲の演奏は、即興曲に近接したロマン、パトスを主体として表現するもの、それから、あくまで古典交響曲の脈絡の中でシンフォニーとしてとらえるものの両極端があります。前者はフルトヴェングラー、ワルター、クナッパーツブッシュが代表でしょう。僕は、上記の理由から前者のほうがよりシューベルトの本能的なイマジネーションを抉り出していると考えますが、同時に、一度は彼がそれをシンフォニーというフォーマットで発想した点も無視できないと思っています。ですから好みの問題になりますが、ここでは後者寄りのCDを中心にご紹介しておきましょう。
ヨゼフ・カイルベルト/ バンベルグ交響楽団
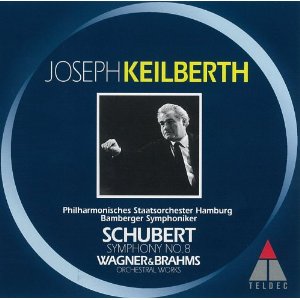 この曲の古典性とロマン性が見事に均衡した名演です。第1楽章はまさにソナタ形式の立派な第1楽章でありシューベルトがシンフォニーというメディアをまず選択した意図が非常に明確に伝わってくる演奏でもあります。第2楽章は一転してロマンティックで幻想的な楽想を過不足なく生かしているのですが、それでも第2バイオリンやビオラが目立たない裏のキザミを律儀に気真面目にドイツ人らしく一生懸命やっており、僕はそういうところが好きなのです。このCDと同じシリーズで発売されたブラームスでのアプローチを踏襲しています。バンベルグ響というオケはフランクフルト時代にホルスト・シュタインの指揮で何度か聴き、その「ドイツ語の」音楽造り、とりわけそれが奏功したベートーベンとブラームスを心から楽しんだ思い出があります。この未完成もなんら特別な力こぶが入っていない、ドイツの地方で普通にやっている演奏会の記憶と重なるのです。やはり僕はドイツが、ドイツ音楽が大好きであり「おふくろの味」になっているんだなとしみじみ思います。
この曲の古典性とロマン性が見事に均衡した名演です。第1楽章はまさにソナタ形式の立派な第1楽章でありシューベルトがシンフォニーというメディアをまず選択した意図が非常に明確に伝わってくる演奏でもあります。第2楽章は一転してロマンティックで幻想的な楽想を過不足なく生かしているのですが、それでも第2バイオリンやビオラが目立たない裏のキザミを律儀に気真面目にドイツ人らしく一生懸命やっており、僕はそういうところが好きなのです。このCDと同じシリーズで発売されたブラームスでのアプローチを踏襲しています。バンベルグ響というオケはフランクフルト時代にホルスト・シュタインの指揮で何度か聴き、その「ドイツ語の」音楽造り、とりわけそれが奏功したベートーベンとブラームスを心から楽しんだ思い出があります。この未完成もなんら特別な力こぶが入っていない、ドイツの地方で普通にやっている演奏会の記憶と重なるのです。やはり僕はドイツが、ドイツ音楽が大好きであり「おふくろの味」になっているんだなとしみじみ思います。
ハンス・クナッパーツブッシュ/ ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(1950年1月30日ライブ)
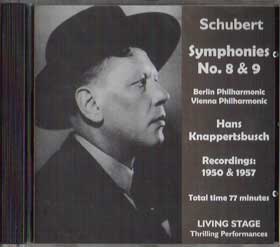 ものすごい演奏です。第1楽章。地獄の底から鳴り響くような低弦のうねりとあまりの遅さは不気味なほどで、伴奏の弦のキザミもごつごつして女性的なものは皆無の厳しさです。金管とティンパニの強打は怒りをぶつけるよう。指揮者がこの楽章に見ているものは強烈な情念であって古典的シンフォニーという風情など微塵もありません。第2主題は一転やさしく、ポルタメントがかかってロマン派の音楽のようですが、すぐに厳しさが戻ります。展開部の荒れ狂い方もシューベルトの範疇をこえていてこの曲にこんな極北の厳しさがあったのかと居ずまいを正すしかありません。コーダはかなりアンサンブルがずれていてこの日の指揮がことさら気合いにあふれた即興性の高いものだったことを感じます。第2楽章は普通のテンポで夢見るように始まりますがすぐに雪崩のようなトゥッティに見舞われて現実に引き戻されます。中間部のつかの間の長調部分、オーボエ、クラリネットが歌う旋律も彼岸を見るようで、やがてバイオリンのユニゾンが導く「あちらの世界」を垣間見る転調が魂をいざなうような、まさにこの2楽章の音楽が地獄から湧き起って天国へ昇天するようなドラマとして見えてきます。シューベルトの脳裏をよぎり、彼が閉じ込めようとした「シンフォニーの殻を突き破ってこぼれ出てしまったもの」の正体見たりと呟くしかありません。57年ウィーンフィルとの9番ライブも同様に衝撃的な演奏であり、ものすごいの一言しか表現のすべがありません。シューマンに、ブルックナーに、そしてマーラーに伝播していったシューベルトのDNAが手首に青く浮かぶ血管のように浮き彫りになった感じのする演奏で、この曲がこんな曲かと問われれば決定的にNOと答えるのですが、演奏家がスコアから何を読み取り何を表現するのか、彼はその表現にどれほど命を懸けているのかということへの一つの電撃的な回答です。うわべをなぞるきれいごとの演奏ではなく、演奏家が作品解釈をしてつけ加えるべき「演奏芸術」というものの奥深さを知る意味で非常な価値を感じます。クナッパーツブッシュという異形の指揮者の凄さをこんなに如実に伝える演奏もあまりありません。会場ノイズはありますが録音も非常になまなましく、ムジークフェラインの前の方で聴くような手に汗握る稀有の体験ができます。このCDは聴衆のみならず演奏家の方こそ一聴されることを強くお勧めします。
ものすごい演奏です。第1楽章。地獄の底から鳴り響くような低弦のうねりとあまりの遅さは不気味なほどで、伴奏の弦のキザミもごつごつして女性的なものは皆無の厳しさです。金管とティンパニの強打は怒りをぶつけるよう。指揮者がこの楽章に見ているものは強烈な情念であって古典的シンフォニーという風情など微塵もありません。第2主題は一転やさしく、ポルタメントがかかってロマン派の音楽のようですが、すぐに厳しさが戻ります。展開部の荒れ狂い方もシューベルトの範疇をこえていてこの曲にこんな極北の厳しさがあったのかと居ずまいを正すしかありません。コーダはかなりアンサンブルがずれていてこの日の指揮がことさら気合いにあふれた即興性の高いものだったことを感じます。第2楽章は普通のテンポで夢見るように始まりますがすぐに雪崩のようなトゥッティに見舞われて現実に引き戻されます。中間部のつかの間の長調部分、オーボエ、クラリネットが歌う旋律も彼岸を見るようで、やがてバイオリンのユニゾンが導く「あちらの世界」を垣間見る転調が魂をいざなうような、まさにこの2楽章の音楽が地獄から湧き起って天国へ昇天するようなドラマとして見えてきます。シューベルトの脳裏をよぎり、彼が閉じ込めようとした「シンフォニーの殻を突き破ってこぼれ出てしまったもの」の正体見たりと呟くしかありません。57年ウィーンフィルとの9番ライブも同様に衝撃的な演奏であり、ものすごいの一言しか表現のすべがありません。シューマンに、ブルックナーに、そしてマーラーに伝播していったシューベルトのDNAが手首に青く浮かぶ血管のように浮き彫りになった感じのする演奏で、この曲がこんな曲かと問われれば決定的にNOと答えるのですが、演奏家がスコアから何を読み取り何を表現するのか、彼はその表現にどれほど命を懸けているのかということへの一つの電撃的な回答です。うわべをなぞるきれいごとの演奏ではなく、演奏家が作品解釈をしてつけ加えるべき「演奏芸術」というものの奥深さを知る意味で非常な価値を感じます。クナッパーツブッシュという異形の指揮者の凄さをこんなに如実に伝える演奏もあまりありません。会場ノイズはありますが録音も非常になまなましく、ムジークフェラインの前の方で聴くような手に汗握る稀有の体験ができます。このCDは聴衆のみならず演奏家の方こそ一聴されることを強くお勧めします。
オイゲン・ヨッフム/ ボストン交響楽団
 管の音色にやや明るさを感じますがボストンシンフォニーホールの素晴らしい音響に救われており、ヨッフムの造る重心の低いがっしりした音楽の素晴らしさは充分に伝わってきます。カイルベルトと同様に古き良き時代の職人芸を感じさせる実直で飾りのないアプローチがいいです。しかしカイルベルトとは対照的にブラームスの北ドイツではなくブルックナーに繋がる南ドイツ系の音楽として解釈しているのが特色で、第1楽章のチェロ旋律の扱いなどロマン派のようであり第2主題のクラリネットもデリケートに吹かせています。シューベルトの音楽がどう後世に影響したかというドイツ音楽史を知る我々は、こういう演奏が現代オケによる未完成らしい演奏と聴くようになっています。しかし作曲当時のシューベルトの意図はあくまで「シンフォニー」だったわけで、ファーストチョイスとしてこれをとるかカイルベルトをとるかは見解が分かれるところだろうと思います。
管の音色にやや明るさを感じますがボストンシンフォニーホールの素晴らしい音響に救われており、ヨッフムの造る重心の低いがっしりした音楽の素晴らしさは充分に伝わってきます。カイルベルトと同様に古き良き時代の職人芸を感じさせる実直で飾りのないアプローチがいいです。しかしカイルベルトとは対照的にブラームスの北ドイツではなくブルックナーに繋がる南ドイツ系の音楽として解釈しているのが特色で、第1楽章のチェロ旋律の扱いなどロマン派のようであり第2主題のクラリネットもデリケートに吹かせています。シューベルトの音楽がどう後世に影響したかというドイツ音楽史を知る我々は、こういう演奏が現代オケによる未完成らしい演奏と聴くようになっています。しかし作曲当時のシューベルトの意図はあくまで「シンフォニー」だったわけで、ファーストチョイスとしてこれをとるかカイルベルトをとるかは見解が分かれるところだろうと思います。
カルロス・クライバー / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
 大変に主張の強い硬派の演奏です。表現主義的と言ってもいい。文学青年的になよなよした未完成とは対極の表現ですが、ウィーンPOのチャーミングな管楽器と練り絹のような弦楽器の魅力は満開であり、クライバーの高い集中力と見事に融和してひとつの完結したシンフォニーを聴いたという印象を与えてくれます。この演奏がCDで出た80年代中ごろ、どろどろした情念にたよらない新時代の未完成という新鮮な感じで受け止めましたが、現代は古楽器演奏がそのイメージは凌駕してしまっています。しかしクライバーの表現意欲の強さは何人も凌駕することは容易ではなく、天下のウィーンPOをここまで自在にコントロールするのも容易ではないでしょう。3番の方も名演です。
大変に主張の強い硬派の演奏です。表現主義的と言ってもいい。文学青年的になよなよした未完成とは対極の表現ですが、ウィーンPOのチャーミングな管楽器と練り絹のような弦楽器の魅力は満開であり、クライバーの高い集中力と見事に融和してひとつの完結したシンフォニーを聴いたという印象を与えてくれます。この演奏がCDで出た80年代中ごろ、どろどろした情念にたよらない新時代の未完成という新鮮な感じで受け止めましたが、現代は古楽器演奏がそのイメージは凌駕してしまっています。しかしクライバーの表現意欲の強さは何人も凌駕することは容易ではなく、天下のウィーンPOをここまで自在にコントロールするのも容易ではないでしょう。3番の方も名演です。
ギュンター・ヴァント / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
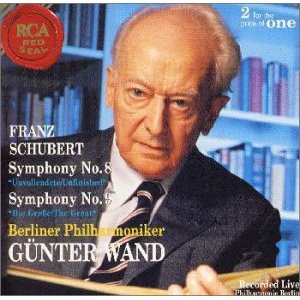 こちらも大変硬派、頑固おやじ派です。完全にシンフォニーとして振っています。僕は94年にフランクフルトでヴァントの指揮するブルックナーの第8交響曲を聴きましたが、これはひとつの事件でした。ブルックナーのシンフォニーは長大かつロマン的要素に横溢し、形式論理性を感じさせる演奏にはそうは出合いません。実演で言えばこのヴァントと83年にフィラデルフィアを振ったスクロヴァチェフスキーの2人の硬派指揮者以外、まったく感じたことはないのです。このシューベルトもライブですが、あのブルックナーを思い出させる骨太の、しかし音楽の情感を細部までくみ取った充分にロマンティックな要素もある名演です。ピアニッシモになっても音が痩せない高い集中力、素晴らしい弦の合奏力、魅力的な管の音色。ぜひお聴きいただきたいCDです。より古典的アプローチになじむ9番の方もまったく同じスタイルで押し通しており、格付けでいえばトリプルAドイツオーケストラによるトリプルAドイツ音楽です。このCDは世界の一級品のみが与えてくれる「所有する充実感」まで約束してくれます。
こちらも大変硬派、頑固おやじ派です。完全にシンフォニーとして振っています。僕は94年にフランクフルトでヴァントの指揮するブルックナーの第8交響曲を聴きましたが、これはひとつの事件でした。ブルックナーのシンフォニーは長大かつロマン的要素に横溢し、形式論理性を感じさせる演奏にはそうは出合いません。実演で言えばこのヴァントと83年にフィラデルフィアを振ったスクロヴァチェフスキーの2人の硬派指揮者以外、まったく感じたことはないのです。このシューベルトもライブですが、あのブルックナーを思い出させる骨太の、しかし音楽の情感を細部までくみ取った充分にロマンティックな要素もある名演です。ピアニッシモになっても音が痩せない高い集中力、素晴らしい弦の合奏力、魅力的な管の音色。ぜひお聴きいただきたいCDです。より古典的アプローチになじむ9番の方もまったく同じスタイルで押し通しており、格付けでいえばトリプルAドイツオーケストラによるトリプルAドイツ音楽です。このCDは世界の一級品のみが与えてくれる「所有する充実感」まで約束してくれます。
(補遺、3月8日)
ウィルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
 52年2月10日、ベルリン・ティタニアパラストでのライブ録音。フルトヴェングラーの未完成は8種類ある。録音の具合も含めると全部が別ものであり、僕の趣味は圧倒的にこの52年盤を支持する。この演奏会で後半に演奏されたブラームスの交響曲第1番はまぎれもない歴史的名演であり(ブラームス 交響曲第1番ハ短調作品68)、前座のこの未完成もただならぬ緊張感が支配して耳をくぎづけにされる。第1楽章は淡々と開始するが緩急強弱のメリハリが素晴らしく、弦は歌い、明瞭なティンパニを伴った有機的なトゥッティがコクと深みを添える。第2楽章の第2主題を導く絶妙のリタルダンド、そしてコーダのヴァイオリンが虚空に単音を伸ばして転調する虚無感など見事にきまっており、フルトヴェングラーならではの芸域の最高峰にある演奏と絶賛したい。
52年2月10日、ベルリン・ティタニアパラストでのライブ録音。フルトヴェングラーの未完成は8種類ある。録音の具合も含めると全部が別ものであり、僕の趣味は圧倒的にこの52年盤を支持する。この演奏会で後半に演奏されたブラームスの交響曲第1番はまぎれもない歴史的名演であり(ブラームス 交響曲第1番ハ短調作品68)、前座のこの未完成もただならぬ緊張感が支配して耳をくぎづけにされる。第1楽章は淡々と開始するが緩急強弱のメリハリが素晴らしく、弦は歌い、明瞭なティンパニを伴った有機的なトゥッティがコクと深みを添える。第2楽章の第2主題を導く絶妙のリタルダンド、そしてコーダのヴァイオリンが虚空に単音を伸ばして転調する虚無感など見事にきまっており、フルトヴェングラーならではの芸域の最高峰にある演奏と絶賛したい。
ディアナ大学の管弦楽団。ドビッシーの牧神の稿でも紹介しましたがアマチュアでも有能な指揮者がいればここまでできる。まだ知られておらず僕も初めてだが、指揮者Hao-An (Henry) Cheng の造形力はとてもいい。高い才能を感じる。
(補遺、3月27日)
ルドルフ・ケンぺ / バンベルグ交響楽団
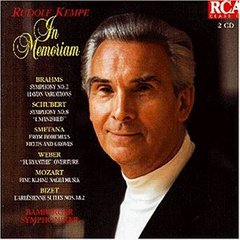 第1楽章はトランペット、ティンパニを強奏するなど激しい表現で、ベートーベンに近いドイツ式の交響曲のスタイルを堅持する。ケンぺはチャイコフスキーを振ってもこうだった。そこが好悪を分かつだろうが僕は好きだ。絶えず緊張感があり、ホルンの和音は重く、トロンボーンのそれは暗い。第2楽章は束の間の安寧を得るものの、ヴァイオリンの単音が静寂を囲って短調を導くと風景が寒色になる。暖色の木管が一時の彩りをそえるがティンパニが不吉な暗さで雰囲気を戻す。この曲、同じロ短調の悲愴交響曲に影を落としているかもしれない。そう思わせられるインパクトある演奏と思う。
第1楽章はトランペット、ティンパニを強奏するなど激しい表現で、ベートーベンに近いドイツ式の交響曲のスタイルを堅持する。ケンぺはチャイコフスキーを振ってもこうだった。そこが好悪を分かつだろうが僕は好きだ。絶えず緊張感があり、ホルンの和音は重く、トロンボーンのそれは暗い。第2楽章は束の間の安寧を得るものの、ヴァイオリンの単音が静寂を囲って短調を導くと風景が寒色になる。暖色の木管が一時の彩りをそえるがティンパニが不吉な暗さで雰囲気を戻す。この曲、同じロ短調の悲愴交響曲に影を落としているかもしれない。そう思わせられるインパクトある演奏と思う。
(補遺、2018年8月26日)
スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ミネアポリス交響楽団
 Mercury Living Presenceの録音はオケに近接したマイクセッティングで細部まで克明に描き出し是か非かは好みを分かつ。ところがスクロヴァチェフスキーの演奏は、その録音特性のなかでロ短調のこの曲のはらむ葬送のごとき不気味、不吉な側面を感じさせるという結果になっている。それは一にも二にもピッチと楽器間のバランスが抜群で(第1楽章のティンパニのピッチなど感涙もの、それでこそ不吉に響くという不思議なことになっている)、指揮者の尋常でない耳の良さと奏者のプロフェッショナリズムが解釈の方向にピタッとはまっている成果だ。最も音楽的に美しく、本質を突いた未完成と思う。
Mercury Living Presenceの録音はオケに近接したマイクセッティングで細部まで克明に描き出し是か非かは好みを分かつ。ところがスクロヴァチェフスキーの演奏は、その録音特性のなかでロ短調のこの曲のはらむ葬送のごとき不気味、不吉な側面を感じさせるという結果になっている。それは一にも二にもピッチと楽器間のバランスが抜群で(第1楽章のティンパニのピッチなど感涙もの、それでこそ不吉に響くという不思議なことになっている)、指揮者の尋常でない耳の良さと奏者のプロフェッショナリズムが解釈の方向にピタッとはまっている成果だ。最も音楽的に美しく、本質を突いた未完成と思う。
関連記事です:ノリントン・N響のシューベルトを聴く
クラシック徒然草-モーツァルトの3大交響曲はなぜ書かれたか?-
シューベルト交響曲第9番ハ長調D.944「ザ・グレート」
Categories:______シューベルト, クラシック音楽






花崎 洋 / 花崎 朋子
3/18/2013 | 8:41 AM Permalink
未完成交響曲、好きな交響曲を5つ挙げよと言われれば、おそらく、その中に入るくらい気にいっております。作曲家を「理系」と「文系」に分ける・・・初めて伺い、たいへん新鮮な発想で、興味深く読ませていただきました。おっしゃる通り、チャイコフスキーは文系に見えて、実は理系であると私も思います。造型がしっかりしていて、たいへん論理的でもありますね。それに対してシューベルトはショパンと並んで典型的な文系ですね。「未完成交響曲」が未完成で終わった理由、私も、3楽章以降を何とかしなくてはと思ってはいるものの、完成済みの2つの楽章に釣り合うものを書けないでいる内に世を去ってしまったと、以前から思っていました。未完成交響曲を、理系的アプローチと文系的アプローチ、両者を意識して聴き分けるという、新しい楽しみ方が増えて、今後楽しみです。ところで、未完成の遺稿を発見し、世に紹介したのは、メンデルスゾーンでしたか? 花崎洋
東 賢太郎
3/18/2013 | 11:37 AM Permalink
いえ、それは9番です(発見したのはシューマンですが)。8番はヒュッテンブレンナーという友人に預けられていて、ヨハン・フォン・ヘルベックという人が、グラーツにあるヒュッテンブレンナーの家を訪問し、その楽譜をウィーンに持ち帰って初演しました。このいきさつは謎で、映画にもなっているようです。
花崎 洋 / 花崎 朋子
3/18/2013 | 3:06 PM Permalink
東さん、有り難うございます。シューマンが9番を発見し、8番は友人に預けられていたのですね。未完成のもう一つの謎ですね。正しい知識が得られまして良かったです。花崎洋
東 賢太郎
3/18/2013 | 9:13 PM Permalink
9番はホルンによる第1主題で開始というアイデアが当時としては奇想天外で卓抜ですが、シューマンがそれを発見したのは1838年で1841年に自身の1番を書きました。これも金管で始まりますね。ブラームスのピアノ協奏曲2番もそうですしチャイコフスキーの4番にも影響があるかもしれません。
花崎 洋 / 花崎 朋子
3/19/2013 | 11:23 AM Permalink
なるほどですね。現在の聴衆たちは、チャイコフスキーの4番の方を先に聴いている人も多く(私もそうでした)、シューベルト9番の冒頭もそれほどは驚きませんが、いきなり、ホルンによる第一主題、当時の人にとっては、まさに奇想天外で斬新に聞こえたことでしょう。この奇抜さも、文系的天才のシューベルトの面目躍如でしょうか?
話は脇に外れてしまいますが、以前、ウィーンフィル創立150周年を記念して出されたCD集(私は持っていませんが)の中に、あのクナッパーツブッシュ指揮の「ザ・グレート」が入っていて、聴衆への挨拶を極度に面倒に思っていた彼は、何と、聴衆の拍手が鳴り止まない内に、あのホルンの主題を始めているそうです。
東 賢太郎
3/19/2013 | 11:35 AM Permalink
おっしゃる通りです。それも速めのテンポで素っ気なく始めています。あの長大なドラマを始めようというのですから舞台に出たときはすでに集中力が高まっていて儀礼などうとましかったのではないでしょうか。他に似たものはないほど特別の解釈で第4楽章コーダのギアチェンジなどきっとシューベルトが聴いても度肝をぬかれるでしょうが、ここまで自信を込めてやられるとねじ伏せられて何も言えません。指揮者かくあるべしです。
花崎 洋 / 花崎 朋子
3/20/2013 | 9:01 AM Permalink
そのCD、やはり東さんお持ちだったのですね。集中力が高まり、早く演奏に入りたいとの気持ち、分かるような気がします。それにしても、ハイドンのV字交響曲の第4楽章のメインのテンポの異様な遅さとコーダの猛烈なギアチェンジや、モーツアルトのアイネクライネの第4楽章など、まさにやりたい放題で、クナッパーツブッシュの怪物ぶりが良く出ており、ねじ伏せられ、私も何も言えなくなってしまいます。今の時代には、ここまで強烈な個性を持った指揮者はいませんね。花崎洋
Trackbacks & Pingbacks
[…] この曲の作曲当時、交響詩というジャンルはありません。ロマン派という概念もありません。もしその両方があったら、ベートーベンはこの曲のコンテンツを交響詩にしただろうか?僕の想像はノーです。彼はやはり交響曲を書きたかったのであり、彼の関心はそれとpastoral 風コンテンツの融合にあったと思います。未完成交響曲の稿で僕はシューベルトの直面したと思われる同じ問題を論じました(シューベルト交響曲第8番ロ短調D.759「未完成」)。交響曲というロジックとそれになじまないコンテンツ(ストーリー)。両者を融合することはシューベルトには難題でした。しかし変奏の達人であったベートーベンはその見事な解答をこの曲で提示しています。交響曲では変奏という技法はソナタ形式の展開部に主に披瀝されるものですが、それを展開部以外でも駆使する。そうしてソナタ楽章のいたるところに判じ物のようにストーリーを暗示するキャラクターを刻印することでそれを切り抜けているのです。 […]