魔笛とフランス革命-妙な台本の謎を解く-
2019 NOV 15 0:00:59 am by 東 賢太郎

 「魔笛とフリーメーソン」なら世の中には書物があふれていて、メーソンを象徴する数字は3だから序曲の最初に和音が3回鳴るとか変ホ長調は♭が3つだとか、真実かもしれないがそうであってもなくてもまったくどうでもいいことが書いてある。では「魔笛とフランス革命」はとなると、自由・平等・博愛にひっかけたものは見たことがあるがそれはメーソンのスローガンにすぎないのであって、革命との抜き差しならぬ関連を論じたものは少なくとも僕は知らない。そこで、本稿ではその表題で僕の仮説を述べることにする。
「魔笛とフリーメーソン」なら世の中には書物があふれていて、メーソンを象徴する数字は3だから序曲の最初に和音が3回鳴るとか変ホ長調は♭が3つだとか、真実かもしれないがそうであってもなくてもまったくどうでもいいことが書いてある。では「魔笛とフランス革命」はとなると、自由・平等・博愛にひっかけたものは見たことがあるがそれはメーソンのスローガンにすぎないのであって、革命との抜き差しならぬ関連を論じたものは少なくとも僕は知らない。そこで、本稿ではその表題で僕の仮説を述べることにする。
矛盾するようだが、やっぱりそれを論じるにはフリーメーソンの話から説き起こす努力は避けて通れない。なぜなら、わが国ではフリーメーソンという言葉を持ち出しただけで「まゆつば物だね」と思考停止する人があまりに多いからだ。歴代アメリカ合衆国大統領のうち15人も関与があったメーソンがいかがわしいのにアメリカという国家はそうではないという理屈がどこかの教科書にでも書いてあるなら別だが、思考停止はあまり科学的態度とは言えない。
ニューヨークの自由の女神像の正式名称は “Liberty Enlightening the World” であり、「女」や「神」などが勝手に出てきてしまって誰も不思議と思ってない日本人の感性と、フリーメーソンをいかがわしいと意識させる感性とは近親関係にあるように思う。Enlightenmentというと、我々が世界史で習う「啓蒙思想」なるものがこれの英語であり、フランス語は Lumièresであることでわかるがラテン語の lumen(光)が語源であり、ルーメンは物理学で光束の単位になっている。啓蒙思想は封建社会の宗教的世界観に動揺を与え自然科学や近代哲学の伸展のエンジンとなったが、王侯の側にも啓蒙的君主となって新たな統治の道具と見立てる者が現れるほどの影響力があった。
”女神さん” のパワーは絶大であり、キリスト教的世界観が揺らいで教皇・教会の権威が揺らぎ、民衆は「ところで王権神授説ってなんだっけ?」と目覚め、絶対主義諸国のガバナンスの正当性が根源から崩壊していくというドミノ現象にいたる。このムーヴメントが暴力という実力行使を伴って最も先鋭化した国がフランスであり、Enlightenment はフランス革命の思想的基盤になった。「啓蒙」はニュアンスが丸まった訳語で僕は教室で意味がさっぱり分からなかったが、要するに、未開、愚鈍な者にぴかっとウルトラマンのスペシウム光線のように叡智の光を浴びせて賢くしてやるという意味だから「教化」が原意である。フランス革命とは、それを実践したものだとして貴族の殺戮という殺人罪を正義に変えてしまった後付けの美名である。英国がアドバイザーとなって旧体制打破に成功した明治政府も自らの政権奪取の正当性をそれに倣おうとしたが、さすがに革命はうしろめたかったのだろう、極めて日本的なソリューションとして天皇を前面に立てた王政復古をしておいて、殺戮の方は維新なる雅称に置き換えた。
”女神さん” が右手で高く掲げるトーチはEnlightenment光線で世界を教化してくださるのだが、この像は当初はフランスの彫刻家でフリーメーソンであるフレデリク・バルトルディ、エッフェル塔の設計者でやはりメーソンであるギュスターヴ・エッフェルらが1867年のスエズ運河開通式でエジプトに贈る「イシス神像」だった。イシスなら ”女神さん” でも “観音さん” でもよかったかもしれないが、エジプトに拒否されたので構図を変えてニューヨーク市にもらわれることになった。寄贈者はフランス最大のフリーメーソン・ロッジであるGrand Orient deFranceで、受贈者はGRAND MASTER OF MASONS IN THE STATE OF NEW YORKと台座にある。
つまり、自由の女神はフランスのメーソンが、初のメーソン国家であるアメリカ合衆国の建国百周年を祝してアメリカのメーソンに贈ったプレゼントだった。僕が卒業したウォートン・スクールはペンシルバニア大学の経営大学院だが、同校は1740年にベンジャミン・フランクリンらが創立したアメリカ最初の総合大学だ。フランクリンといえば避雷針とくるのが我々日本人だが、フランスをアメリカ独立戦争に参戦させ、それに勝利して1776年に独立宣言を起草した男ということの方がよほど重要だ。彼がそういう活躍をできたのもグランド・マスターというフリーメーソンのロッジの最高幹部だったからである。
アメリカ独立革命はFrench Revolutionに習ってAmerican Revolutionと呼ばれる。絶対王政支配の打破、植民地支配の打破はどちらもEnlightenmentがもたらした勝利であるという点でメーソンにとっては同質であったからだ。アメリカがパリ条約を締結してイギリスから法的に独立したのが1783年で、その翌年にモーツァルトはフリーメーソンに入会している。そこで得た情報からやがてEnlightenmentのご本家であるフランスでも何かおきると感じたはずだが、まさか国王、王妃がコンコルド広場で斬首されるとは夢にも思っていなかったろう。
地元ウィーンでの揺動を期待して1786年に「フィガロの結婚」を仕立てたが、後に「皇帝ティトの慈悲」を書くように、彼はハプスブルグ王政が壊れることを予想も期待もしていない。ウィーンでの Enlightenment がヨーゼフ2世をさらなる啓蒙的な名君へと導けば出世を阻む守旧派のダニのごとき取り巻き貴族を一掃してくれ、ひいてはイタリア人のサリエリを排除するか悪くても後継者になれるかもしれないぐらいの期待であったと考えるのが順当であろう。彼はオペラハウスを席巻したかった。フィガロで政治的揺動をしつつ作曲家としての実力のデモンストレーションもすることは一石二鳥であり、二重のモチベーションから稀代の名作が生まれたと思われる。
フィガロがメーソン情報を動機としたオペラなら、魔笛はメーソンを描いたオペラであるというのが通説だ。確かに、先日のワルシャワ室内歌劇団の上演を見ていて、第2幕以降は入会儀式ばかりであり、もしパパゲーノ、パパゲーナがいなければさぞかしつまらないオペラになったろうと感じていた。しかし、わからないことがあった。彼はなぜ、基本的に何らセクシーではない題材であるメーソンのオペラを書く気になったのかということだ。前年に共作した「賢者の石、または魔法の島」がそこそこ当たっており、魔笛とは数々の共通点があることから二匹目のどじょうを狙ったという指摘もあるものの、両作品の出来栄えは比べるのもアホらしく書く気もしない。
それだけだろうか?僕は同じ1791年の、どちらも彼自身の作である「皇帝ティトの慈悲」と「魔笛」のクオリティの差(これは誰が聴いてもわかる、雲泥の差だ)がとても気になっていた。フィガロがそうだが彼はモチベーションの多寡が作品に出る人で、モーツァルトに駄作はないなんてことはない。魔笛の音楽の質の高さは彼の全作品を見渡してもダントツであり、それがあの妙ちくりんなストーリーについている、何なんだそれは?というのが長年僕の解けない謎だった。それが先日、上野の東京文化会館で、ある仮説が浮かんだ。音楽が Enlightenment をくれたのかもしれない。
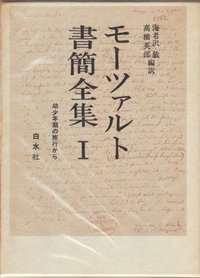 白水社のモーツァルト書簡全集6巻は計5回読んだ。再読しない主義だから愛読書といえる。本書は父子によって書かれ、読者の関心の在り方で多様な光を放つ秀逸なドキュメントだが、まずは彼の旅の足跡を辿るのが楽しい。あれっ、あんなところに彼は行ったのかという発見があり、例えば父とナポリからポンペイの遺跡を見物しに出向いている。その行程は車で辿ったことがあるが、ベスビオ火山はモーツァルトの当時は活動期で噴煙を吐いており、イシス神殿には装飾や備品がほとんど当時のままに残っていてポンペイを世界に知らせるのに貢献したそうだ。僕は27才のころそこで目の当たりにした光景が脳裏に焼きついて、庭の噴水から引いた水が美しいモザイクを敷いた居間の溝を涼やかに流れるポンペイ式の家に住みたいと思うようになってしまった。
白水社のモーツァルト書簡全集6巻は計5回読んだ。再読しない主義だから愛読書といえる。本書は父子によって書かれ、読者の関心の在り方で多様な光を放つ秀逸なドキュメントだが、まずは彼の旅の足跡を辿るのが楽しい。あれっ、あんなところに彼は行ったのかという発見があり、例えば父とナポリからポンペイの遺跡を見物しに出向いている。その行程は車で辿ったことがあるが、ベスビオ火山はモーツァルトの当時は活動期で噴煙を吐いており、イシス神殿には装飾や備品がほとんど当時のままに残っていてポンペイを世界に知らせるのに貢献したそうだ。僕は27才のころそこで目の当たりにした光景が脳裏に焼きついて、庭の噴水から引いた水が美しいモザイクを敷いた居間の溝を涼やかに流れるポンペイ式の家に住みたいと思うようになってしまった。
ポンペイは13才のモーツァルトにも鮮烈な印象を残したろう。ところが手紙には感想や心情に類するものが何も書かれていないものだから、僕はしばらくは彼がそういうものに無関心で不感症かもしれないと思い込んでいた。しかし、そうではないのだ。魔笛の舞台であるエジプトに行ったことがなくとも、彼はポンペイ遺跡のイシス神殿は見知っている。それが第2幕の合唱、“O Isis und Osiris” と歌われるように魔笛の借景となったのではないだろうか。
足跡ばかりではない、書簡集はモーツァルトや家族をとりまく日々の雑多な人間模様やふりかかる難事を通じ彼が何を思いどう行動したかをリアルタイムで一緒に体験し、肌で共感できる場だ。彼はわがままで自信家で幾度も度を越し、失言し、チャンスを逃し、親にもらったものの大きさにしてはコスパの悪い人生を生きた。もっと楽に生きられたろうし、いくつかオファーのあったマイナーなポストを謙虚に受けていれば良いご縁に恵まれたかもしれない。ロンドンへフィガロをもって行っていれば英国人に最高のエンタメとなってハイドン以上の人気を博し、間違いなく億万長者になったろう。
しかし、彼はそうしなかった。自分ではどうしようもない身分の壁に怯むことなく立ち向かった。書簡の随所に感じられるが、彼は王侯貴族など心中では馬鹿にしきって歯牙にもかけぬ超然とした能力主義者であり、強者が報われて当然とする資本主義的思想の持主であり、ビッグ・スペンダーのエピキュリアンであった。すぐれて社会主義共同体的であるドイツや日本の国民性からして決して好かれる性格ではない。それが、愛する天才にそうであって欲しくない人たちによって、短調作品にちらりと本音を吐くかわいそうな弱者というプロレタリア文学的な鋳型に押し込められていったのである。
それがとんでもないお門違いであることはすでに書いた。絶対王政を支えたアッパー階層である封建領主、有産市民のどちらの身分でもなかった彼がなぜフリーメーソンに唐突に入会して儀式用の音楽を嬉々として書き上げるほど熱中したのかは弱者論では説明できない。彼はプロレタリア文学的な人たちほど政治にうぶではなく、メーソンでの会話でやがてフランス革命に至る硝煙のにおいを嗅ぎ取って勝負に出たバリバリのリスクテーカーだ。父レオポルドやヨーゼフ・ハイドンは定年まで勤めるサラリーマンであり、メーソン入会はしても穏健な旧世代にとどまったが、モーツァルトは若くして飛び出して起業するような急進派の急先鋒だったのである。そのリスクが想定外に爆発して貴族から総スカンになってしまったが、人間界の常識として、それをもってこういう人をかわいそうな弱者と呼ぶことはない。
たとえば、父への手紙で22才のモーツァルトはヴォルテールの死のニュースにふれている。この百科全書派の啓蒙主義者につき父子は平素から会話していたことをうかがわせるが、このこと一つをとっても父の政治的洞察力はとてもアウグスブルグの一介のヴァイオリン弾きのものではない。そのヴォルテールはパリのフリーメーソンだったが(彼を入会させたのはベンジャミン・フランクリンだ)、死後に膨大な著作の版権を買い取って全集として世に広めたのがフィガロの原作者でやはりメーソンのボーマルシェであり、モーツァルトの遺品にはボーマルシェの著作があった。以上の人々全員が、これまたバリバリのリスクテーカーだ。戯曲『狂おしき一日、あるいはフィガロの結婚』がパリで初演されたのは1784年で、貴族を批判、風刺するこの劇にルイ16世は「上演を許すくらいなら、バスティーユ監獄を破壊する方が先だ」と激昂した。モーツァルトは同年の12月にフリーメーソンの慈善ロッジ(ウィーン)に入会しているのである。
モーツァルト⇒フリーメーソン⇒フィガロの結婚⇒フランス革命
と一本の糸で繋がった。その最後の2つについてはナポレオン・ボナパルトが「回想録」で、
“「フィガロの結婚」によってフランス革命は動き出していた “
と書いていることでも裏付けられようが、その「動き出していた」時期こそが、モーツァルトが通称フィガロ・ハウスで人生の絶頂を迎えていた時期だったのである。「フィガロの結婚」において女たらしの貴族に赤恥をかかせて嘲笑し、次の「ドン・ジョヴァンニ」では復讐に燃える騎士長の幽霊の手を借りてとうとう女たらしの貴族を地獄に落としてしまった。ではその次には何が来るべきだったのだろう?
「魔笛」である。
その台本を書いたシカネーダーはモーツァルトのフィガロができる前の1785年に、ボーマルシェのフィガロのウィーン上演を目論んでいたが危険思想であるとして差し止められた。ルイ16世の激昂と危機意識は遠く離れたハプスブルグ王室でもある程度までは共有されていたことをご理解されたい。そしてもうひとつ、フリーメーソンであったシカネーダーも「フィガロ」の貴族批判精神の賛同者だったのであり、その彼が「貴族死ね」のモーツァルトと意気投合して書いたのが「魔笛」だった事実をまず心に留め置いていただきたい。
以下が僕の仮説である。「ザラストロ」のモデルはウィーンのメーソン支部を率いるフォン・ボルンという実在の人物であり、存在感をもってエジプトの神殿に君臨している。一方で敵役の「夜の女王」は雷鳴と共に天空から現れる生身を感じない幻のような存在である。これはなぜだろう?夜の女王はハプスブルグ帝国の象徴マリア・テレジア女帝のお化けだからである(彼女は1780年に亡くなっている)。お化けは次のオペラ、ドン・ジョヴァンニにも石像の姿となって堂々と出てくるから不思議でもない。次に、パミーナだ。この役は生身の人間として感じられるのは当然だ。夜の女王の娘であるパミーナは、従って、マリー・アントワネットであるということになり、この王妃は作曲当時にパリに住んでいたからである。パミーナはザラストロに連れ去られ、女王はそれを嘆いている。オペラで女王は娘に剣を与え、「これでザラストロ(=メーソン)を刺し殺せ」と迫る。
それを現実の出来事と重ねてみると、透かし彫りのように面白いことが見えてくる。魔笛が構想されたころ、マリー・アントワネットも嫁入り先のパリで身が安全ではなかった。まるでパミーナのように。パミーナはザラストロの神殿から脱出を試みるが、奴隷頭モノスタトスに捕らえられてしまう。マリー・アントワネットも、革命の危険を悟って庶民に変装し馬車でパリ脱出を試みるが、革命軍に捕獲され連れ戻されてしまうのである。それ(ヴァレンヌ事件)は1791年6月25日の出来事だが、その2週間前(6月11日)に、モーツァルトは「魔笛」の第2幕(第11曲)のこの音楽を書いているところだった。フランス革命と魔笛の作曲は同時進行していたのである。
魔笛の完成は1791年9月28日だ。その1か月前、ハプスブルグのレオポルド2世はピルニッツ宣言を出し、妹の嫁ぎ先であるフランス王室を守るためオーストリアの軍事介入をほのめかす。革命軍への事実上の宣戦布告である。ここからマリー・アントワネットはオーストリア軍と通謀し機密を漏らしていると疑われれ、ますます身に危険が忍び寄ることになる。モーツァルトは、かつてシェーンブルン宮殿の御前演奏で求婚(?)した王妃を覚えていないはずはないし、むしろ何らかの感情、思慕があったのではないだろうか。兄レオポルド2世の統治するウィーンに戻って欲しかったのだろうか、それとも別な安全な場所に救済されてほしかったのだろうか?
少し時をさかのぼるが、重要なことがある。音楽、演劇好きだったマリー・アントワネットが自分の館であるプチ・トリアノンに作らせた小劇場で1785年9月15日に上演されたボーマルシェの演劇「セビリアの理髪師」にロジーナ役で出演したことだ。自分たちを殺そうと鼓舞する劇に王妃自らが出るなど信じ難いが、彼女に思想的背景や策略があったとは思えず単にお遊びだったようだ。しかし、「セビリア・・」は周知のとおり「フィガロ」の前編で、ロジーナはアルマヴィーラと結婚して伯爵夫人になるのである。前述のように、その「フィガロ」に対して旦那のルイ16世が「上演を許すくらいなら、バスティーユ監獄を破壊する方が先だ」と激昂しているのだから夫婦仲まで心配になるが彼女の真意は分からない。
これを知ったモーツァルトは彼女が王妃という立場にもかかわらず王政派保守一点張りではない啓蒙された王妃と解釈し、そうであればフランス革命軍による救出もありと思った。その確証はないが、そこまでお気楽な女性と思ってなければそう解釈しても不思議ではないし、むしろタミーノが現れて助けてというシグナルと思ったかもしれない。逃避先は革命までは至りそうにないウィーンのフリーメーソンであり、その庇護者はオペラではフォン・ボルン演じるザラストロだが、現実はメーソンの Enlightenment によって慈悲ある啓蒙君主化したハプスブルグ宮廷である。もちろん、宮廷楽長はモーツァルトなのである。マリー・アントワネットは絶対王政の悪の代表である母、マリア・テレジアに捕らえられ、王政の仲間であるパリのブルボン王朝に幽閉され危険な目に遭い、革命軍とフリーメーソンに救出され逃避行の末に啓蒙君主になったウィーン王室に戻って幸せになる。これなら魔笛は『貴族と革命軍のバトル劇』として筋が通るというのが僕の仮説である。
モーツァルトは2年後にコンコルド広場に彼女の首がころがるとは知らずに世を去った。
(こちらへどうぞ)
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:______モーツァルト, ______音楽書










大武 和夫
11/20/2019 | 12:22 PM Permalink
遅まきながら読ませて頂き、驚倒! これは凄い。知らなかったことも教えて頂きました。ウーン、この仮説、証明できないものですかね。(タミーノはモーツァルト自身でしょうか?)
世の中のモーツァルト研究者の皆さ~ん、東さんのブログ、読んでますかあ?
大武和夫
東 賢太郎
11/23/2019 | 10:11 PM Permalink
大武さん、最近億劫でオペラやコンサートにご無沙汰ぎみなのですが、たまに行くときっと自分なりに新鮮なんでしょうね。ところで週末は「眠りの森の美女」を観てきます。バレエはとんと興味なしでしたが食わず嫌いはいけないと思った次第です。