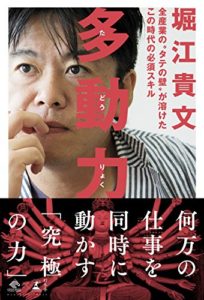公務員を就職先に選んだ東大経済学部生は9人
2023 NOV 3 17:17:21 pm by 東 賢太郎

「今年夏、東大が3月に卒業した学生の進路を公表すると、省庁の幹部に驚きが走った」「公務員を就職先に選んだ東大経済学部生が9人しかいなかった」「東大生のキャリア官僚離れは深刻だ」(朝日新聞デジタル、2023年10月7日)
コロナ前だが映画製作で東大生の子にきいたところ、官僚は最初の10年の下働きが無駄で、頑張って30才になるとスキルなしだから辞められなくなって、その割にリターンは読めない(政治家に嫌われてパーはリスク高すぎ)と言っていた。人気は理系は起業、文系はコンサルとファンドだそうだ。
この考え方は私学の人とそう変わらなくなっているのではないか。国立大だから国にというステレオタイプは消えつつあるんじゃないかという気がしてきた。国の方が民間より上だという空気が昔は大いにあったが個人的には何やら気張ってて田舎くさいなと思ってたし、父は国家派だったが母は商人派で、僕はその点は母方だった。
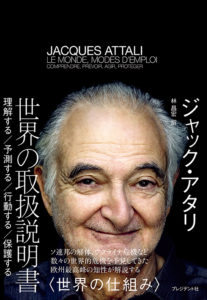 ジャック・アタリは近著で「11世紀から現在に至るまでの時代は商人が地政学、政治、価値観を支配する『商秩序』の時代であった」と書いている。我が国でも中世の国司は荘園を侵略し簒奪する側だったが、貨幣経済の浸透とともに商人が台頭を始めると楽市楽座で彼らを保護して領地に経済力を貯え、南蛮貿易で鉄砲をそろえて戦さを勝ち抜いた信長のような商人共生型近代国家スキームの武将が現れる。天性の商人だった秀吉は信長の中央集権的重商主義を進めたが、それを貧富の差が出ない地方分権的農本主義に180度転換した家康のスローガンが士農工商である。「士」(武士)が官僚であり、いまも日本人に根強い「官>民」という思想はそれをルーツとしている。
ジャック・アタリは近著で「11世紀から現在に至るまでの時代は商人が地政学、政治、価値観を支配する『商秩序』の時代であった」と書いている。我が国でも中世の国司は荘園を侵略し簒奪する側だったが、貨幣経済の浸透とともに商人が台頭を始めると楽市楽座で彼らを保護して領地に経済力を貯え、南蛮貿易で鉄砲をそろえて戦さを勝ち抜いた信長のような商人共生型近代国家スキームの武将が現れる。天性の商人だった秀吉は信長の中央集権的重商主義を進めたが、それを貧富の差が出ない地方分権的農本主義に180度転換した家康のスローガンが士農工商である。「士」(武士)が官僚であり、いまも日本人に根強い「官>民」という思想はそれをルーツとしている。
アタリという学者はディープステート(DS)のスポークスマンであり、DSは国家ではなく国家をまたぐから国際金融資本と呼ばれる商人(資本家)である。農本主義の士農工商とは天地真逆であり、両者が融和するはずがない。現在、岸田政権は米国の背後にいるDS(民主党左派)寄りであり中国共産党もDSに親和的であることから自民党保守は分裂的であり、そのどちらにも反駁する真の保守を標榜する新党に出現の余地を与えた。同党は日本で反DS的主張を展開する宿命ゆえ農本主義的に思える。現代の黒船DSを士農工商政策で制圧できるはずがなく、鎖国をめざすわけでもなかろうから本音は不明だ。当世の東大生はそうした空気を察知しているのではないかというのが私見である。
東大卒が減ってもプラクティショナー資質の優れた人はいるので採用を工夫すれば官僚の質が下がるとも思わない。東大法学部のようにドメスティックな学問専攻の人を中心に据えるのは士農工商由来の方針であり、DS服従に甘んじるならそれでいいが、DSに正面対峙して最善の選択が求められるGDP3~4位の国家としては危険だろう。心は日本人だがDSエリートを英語で論破できる資質の人こそ増やすべきだ(東大生はそういう訓練はされていない)。政治家も同様で、そういう官僚を使えるかという選別基準になれば親の七光りだけの議員は自然に国会から消えていくだろう。
しかし政治家のF先生の話を聞くと銀行は国会議員には金を貸してくれませんよというからそれも大変な職業なのだ。奥さんは心配だろう。僕は1億5千万借りたがサラリーマンだったからで今はもう無理である。人の仕事の価値は金で決まるわけでないが好きなことをやるには金が要る。DS業界ど真ん中でやってきた僕は仕事も趣味も満足できたからこのジョブを生んでくれたDSに感謝しなくてはいけないが、ではLGBT法案賛成かといえば大反対で怒っている。つまり政治信条と人生が一致せず、どっちか取れといわれれば人生なのだ。僕は政治家には向いてない。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
洋モノ美しいもの好き
2017 OCT 26 23:23:04 pm by 東 賢太郎

 いつだったか、この本を買ってきていたく感動して一気に読んだ記憶がある。そうしたら昨夜たまたま寝れなくて見ていたTV番組に本の主人公のモデル、サンモトヤマ創業者・茂登山長市郎氏が登場していた。氏は終戦後の銀座に闇屋を構える。初めは進駐軍のつてで米国品を輸入したが、出会った写真家・名取洋之助から「美しいものが好きならヨーロッパに行け」「まず美術館と教会を観ろ。一流ホテルに泊まれ」と言われる。単身パリ、フィレンツェに出かけ、グッチ、エルメスなどの日本独占販売権を獲得する。ひたすら美しいものを追い求め日本に欧米ブランド文化を根付かせた男の熱い一代記だ。
いつだったか、この本を買ってきていたく感動して一気に読んだ記憶がある。そうしたら昨夜たまたま寝れなくて見ていたTV番組に本の主人公のモデル、サンモトヤマ創業者・茂登山長市郎氏が登場していた。氏は終戦後の銀座に闇屋を構える。初めは進駐軍のつてで米国品を輸入したが、出会った写真家・名取洋之助から「美しいものが好きならヨーロッパに行け」「まず美術館と教会を観ろ。一流ホテルに泊まれ」と言われる。単身パリ、フィレンツェに出かけ、グッチ、エルメスなどの日本独占販売権を獲得する。ひたすら美しいものを追い求め日本に欧米ブランド文化を根付かせた男の熱い一代記だ。
感動したのは魅せられたグッチに毎朝毎朝10時の開店と同時に通いつめ、とうとう会えたオーナーに「日本を俺にまかせてくれ」と裸一貫でぶつかったことだ。その情熱が通じて、ちょとした運も助けてくれて、その場で「やってみろ」と認められていく手に汗握るくだりは野村證券に入社してすぐ、かけだしだった2年半の忘れられない大阪梅田支店でのあれこれと重なってしまい感情移入なしにはいられない。こんな人がいたのかと心にずしんと響く音を聞いてしまったのだ。
本で強く印象にあった茂登山氏は、想像通りの魅力的な人だった。着ているシャツの色。「だってウチはサン、太陽でしょ、だから赤と黄色が好きなんです」なんて、何の理屈もないが、うんなるほどと腑に落とされてしまう。こういう人は学友にはいない、そういえば証券会社のお客様にいたなあと思った。僕はこの商売を始めるまでは営業マンなど程遠いかなりの人見知りで、初めての人と気軽に友達になったり長く会話することさえない性格であり、証券の仕事で出会った人間力あふれる先輩やお客様にそれを直してもらったようなところがある。
ただ例外があって、何であれ、どんなジャンルであれ、語ることに情熱と自信があってリスペクトできる人は昔からその限りでなかった。氏素性でも勲章でもなく人としてのヴァリュー、生き筋の良さとでもいうべきもので、氏はまさしくそれをお持ちの人であって、好きなことをぜったいの自信をもってやってるから言葉が重たくて歯切れがいいのだ。ああいう人はどこにもいるようなもんじゃない。頭脳明晰、理路整然の言葉を吐ける人はいくらもいるが、大体において男としてつまんないヤツばかりだ。
やっぱり洋モノが好きな僕は、氏と同じ時代に生まれてたら闇屋をやったかもしれないと見ていて思った。外人相手の仕入れの交渉なんてさぞエキサイティングだろうとわくわくするのは商人の血が流れてるからか。そして何より、美しいものが好き。氏の人生を動かしたそれが、譲れないほど僕にもある。そうするとどうしたってヨーロッパ、洋モノになってしまうのだ、パリやロンドンやウィーンやローマの記憶に今だってどんなに魅せられていることか。
先日娘の誕生日に「お父さんの人生はね、お前たちが生まれたヨーロッパ時代までが上昇、そこからずっと下降だよな」と話した。そのまま終わるのは嫌だとまだやってるが、でもあした死んじまってもけっこう満足だぞ。そのぐらいね、サラリーマンではないぐらいいろいろすごい経験させてもらって、ここ(心)にはいい思い出がごまんと詰まってるんでね、とも言った。まさしく本音だ。これは野村という代え難いほどいい会社に入れてもらって、自分から希望したわけでないがきっと阿吽の呼吸で好きが伝わって12年も欧州赴任した。こんなラッキーな人生はまたとあろうか申し訳ないとまで思うが、それがまた上掲書の氏のことに重なってしまうのだ。
思えば僕にとってクラシック音楽も洋モノ好きの一部分だった。いまだってそうだ。レコードなどまだまだ戦後の闇屋、バッタ屋っぽかった秋葉原で電器屋が売ってたのであって、髙島屋なんてお品のある所じゃない。1枚2千円で欧州をのぞけるウィンドウだったのだが、のぞいた景色は大変上等だ。そんなものを闇屋風情で自分の眼で選んで買うミスマッチも味があった。本当は絵の方が好きかもしれないが色覚のせいでひけめもあって、でも子供の時、楽器や歌でほめられたことは一度もないが絵はおおいにそれがあって、こっちのほうがもっと適性があったかもしれない。だからこそ、ビジュアルな美を求める茂登山氏の世界には他人事でない感じがあるのか。
番組でもうひとつ、六本木のイタリアンレストラン、キャンティのオーナー夫人・川添梶子も面白かった。旦那の川添氏は後藤象二郎のお孫さんだ。客は著名人、といってもアート、芸能系で、まあパリでいうサロンみたいなもんだろう。梶子は昭和3年生まれでお袋と同じ。やっぱり洋モノ美しいもの好きで、やりたいことやって早くに亡くなったが見事な人生とお見受けした。お袋が僕を成城学園初等科に入れたのは自分がこういう世界が大好きだったからだが、見ていてよくわかった。そういうのは縁遠かったが、出てくるキャンティの客人はみんな人間的魅力があって、なんかほわっとしたこういうのもいいなと思った。
先日、T社長ご逝去の知らせで某弁護士から「我々にも、残された人生の時間はそんなに長くないことを肝に銘じて、仕事や遊びに励みたいと思います」と彼らしいメールがあった。そうだ、そういうトシなんだねと思わざるを得ない。そういうこともあって番組見ながら「ところで今まで俺って何やってたんだろう」という自問の気持ちも出てきたりして、「ここまでおかたい金融屋の父親路線できているけどゆるいお袋の方もいいんじゃないかな」と横恋慕しそうになってくる。お袋は喜ぶんだろうなそれを。なにせ美しいもの好きばかりはそっちの遺伝だ、どうしようもない。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
金正恩のさらなる高笑い
2017 SEP 13 2:02:28 am by 東 賢太郎

これを書いたのは去る5月22日、母の病室でのことだった。お読みいただくと、そこから情勢が何も変わっていないのに驚かれるだろう。
ソナー・アドバイザーズ株式会社 | 金正恩の高笑いが聞こえる …
国連安保理で中露が制裁決議に反対はせず、米国案をやや軽くしたものが通った。これが米国の一手前進だとか最後通牒だとか議論されるが、関係ない。プーチンの言うように彼らは雑草を食ってでも核開発はやめない。いまさらやめる理由がないからだ。
一縷の望みは雑草を食ってるうちに軍部で空腹に耐えられずクーデターが起きることだが、オウンゴールを期待するのもいささかむなしい。思えばオバマの8年は民主党の3年以上に罪深いものだったのだ。リベラル路線で黒人が来て次は女性という見せかけの平等とグローバリズム。それがトランプの登場でひっくりかえった途端に北朝鮮の火薬庫に着火してしまった。
最悪なのは米国がプライドと国益を担保しつつ雑草魂に屈して条件付き対話路線に寄ってしまい、朝鮮半島が北によって統一されることだ。
これは日本国民にとって永遠の悪夢である。のんびりモーツァルトなどきけなくなる。対馬から目視できるところに核保有国が出現するリスクをヘッジするには核保有で対抗する以外に手段はない。隣家のおっさんはライフルをぶっ放す癖があるけど本当はいい人なんです、ウチはセコム(注・別名を日米安全保障条約ともいう)入ってるし、銃なんて危険なものはいりませんでは済まなくなるだろう。
フランス人経済学者で欧州復興開発銀行初代総裁でもあったジャック・アタリの「21世紀の歴史」を読みかえした。大統領だったサルゴジが評価した本だ。個人の自由は人類最大限の価値としながら市場民主主義を経て利他愛に基づく超民主主義へという予測は、当時は面白かったが、今やどこの星の話だという感じだ。同書は2008年刊行だが、たった9年で世界は大きく反転してしまったわけだ。
上掲ブログに皮肉ったが、将軍様はかつての日本軍プロパガンダを踏襲しているとさえ思える。ABCD包囲網ができたらやっぱり踏襲するのだろうか?白人の作った国際秩序が地球の正義であるのか?昭和27年の我が国の独立が70年の時を経てどういう着地を迎え得るのか、退路を断たれた選択の時期が近づいてきている。
(こちらへどうぞ)
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
ホリエモンの「多動力」と「独りぼっち」の関係
2017 AUG 16 18:18:45 pm by 東 賢太郎

堀江さんには悪いが僕はこの本を買ってない。僕はバカな人の本は読まないがそうではない、本屋でさっと目次を見てそれでわかってしまうぐらい僕が日々していることで、これからやろうとしている大計画でもあるからだ。
「多動力」とは何か。それは、いくつもの異なることを同時にこなす力のことを言う。IоTはありとあらゆる「モノ」がインターネットとつながっていくことを意味する。すべての産業が「水平分業型モデル」となり、結果〝タテの壁〟が溶けていく。この、かつてない時代に求められるのは、各業界を軽やかに越えていく「越境者」だ。そして、「越境者」に最も必要な能力が、次から次に自分が好きなことをハシゴしまくる「多動力」なのだ、と彼は書く。まったく同感だ。
昭和世代の特に役所や大企業のエリートでなるほどと思う人はいても実践してる人は少ないだろう。僕がこう書いたのは伊達や酔狂でも独りよがりでも何でもない、意図してではないが気がついたらネット社会の恩恵をフル活用していたのであって、自分が管制塔になって指示を飛ばすという「経営という作業」にこれが最も効率的だった。それは、書いたように、便所掃除をしながら経験的、実験的に、帰納的に知った。
僕の仕事はスマホさえあればワイキキ・ビーチでも野球場でもトイレでもどこでもできる。だから「会社」や「事務所」は実は要らない。ということは通勤時間が無駄だから理想的なのは家であり、自宅の一部は執務室にして朝方と土日休日はそこで仕事している。「独りぼっち」と書いたが弁護士、会計士、税理士らがいて、彼らはパートナー(社員ではない契約でつながった仲間)と呼ぶ。各々の専門分野で彼らが信用できるから僕は構わず大事な部分に鋭く集中できるというWIN-WIN関係だ。
第1章 1つの仕事をコツコツとやる時代は終わった
第2章 バカ真面目の洗脳を解け
第3章 サルのようにハマり、鳩のように飽きよ
第4章 「自分の時間」を取り戻そう
第5章 自分の分身に働かせる裏技
第6章 世界最速仕事術
第7章 最強メンタルの育て方
第8章 人生に目的なんていらない
以上が目次。まったくその通りだ。重厚長大企業で儒教にそまって論語だ師の教えだで育った人には宇宙人だろう。しかし宇宙は物凄い勢いで膨張する。
・自動運転が進めば、もはや自動車の形である必要はなくて、ただの移動するイスになるかもしれない。そのとき、自動車業界もインテリア業界もタテの壁はなくなる
・フジテレビのライバルは日本テレビではなく、恋人からのLINEになる
・あらゆる産業のタテの壁が溶けていけば、今までの経験や肩書きは通用しなくなる
・「越境者」に最も必要な能力が、次から次に自分が好きなことをハシゴしまくる「多動力」
・「1つの仕事をコツコツと」では負け組になる
・80点取れるものをいくつももっている人が強い
・一流の寿司店になるための情報や技術などは専門学校でちゃちゃっと身につけてしまうことができる
・これからは旧態依然とした業界に「オープンイノベーション」の波が来て、情報それ自体の価値はなくなる
・僕の代わりをしてくれる人はどこにもいない。だからおもしろい仕事があちこちから舞いこむ
彼も「お独り様」なのだ。
(注記)
堀江さんの考え方には同期できるものが多いが、注意すべきは彼は非常にスマートな頭脳の持ち主で実体験的な教養の持ち主でもある。そのまま鵜呑みに真似て誰でもできるものではない。それが可能になって20代の諸君が時代から振り落とされないためには、まず「教養」を身につけることだ。それがどうやって身につくか、それは一概に言えないし僕にもわからない。手探りで苦労して求めてみるしかない。少なくとも読書であり、テレビを見ている暇などはないだろう。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
経営者は指揮者であるとともに作曲家である
2016 AUG 6 3:03:30 am by 東 賢太郎

けっして格好をつける気はないが、僕のところに来る仕事というのは難易度の高いものだ。普通の人ではできないし、大企業、ブランド企業でもできない。だから来る。つてを通じて紹介されるお客さんは困っている。しかも彼らは誰もが知る企業のオーナーだったり外国の財閥だったりする。もちろん妙な性質の頼み事ではない。金融、証券の本筋に関わるものだし、僕にはそれしかできない。
それが「アドバイザー」なる職業の実態なのだが、こういう仕事はまず守秘義務契約を結びリテイナーといって着手料をもらう。そして、もしうまくいったら成功報酬をもらう。弁護士、会計士のように時間給でないので収入は読めないが、1時間がいくら高くても徹夜して24時間だ。かたや僕は不成功ならただ働きのリスクはあっても、成功したらずっと大きな報酬がもらえる。
しかもお金以前のものがある。はっきりいって、誰でもできるような案件をやるインセンティブはまったくない。難しい問題ほどチャレンジ意欲がわくという性格なので、その意味でもこれは向いている。場合によっては難攻不落案件だから「面白い、タダでいいから僕だけでやらせてください」というのもある。趣味性の高い仕事ということもできる。
「できません」とお断りしたのもけっこうある。難易度のせいでもお金のせいでもなく、食指が動かない。説明不能。直感的に不安を感じるというか、お金に関わる仕事はいろんなリスクがあるので、危うきに近寄らずという「嗅覚」は不可欠なのだ。おかげで訴訟沙汰は一度もない。コンプライアンスは弁護士にお任せしてるが、それ以前に、自分が近寄らないことが最良のコンプラ対策だ。
しかし偉そうなことは言えない。この仕事ができているのは、ひとえに人脈の力にすぎないからだ。何かしてくれと頼まれれば、これはこの人、あれはあの人と振り分ける。その組み合わせが予想外の発展を見せたりして、思いもよらない解決に至ったりする。そうすると新たに信用ができて人脈は倍加する。人脈マトリックスはweb(蜘蛛の巣)状になって広がる。すると問題解決力は順列組み合わせで増強されるのだ。
僕の会社はwebのど真ん中にいる。webは信用の輪であって、契約の輪ではない。雇用も契約であり、社員をたくさん雇うことが輪を広げる要件ではない。案件ごとに最適な人とパートナーシップを形成することが最も効率的でコストパフォーマンスも良く、得た収入を役割と貢献度によって不公平なく分配できるから構成メンバーのインセンティブも高い。従って競争に勝てる確率も高い。
社長である僕に要求される仕事はその折々で異なるメンバーを束ねて統率すること。いわばオーケストラの指揮者だ。これを法的に法人として組成するには株式会社でもいいが、合同会社、LLCはよりその経営目的とプロセスに合理的ではあるだろう。しかしフレームワークよりも問題はリーダーシップだ。どんな専門職の構成員でも束ねられる力が必要だ。
自分でやったことはないが、音楽に深入りしていろんな指揮者のガバナンス、リーダーシップのスタイルを学ばせてもらったのはビジネスに非常に役に立ってきたと思う。逆にビジネスリーダーとしての体験から指揮者をみるのも興味深い。彼らの最大の仕事も、たぶん、別々の楽器奏者(専門職)に気持ちよく存分の力を発揮してもらい、マスとして最適解を引き出すことに違いない。
ドラッカーが著書「現代の経営」でこういっている。
指揮者は作曲家の楽譜を手にする。指揮者は、いわば翻訳家である。だが経営者は、指揮者であるとともに作曲家である。
Yahoo、Googleからお入りの皆様
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
ピケティの新・資本論について
2015 FEB 1 6:06:13 am by 東 賢太郎

トマ・ピケティの新・資本論がはやっているらしいので「パリ白熱教室」(パリ経済学校講義4時間分)を聴いてみた。お断りするが僕は資本論はなんとなく雑駁に読んだが「21世紀の資本」を読んだわけではなく、それのつもりで内容を見ずに「新・資本論」(日経BP社)の方を買ってしまって仕方なく読んだが、天声人語といい勝負の軽いコラム集みたいなもので、カサは厚いがたいして意味のない書物であった。ああ損した。
講義は所得と富の分配についての考察である。それが不平等であり機会均等とはいえない水準に達して世襲されているのは問題だということだ。正直のところ別に目新しい話とも思えないが歴史として聴くと面白かった。しかし何かインプリケーションがあるかというと、ヒストリカルデータを小まめに取ったという学術的価値はあるのだろうが、僕にとっては直感をやっぱりねと追認されただけ。「上位1%が国の総所得の25%を占めている」という指摘が何を今さらなのか大うけにうけて米国でベストセラーになって、「アメリカ人が騒いでいる」といって騒げば物がよく売れる特殊な国である日本国でブレークした麻疹(はしか)現象という印象である。来年の今ごろは名前も忘れられているだろうと予測する。こういうのが突然流行ったりするのもデフレの産物だなと思料。そのデフレを助長して株をお見事に7000円まで暴落させた政党の党首がこれを担いで安倍政権批判をしているのを見るとマッチポンプという言葉が浮かんでくる。ちなみに翻訳のせいかもしれないが、ピケティのいう「資産」と「資本」という用語の定義が厳密にいうとよくわからないことを書いておく。
彼の主張の根幹をなす式がこれだ。
r-g>0
それは結構だが、r(資本収益率)の過去のデータ収集のご努力には敬意を払うとしても、現在の r はどう測定しているのかさっぱりわからない。これが絶えず変動するのは金融の世界の常識であり、過去がどうあれそれが予測できないからフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズは「ブラック・ショールズ・モデル」でノーベル経済学賞をもらったのであり、そのショールズ先生が経営関与していたヘッジ・ファンドが98年のロシア金融危機で大損して倒産に追い込まれたのであり、資本家は常に配当、利子、賃貸料、キャピタルゲインで潤っているようにお気軽に説明しているがそんな簡単なものと思っているなら彼の理論は机上の空論でしかない。それらはすべて金利の関数であり、それが世界の中央銀行総裁が困るほどゼロに近い現状では r もかなり低い状況にあるはずであり、そうでなくては疑似資本と考えられる超長期金利(10年以上の長期国債利回り)が世界中で歴史的に異常な低率になっているという、観測データのある限り人類史上初の現象は説明できないであろう。できるなら反論していただきたい。さらに疑問なのは、彼はここで資本収益率の背景にあるリスクとの相関性に言及していない点である。資本を持っていればノーリスクでどんどん増えるなどとまさか彼は思っていないだろう。それを言わないなら、彼がどんな読者や聴衆をターゲットにこの論をぶとうとしているかうっすら意図が見えてくる気がする。はっきり言ってしまえば我が国の民主党と変わらないレベルという所だ。
講義でピケティが「rが常に高い」と説明している論拠はこうだ。
①「君たちが銀行に10万ユーロ預金してもハーバード大学年金基金の得ている年間10.2%という収益率は得られずインフレで目減りしてせいぜい3%だろう」 ②「彼らの投資対象はデリバティブやサブプライムローンのように複雑な金融商品だ」 ③「資金の運用には規模の効果もつきものだ」 ④「ハ-バード基金は1億ドルだがその管理に0.3%も払っている」 ⑤「だから資産運用に長けたマネージャーも雇える」 ⑥「金融市場の規制緩和は金融収益の格差を拡大し今日の資産格差を生み出した 理由の一つだ」
反論
①インフレで目減り?いま欧州はデフレでしょ ②サブプライムが投資対象?だったなら彼らは大損こいてr<0でしょ ③だから少額でも買えて規模の利益もみんなで得られる投資信託があるんでしょ ④マネジメントフィー0.3%?ならば「も」じゃなくて「しか」ですよ(笑) ⑤資産運用に長けたマネージャーが損してるケース(r<0)もいっぱいあります ⑥規制緩和が生んだ金融商品で最も損したのは銀行と大手投資家(資本家)でしょ
ということで、この講義が2011年のものだったならこの先生は資本主義の未来は予測できるが2、3年後の未来に欧州がデフレになることは予測できなかったということであり、②に至っては失笑するのみだが、さらにちょっとだけ真面目に申し上げれば、彼がHarvard Endowments (ハーバード大学基金)のことを言っているなら運用額は少なく見ても2兆円を下回ることは絶対にない。そんなことぐらいはフランス人を含む世界の金融マンの常識であって、1億ドル(約100億円)などという天文学的に見当違いな数字を純真な学生相手に持ち出しているところなど、この人がいかに数字に鈍感で金融に無知か、いやもっと言ってしまうと、100億円が天文学的に巨大な金額だと無意識に信じこんでいる世界の住人としてその世界に向けてしゃべっているということを図らずも露呈していると思われる。規制緩和で生まれたわけのわからない金融商品で儲けているのはけしからんといいながら、30万ユーロ(0.3%の管理費用)を出せば優秀な運用者を雇ってそれで儲けられるのになどと支離滅裂なことまで言っている。ちなみに、2兆円を運用するのに30万ユーロぽっちで雇えるマネージャーが詐欺師でもNPOのボランティアでもなく資産運用に長けたマネージャーであると言って同意する資産運用のマネージャーは100万人に1人もいないだろうが、彼はハーバード大学の運用資金量を200分の1とカン違いしているのだという前提に立って好意的に見ればそれは事実と整合的な運用コストという結論に達するだろう。本質は完全に左だがそう見えないよう右寄りに塗固しようと慣れない努力を試みるから馬脚が出るのであって、老婆心ながら資本論をちゃんと読んで堂々と左宣言すればよろしい学者だと思料する。誰が呼んできたんだろう?
僕が「21世紀の資本」を読んだわけではないことを再度お断りする。そこに上記の点について論理的、実証的に満足な説明がなされているなら忘れていただきたいが、仮に r-g>0が有史以来の歴史的事実だったとしても、今は歴史的事実が事実でなくなったかもしれないという歴史的事実が発生している世の中なのであって(だから彼は人気者に祭り上がったのだろうが)、旧来の歴史的事実が何千年何万年続いていようがそれに基づいて処方箋を書きましょうというのはナンセンスである。90才で癌で入院した患者に健康だった89才までの人間ドックのデータで薬を出しましょう、今まで死んでいないのだからあなたは永遠に死にませんよというようなもので、学者がこんなことを言ってるからECBの量的金融緩和が大変な後手に回って欧州は癌が進行してしまったのは気の毒でならない。20年の入院、闘病で癌を克服しかけている先輩国・日本に出稼ぎに来て心配までしてくれなくていいから、早くクニに帰ってドラギ総裁にその制癌剤は間違ってますよと言わないとキミの国のほうがよっぽど大変なことになるよというのが彼の議論の筋だろう。
少なくとも講義を聴く限りの結論はこうだ。
・「米国の上位10%の資産保有シェア90%はフランス革命時点のフランス並みだ」というご発言のとおり、左のフランス人らしいなあということ
・官僚国家フランスの学者、インテリの投資の知識が、米国は言うに及ばず恐らく中国以下であるという点において日本のそれに匹敵するということ
・こんな程度でアベノミクスがどうのといわれてもかなわんなあ、あんまり日本人をおナメくださるなよということ
・パリ経済学校がなんだか知らないが東大生に聴かせるべきレベルではないということ
私見
彼の講義で一つだけ共感したのは教育の機会平等である。大学進学率と所得の相関について述べているが、これも彼の高い本など買わなくても昔から言われていることにすぎないのだが、大きな問題と思う。
「米国人のおよそ4人に1人は地球が太陽の周りを公転していることを知らなかった」(ソース/AFP )
「日本の大学生・短大生の4人に1人が日没の方向を東と答え、地球の周りを回る天体として33%が火星、18%が太陽をあげ、42%が月の満ち欠けする理由は地球の影の影響とした」(ソース/Jキャストニュース)
という事実のほうがr-g>0なんかよりよほど驚嘆に値するのであって、彼らが別に天文学者を目ざすわけではないにしても、これが象徴する事態が収入格差の説明要因として甚大と思うのは僕だけだろうか。こういう状態で大人になってしまったり大学なるものに入学できてしまったりした上で、実は太陽は地球を回ってないんですよ、あなたはそれで損してるんですよと諭されてそうかそんなに不平等な世の中なのかと初めて思い始める教育しか国民の多くが受けられない世の中であるならば由々しきことであり、それこそが政府が心血を注いで是正すべき不平等の種である。この不平等が左翼政権になったり資産累進課税をしたりすると見事に解消されたという事例は僕は寡聞にしてただの一つも知らないが、その原因がピケティの主張するように親の年収格差にあるなら、国立大学は5科目受験を前提に授業料ゼロとして教育機会均等を図るべきである。
以上
(ソナー・アドバイザーズのブログ)
Yahoo、Googleからお入りの皆様。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
株式道場-未来を原理思考しない日本人-
2014 NOV 20 17:17:27 pm by 東 賢太郎

皆様どのぐらい僕の経済記事をまじめに読んで下さっているか知りませんが、これが去年の12月25日時点にご披露した2014年の日本の株式市場と円ドルレートの予想です。
来年の日本株を予想する (My thoughts on Equity Market in 2014)
この予測の結果、来年は弊社が運用アドバイスする資産を倍増していただけることになりました。我々は口先だけの評論家ではなく結果の成否でメシを食っているのでそれはビジネスとしてよかったということではありますが、僕の気持としては弊社の「アドバイスという商品」の価値を認めて下さったことが何よりもうれしいです。こういうお客様のために仕事をしたいと思うのです。ちなみに我々の運用の助言契約先に日本人、日本居住者はいません。
日本人は未来をまじめに思考して議論する人が先進国としては驚嘆に値するほど少数派の民族です。欧米人と決定的に違うのはそこだといってまったく過言ではありません。今日のことだけ一生懸命やりなさい、明日のことなんかわかるはずがないでしょという(本人が意識しているかどうかに関わらず)頑強な文化的刷り込みがあって、これが一般庶民ならともかくインテリ層までそうであるというのは何かどうしようもなく抗しがたい屈強な根拠でもあるに違いないと絶望的な気持ちになるばかりです。
確かにそうです。わかるはずがないんです未来のことは。でも多少はわかるかもしれないし、わかれば徹底的に有利でしょ、だから原理というものを解明すればいいじゃないか。そう考えるのが西洋人であり、僕個人も根っからそういう人です。もちろん日本人が未来を考えないというわけじゃありません、正確にいいますと、原理、ロジックというもので未来を見通す可能性というものを信奉していない、かたや西洋人はその信奉者である、だからこれはやはり宗教に起因する違いと思います(僕は仏教徒ですが)。
例えば月にロケットを飛ばす、それはロケットを月に命中させるということであり、2つの物体の位置を正確に「未来予測」することにほかなりません。それは物理と呼ばれている西洋人の考えた「原理」で知るわけです。日本人だって小惑星イトカワに探査機を命中させましたし、それを帰還させた応用技術力に世界は拍手を送りましたが、それは物理学という西洋の原理解明の学問をひも解いてのことです。教科書で習った方程式を解けば出る答えを「未来を予知した」という捉え方はしていないのではないでしょうか。
投資の世界での原理解明はまだ明確な結論がありませんが西洋人は真剣にその予測モデル開発競争をしています。これは科学に近く、僕の株式への関心もひとえにそこにあります。一般に日本では株というものは上がったり下がったりするわけのわからないもので予測はできず、景気とか業績とか屁理屈ぐらいはあるんだろうがしょせん台風の進路予想みたいなものだ、どうせわからないのだから競馬と同じばくちだろうという認識でしょう。したがって、ここが重要なのですが、投資信託を買って利益が出ても、それはラッキーだっただけであって、それを生み出した運用者に原理を介して未来を見通す能力があるかもしれないと思う人はほとんどいないのです。
スイスにいた頃、ある大手運用会社の会長に「どうして日本では成績のいい投資信託ほど残高が減るのですか?」と質問されました。そうなんです。西洋では逆が常識ですからびっくりするわけです。これは証券会社が加担していて、もう上がりましたからまだ上がっていないのに乗り換えましょうなんていう手数料商売が背景にあります。上がってないのは運用者が未来を見通すことに失敗した、つまり無能の証明なのであり、わざわざ手数料まで払って有能な方から乗り換えさせるなどナンセンスの極みです。
良い運用成績を出し続けるのは能力であり、たまたまアベノミクスで今年はもうかりましたというのではない。そう考えるかどうかは一つの主義であり、それを信じない主義もあります。僕らは前者であり、その能力があるかないかは僕ら自身もわからないのですが、もちろんあると信じているから会社をやっています。その結論が僕らの運用アドバイスの内容なのであり、お客さんから見れば(能力というのは結果でしか見えませんから)その方法論が正しいのだろう、だからそれに従ってみよう、というので資金を増やしていただける。だから僕らに求められるのは方法論を絶対に変えないことなのです。
それが他人に運用の判断をしてもらう側の原理であります。投資信託を買うというのは運用者の能力を買って手数料を払うわけですからその原理に則って行うべき行為なのです。成績の良い人から悪い人に乗り換えるのは、能力的にたくさん打てる三割打者に一割打者の代打を送るみたいなものです。だから投資信託を買われるなら「誰がどうやって運用してるの?」という質問をしなくてはいけません。証券会社のセールスマンでまともに答えられるのはあまりいないでしょう。「一流会社の一流ファンドマネージャーです」のような回答が来たら、即刻お断りした方が賢明でしょう。
さらに言うなら、そういうセールストークにのってしまう人に投資勧誘などすべきでないのです。むかし伝説があって、ある証券会社の地方支店の店頭にお客さんが大量の現金を持って現れ、「必ずもうかるわらんこを下さい」と言ったというのです。よくきいてみたらワラントだった。通じないのでウチは「わらんこ」はおいてませんとお引き取り頂いたそうですが、ばくちだと思うのはまだましだという話です。「必ずもうかる」と詐欺まがいのセールスにでもいわれたんでしょうが、そんなものが世の中にあると信じていること自体とても危険であり、我が国の投資教育は発展途上国なみの水準です。
それはおそらく帝国大学の経済学部がマル経だったことに遠因が求められるでしょうが、ではマルクスの資本論という書がどうかというと、少なくとも立派な未来予知の書であり、僕の印象では素晴らしく原理解明にこだわった書であると思います(その予想は当面は当たってませんが)。その原理を学んで信奉している大学の先生が教えると、その帰結として原理思考とはほど遠い国民が生まれる。このメカニズムはどういう原理に基づいているのかぜひ解明してみたいほどです。
ということで我々は当面のところ外国人の顧客しかもたないというポリシーでやっています。わらんこが下がったと文句を言われてもかなわないからです。
Yahoo、Googleからお入りの皆様。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
テレビを消しなさい
2014 JUL 22 12:12:22 pm by 東 賢太郎

認知科学者の苫米地英人氏によると「貧乏脳」というものがある。
金持ちとは収入が多い人ではなく、収入より支出が少ない人のことをいう。金持ちになる方法は収入を増やすだけではない。ところがそれでは税収が減るので政府、官僚は困る。だから「貧乏脳」を増幅する仕組みを作り知らず知らず国民を洗脳している。以上、「金持ち脳」・捨てることから幸せは始まる(苫米地英人著、徳間書店)(筆者要約)である。
その仕組みの最たるものがテレビであり、CMもドラマも「貧乏は悪だ、消費はすばらしい」という刷り込みを毎日繰り返している。氏によると貧乏脳は2種類から成っていて、「不満足脳」と「低自己評価脳」である。それから逃れるにはテレビを消しなさいと彼は言っている。日本のテレビの対象想定年齢は小学校高学年程度である。人をバカに変え、欲望の権化とする元凶と断じている。
それは知らなかったが僕はたまたま野球とニュース以外はテレビを見ない。そう教わったわけでなく単につまらないからだが、それで人生困ったことは一度もない。だから本を読んだりブログを書いたりできる。時間の問題ではない。テレビから学べることはないということだ。小学生レベルだからあるはずがない。インプットがなければアウトプットもない。だからブログも書けない。
ああいうものを見ていると大脳辺縁系が優位になるらしい。怒り、悲しみ、恐怖など動物としての原初的行動を司る部位だ。そういう貧乏脳から逃れるには前頭前野による「抽象化思考」の必要がある。具体的なお札やコインをイメージしていては金持ち脳はできないらしい。うーん、この辺になるとそういう仕事である僕は自信がない。彼の言う金持ち脳ではないような気もしてくる。
「お金で買えないモノを多く持つほど本当の金持ち」、これはしかりだ。皆さんはどうだろう。それを知れば金を使わなくても手に入るモノの価値がわかり、手に入れる方法が見えてくる。したがって続々と手に入り、満足するようになる。実収入とは無関係に金持ちになれる。これはいい考え方だ。脳が満足すればエフィカシーが上がるからだ。この「満足する」という実感、実体験こそが大事だ。テレビはこれを打ち砕いてしまう。
コーチング用語でエフィカシーとは「自己能力に対する自己評価」という意味だそうだ。だからエフィカシーを上げれば自分はカネを稼げる人間だという自己評価を上げられる。日本人は総じてこれが低い。だから稼げる人間と稼げない人間との差が生じる。稼げる人は稼ぎ方の研究をしているわけでもうまいわけでもない。できると確信しているから稼ぎ方が「見える」のである、と言っている。しかりだ。
別にカネを稼ぐのが人生ではない。僕は死ぬまで人生を楽しむために必要十分な資産額がベストと信じている。ありすぎも害である。もっと増やしたい、取られたくないという邪念が出るからだ。あってもなくてもカネに人生を支配される。これは良くない。しかし「お金で買えないモノ」だけでは食っていけない。だからエフィカシーを上げて、がつがつせず自然に稼げるような脳にするのがいい。この本の教えはそんな所だと思う。
米国カーネギーメロン大学Ph.D.である苫米地氏は博学の合理主義者のようだが言っていることがはっきりして分かりやすい。こういう人は優秀である。要は、むずかしいことはない。テレビを消しなさい、本を読みなさい、だ。お子様、お孫さんがおられる方、実践されてはいかがでしょうか。面白い本であり1時間で読める。お薦めします。
お知らせ
Yahoo、Googleからお入りの皆様。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
おすすめの経済書4冊
2014 APR 22 23:23:12 pm by 東 賢太郎

先週より経済書をまとめ読みしています。いくつか面白いものがありました。
1.経済は「競争」では繁栄しない (ポール・J・ザック著、ダイヤモンド社)
人類を繁栄に導くのは競争ではなく相互の「信頼」であるという主張です。同じことですが僕はある経営者のかたから「信用資本主義」という言葉を教わり深く共感していたのでこの本が目に留まりました。その会社の社員のかたが書いたレポートにたまたま「これからやろうとしているのはオキシトシンを分泌させること」とあったのですが、この本はその脳内物質が人間関係や社会にどういうプラス効果があるかを述べています。著者は経済学者ですが人間を動かす生化学的分析からのアプローチはなかなか説得力があり、日本文化に親和性のある説なので参考にできそうです。
2.スターバックスのライバルはリッツ・カールトンである。(角川書店)
岩田松雄氏(元スタバ・ジャパンCEO)と高野登氏(元リッツ・カールトン日本支社長)の対談の書です。サービスはいずれロボットにかわられる、ホスピタリティはマニュアル化できない、感性の筋トレ、「感動が生まれる接客」をする、悪いお客より社員が大事など新鮮でした。リッツは社員に2000ドルまで自分の判断で使える権限を与えていて、これを使って飛行機でお客様の忘れ物を届けた「空飛ぶドアボーイ」がいたそうです。これは感動を生みますね。スタバにはサービスマニュアルはなく「Just Say YES」という基本姿勢しかないそうです。僕の「ダメな人5か条」にある「いきなりNOを言う」の裏返し。得心いたしました。面白い本です。1~2時間で読めます。
3.アメリカの大変化を知らない日本人(日高義樹著、PHP)
安倍首相が今回の春季例大祭期間に靖国神社は参拝しないというニュースを見て、ああアメリカは失望ではなく本気で怒ったんだなと思いました。アメリカと中国の通貨財政同盟が成立したという本書の主張はあり得るでしょう。SWIFTを使って中国高官の賄賂や不正所得の情報を調査したアメリカが脅しをかけてドル-人民元のペッグを合意し、中国の持続的ドル資産買付によるドル防衛協力の見返りにアメリカは人民元の国際化を進める。事実ならそれを前提とした円-ドル、金価格などのシナリオを再考する必要があります。
4.国家の興亡 ‐人口から読み解く(スーザン・ヨシハラ他著、ビジネス社)
カソリック系家族と人権機関上級副社長、米海軍大学校戦略担当准教授、CIAや国防省の中国専門家など米国シンクタンク、軍部系の複数の著者リストが目を引きました。世界の人口動態データ分析から2020年の米欧中印露と日本での少子高齢化が世界のパワーバランスに何をもたらすのかを論じた書です。軍部の見解として日本の不可避的人口減少により自衛隊員確保すら困難になると予測しており、日米安保条約はいずれオーバーコミットメントになるとしています。これを読むと上記3.のシナリオも不可避的と思われてなりません。我々もいよいよ真剣に自分で資産防衛を考える時代になるでしょう。
結果責任とストックオプション
2014 APR 19 0:00:42 am by 東 賢太郎

前回に評価を下げる5つの法則(Five rules to lose your job)を書きました。その中でも最も致命的にだめなのが「逃げる」です。逃げれば結果は出ません。上司が求めるのは結果ですから、できない理由がどんなに立派でも意味はありません。だから、自分が「やる」と言った以上は何があろうが結果を出す責任があるのだと考える人にしか大事な仕事はまかされません。
野村ではお客様から頂いた注文を書く伝票を「ぺロ」と呼んでいました。支店で投資信託などを1か月単位で募集するときに、課長さんに「今日時点の自分の募集見込み金額は**円です」と毎日申告します。これを毎日増やしていきます。課長は全員の申告数字をベースに課の目標をどう達成するか管理します。これはノルマだからショートすることはありえません。万一、誰かの申告数字が虚偽だったり未達成になったりすると課全体の計画が崩れますから全員に怒られます。
この「申告したけどできませんでした」というのを「空(から)ぺロをきる」といいました。これをやってしまうと当時の野村では問答無用で大罰点がつきました。2度もやろうものなら回復不能なほど信用失墜して「あいつはダメ」といわれ、3度やれば左遷という感じでした。課単位で達成率を競争してますから人事部の評価以前に仲間から失格の烙印を押されて二軍落ちしてしまうのです。
この「空ぺロ」=人でなしという恐ろしい掟が今も生きているのかどうか知りませんが、そこで鍛えられた僕はビジネスにおける信用とはそういうものだとたたきこまれました。企業は手形が不渡りになると潰れますが、まさに空ぺロはそれと同じで、野村は企業経営のプレッシャーをいきなり教えてくれたようなものでした。この修羅場を新人時代にくぐり抜けているから僕はサラリーマンを辞めて起業する自信があったと思います。
この掟は野村に限らずビジネスでは非常に大事です。僕はこれを「スナイパー能力」と呼んでいます。ゴルゴ13やジェームズ・ボンドが「すいません、ダメでした」と頭を掻くシーンはないのです。たとえば小保方さんには美点が一つあって、もし彼女が上司にネイチャーへの論文掲載を何らかの理由で期待されていたとすると、彼女はそれをやり遂げてしまいました。やり方はともかく「空ぺロをきらなかった」わけです。やった行為は理由は何であれ僕は絶対認めませんが、ともあれやりきってしまう気質は言いわけを探して逃げる人よりはビジネスマンとしては数段上であります。
ということは「やる」と言うか否かが決断です。できないと思ったら事前にできないとはっきり言うことが大切です。ここで上司との間で「ボタンの掛け違え」があるとお互いが不幸になります。「やる」と宣言するためには準備が必要で、客観的な目でその仕事と自分の能力を見比べることです。どんなに魅力的な仕事でも、自分の力を超えると思うなら断るか、「ここまでならできます」と正直に申告しておくべきでしょう。
できるとやるは同じではありません。できてもやりきれないこともあります。大きな仕事ほど「心のエネルギー」が必要で、それをチャージして始めることが重要です。インセンティブがそれに当たります。ストック・オプションは成果報酬で、成果に比例してチャージされる電力も増えますから有効とされ、多くの日本企業が活用しています。ただしこれには経営側で留意すべき点があります。
97年のダボス会議で僕は当時GEの大経営者として世界的に有名であったジャック・ウエルチ会長のブレックファースト・ミーティングに出ました。そこで彼が力説したのは「組織プレーができる人にインセンティブを与える」ことです。この組織プレーとは日本的な意味と少し違っていて、学ぶ組織(learning organization)というものです。知恵は現場にあるというのが彼の哲学ですが、そこから得た知恵を独り占めして稼ぐスタントプレーヤーには彼はストック・オプションを与えません。知恵を組織で共有して「学ぶ組織」にする者にだけ与えると言ったのです。
これは目から鱗でした。もちろんオプションは役職や年次で一様に与えるものではありません。また、いくら与えても株価が上がらなければ、つまり与えた成果(=業績)が経営者の見込み通りに出なければオプションはただの紙切れになって誰も幸せになりません。したがって、ストックオプションは「業績連動報酬が欲しくない人(現金が欲しい人)」、「与えても業績に影響度の少ない人」に与えるのは効果を最初から放棄するようなもので、「我こそは株価をあげられる」と挙手する者のうち「学ぶ組織」にできる者に集中して与えよ、そうすれば全員が幸せになるとウエルチは説いたのです。
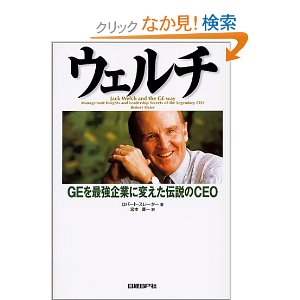 業績を出す=株価が上がる、ということですから、まずそれを「やる」と宣言する者から真の「スナイパー」を選別しなくてはなりません。そしてその中から組織を大切にしてノウハウを出し惜しみなく共有できる度量のある人をさらに選別します。その人を中心に、官僚主義を排し、「学習する文化」を作れと彼は言いました。当時僕は42歳の若僧でしたがこの考え方にはとても感心し、以来「空ぺロなし」と同じくビジネス成功の基本原理だと信じています。このことは「ウェルチ、GEを最強企業に変えた伝説のCEO」(ロバート・スレーター著、日経BP)に詳しく書かれています。
業績を出す=株価が上がる、ということですから、まずそれを「やる」と宣言する者から真の「スナイパー」を選別しなくてはなりません。そしてその中から組織を大切にしてノウハウを出し惜しみなく共有できる度量のある人をさらに選別します。その人を中心に、官僚主義を排し、「学習する文化」を作れと彼は言いました。当時僕は42歳の若僧でしたがこの考え方にはとても感心し、以来「空ぺロなし」と同じくビジネス成功の基本原理だと信じています。このことは「ウェルチ、GEを最強企業に変えた伝説のCEO」(ロバート・スレーター著、日経BP)に詳しく書かれています。