プッチーニ 「ラ・ボエーム」
2012 NOV 18 18:18:47 pm by 東 賢太郎

僕の世代の男性、このオペラが琴線にふれない人がいるのだろうか?
これが始まると1分のうちに僕は20代にもどっている! なんという素晴らしい音楽!!歌、歌、歌!!! 青春をうたいあげたオペラでこれをしのぐものはない。
プッチーニは自分のオペラのヒロインのなかでミミが好きだったらしい。だからだろう、愛情に満ちた渾身のアリアをミミに書いてあげている。蝶々さんにもトスカにもない。ミミの死の場面は感動のあまり泣きながら書き終えたと言われている。
クリスマスイヴ。ろうそくが風で消えてしまい、鍵を手さぐりで探したミミとロドルフォの手が触れる。我々の世代はまだロドルフォになれた。LED照明時代の今なら3 メートル先から「そこに落ちてますよ」で終わりだろう。今の若者がかわいそうな気がしてくる。
この曲、何回実演を聴いたか覚えてもいない。メット、フランクフルト、ヴィースバーデン、チューリヒ、香港、東京などで。そして聴くたびに、舞台を見ても音だけでも、どうしても第4幕で涙が止まらなくなる。はずかしいのでオペラハウスにはあまり行かないことにしている。プッチーニがこの音楽に封じ込めた力はすさまじい。
原作のアンリ・ミュルジュの小説は題名が『ボヘミアンの生活情景』。時は19世紀の半ば、パリのクリスマス・イヴである。第1幕。文無しの芸術家の卵たち、詩人ロドルフォ、画家マルチェッロ、音楽家ショナール、哲学者コッリーネがカルチェ・ラタンに近いアパートの屋根裏部屋で暮らしている。原稿を薪がわりに暖をとるほど貧しい。しかし彼らは人生を謳歌している。若さと未来がたっぷりとある。家賃を取りたてにきた大家を追い出してしまうと、カフェ・モミュスでイヴを祝おうぜと出ていく。
あとで行くよと一人残ったロドルフォ。そこに階下に住むというお針子のミミがノックして入ってくる。ここで二人が出会うことになるのだが、それが鍵の場面になる。そこで歌われるロドルフォのアリア「冷たい手」、ミミのアリア「私の名はミミ」など有名だが、このオペラはアリアだけでもっているわけではない。最初の1音から終わりの1音にいたるまで途切れることのない素晴らしい音楽の連続で、アリア集など作ってもナンセンスなオペラなのである。
暗い舞台設定の第1幕が閉じて第2幕のカーテンが上がったときに目にする華やいだカフェ・モミュスのクリスマスを祝う群衆のざわめき!(左は2011年メットのポスター、下の方の写真が第2幕の舞台である)。誰もがオペラの贅沢さに息をのむ瞬間であり、そこに目くるめくばかりの奔流のような音楽が息つく間もなく流れていく。子供の歌がアクセントになり、マルチェッロの彼女である(あった)ムゼッタの歌う「私が街をあるけば」の魅力的なこと!天才の仕事であるとしか言いようがない。
第3幕は翌年2月。舞台は夜明けのパリ郊外、ダンフェール門の徴税所に雪が降る寒々とした場面。悲劇の影がさしてくる。「ミミを愛しているが、彼女は結核を患っており、貧乏の自分といても助からない。別れなくては」とロドルフォが言う事態になってくる。「以前買ってもらったあの帽子だけは、良かったら私の思い出にとって置いて欲しい」と言い残してミミは去る。咳こむミミ。アリア「さようなら、恨みっこなしにね」 。このあたりの音楽はもうすでにとても悲しい。
しばらく時がたって第4幕の舞台は再びアパートの部屋に戻り、第1幕と同じ音楽で幕を開ける。ロドルフォとマルチェッロは昔の愛を語りあい、孤独を嘆く。そこへコッリーネとショナールがささやかな食事を運んで来る。4人は踊り始め、決闘のまねごとをしたりして戯れている。そこへムゼッタが瀕死のミミを連れて駆け込んでくる。ミミは愛するロドルフォの元で最期を迎えたいと望んでいる。仲間たちはアクセサリーを売ったり外套を質に入れたりして薬を手に入れようと奔走するが甲斐なく、ミミは息をひきとる。
こう書いてしまうと味気ないがプッチーニはワーグナーのライトモティーフという手法を用いて、死に瀕したミミがロドルフォに語りかける場面では出会いの幸せだった場面(第1幕)の旋律をひっそりと回想などする。これがかわいそうで、この辺からはもう泣かずに抵抗などできるものではない。演奏している人たちはそういうわけにもいかないからそれもかわいそうだといつも思う。ミミが亡くなったことはホルンの長い和音が知らせる。永遠の青春譜である。
トゥリオ・セラフィン/ 聖チェチーリア音楽院管弦楽団・合唱団
1959年8月、ローマでの録音。DECCA原盤。
ミミ(レナータ・テバルディ)、ロドルフォ(カルロ・ベルゴンツィ)、ムゼッタ(ジャンナ・ダンジェロ)、マルチェッロ(エットーレ・バスティアニーニ)、コルリーネ(チェザーレ・シエピ)、ショナール(レナート・チェザーリ)
僕はこれでボエームを覚えた。キャストも指揮もオケも最高であり、録音も素晴らしい。ベルゴンツィのロドルフォ、バスティアニーニのマルチェッロが実に立派であり、テバルディのミミも若々しくはないが音楽的に充実しきっている。ローマのオケもいい。そして何より名指揮者セラフィンが見事につわもの達をコントロールしている。これを凌駕するボエームが現れるとは当面考えられない。僕はチューリヒ歌劇場とNHKホールでネロ・サンティが振るのを計3回聴いたが、現役で対抗できるのは彼ぐらいだろう。このオケパートは簡単ではない。ベルリンフィルやウィーンフィルならいいという単純なものではない。第1幕である。
まず、プッチーニの和声法は三和音の伝統的和声法をぜんぜん外れていないので気がつきにくいが、実はドビッシーを感じさせる、いや凌駕さえしている非伝統的な感性に彩られている。ちょっとした場面転換や登場人物の気持ちのうつろいにつく素晴らしい転調や万華鏡のように自在な和声の揺らぎ!台本が若者たちの未熟さ、うぶな恋のかけひき、友情など、食べて恋して歌ってオンリーのイタオペらしからぬリアリズムと繊細さを秘めており、プッチーニの語法がぴったりと寄り添うことで空前絶後の効果をあげていることがボエームの成功の一因であることは間違いないだろう。
オケは3管編成でバス・クラリネット、バス・トロンボーンまであり、打楽器は木琴、カリヨン、鐘、チェレスタ、ハープまでありと、それだけ聞けば現代音楽かなと錯覚する。ズンチャッチャとお歌の伴奏をするオケとは程遠いシロモノである。作曲家の意図通りにこのオケを駆使しないとボエームは演奏できないのである。あたりまえのイタオペ指揮者ではだめだ。耳と力量が非常に問われる。余談だが、チューリヒでは指揮者のすぐ後ろの席だった。ロドルフォが不調で、第1幕が終わると同時につい「こりゃあひどいな」と(日本語で)思わず言ってしまったら振り向いたサンティに睨まれてしまった。そのためかどうか、第2幕開始前に「テノール(誰か忘れたが)は今日はのどの調子が悪い、あしからず」と(ドイツ語で)場内アナウンスがあった。だから仕方なくその日は目の前のオケばかり聴いていたのだが、忘れられない名演奏であった。
トーマス・シッパース / ローマ歌劇場管弦楽団・合唱団 ミミ(ミレッラ・フレー二)、ロドルフォ(ニコライ・ゲッダ)、ムゼッタ(マリエッラ・アダーニ)、マルチェッロ(マリオ・セレーニ)、コッリーネ(フェルッチョ・マッゾーリ)、ショナール(マリオ・バジオラJr.)
フレーニといえばミミ、ミミといえばフレーニである。後にカラヤン盤などに起用されるが64年録音の当盤ではまだ28歳!そして夭折したシッパースも、美声のロドルフォであるゲッダもまだ30代!この大スターたちの若さの記録であるこの録音は永遠の価値がある。ローマのこの歌劇場、92年に聴いたジョコンダは熱かったが、いいオケを使ったとも思う。ムゼッタが固いなどセラフィン盤の完成度は求めるべくもないが、ボエームらしいボエームはこちらなのかもしれない。
アントニノ・ヴォットー / ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団
ミミ(マリア・カラス)、ロドルフォ(セッペ・ディ・ステファノ)、ムゼッタ(アンナ・モッフォ)、マルチェッロ(ローランド・パネライ)、コッリーネ(ニコラ・ザッカーリア)、ショナール(マヌエル・スパタフォーラ)
録音:1956年8月3,4日、9月12日ミラノ・スカラ座劇場
マリア・カラスの声質はミミに向いているとは思えない。しかし、うまい。ミミらしく繕うのではなく「私の名はミミ」などカラスの地声なのだが、演技力と独特の間でなるほどと思わされてしまう。ディ・ステファノのロドルフォは甘い声ではまり役であり、アンナ・モッフォのムゼッタもとてもいい。ヴォット―とスカラ座のオケは最高。こうでなくっちゃという歌心あふれる音を出している。ときどき聴きたくなる個性と魅力にあふれた演奏である。
アルトゥーロ・トスカニーニ / NBC交響楽団・合唱団、少年合唱団
ミミ(リチア・アルバネーゼ)、ロドルフォ(ジャン・ピアース)、ムゼッタ(アン・マックナイト)、マルチェッロ(フランチェスコ・ヴァレンティーノ)、コッリーネ(ニコラ・モスコーナ)、シュナール(ジョージ・チェハノフスキー) 録音:1946年2月(モノーラル)
1896年2月1日にトリノ王立劇場でボエームを初演したのが29歳だったこのトスカニーニ(1867-1957)である。当時38歳のプッチーニが全幅の信頼を寄せる指揮者だった。初演50年記念としてニューヨークで最初のオペラ録音にボエームを選んでくれたことを音楽の神様に感謝するのみである。歌手とオケの緊密なアンサンブルの中心に指揮者があり全部をコントロールしている。この曲はこうでなくてはいけない。アルバネーゼはかわいい系のミミでこれが作曲者の意図に近かったのだろう。カラスが嫉妬したといわれる美声である。ピアースのロドルフォも(ハイCは回避しているが)きっちりとした発声でカンタービレで燃えるところは熱く燃え上がる。とてもいい。
しかし、この演奏で何より僕が感動するのは、歌が盛り上がる部分やホルンのテーマなどでトスカニーニがオケを引っぱりながら感きわまって一緒にメロディーを歌ってしまっていることである。それがはっきりと録音されている。ボエームは彼の血であり肉であり、他人事で指揮棒を振るだけというわけになはいかなかったのだ! 彼の歌が聞こえる部分、実は僕も家でセラフィン盤を聴きながら同じメロディーを大声で歌っていた。この曲は僕にとっても他人事ではない。
この録音でロドルフォ役を歌ったジャン・ピアースが 「指揮するトスカニーニの頬を涙が伝っているのが見えました」 と証言している。このとき79歳だったトスカニーニも、きっと指揮台で20代の青年に戻っていたにちがいない。
Categories:______オペラ, ______プッチーニ, ______演奏会の感想







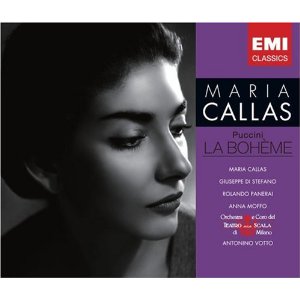
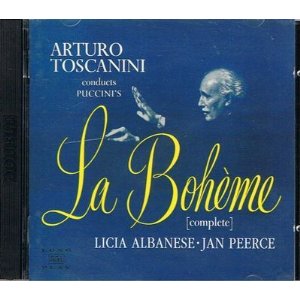



東 賢太郎
11/19/2012 | 8:37 PM Permalink
プッチーニを舞台で歌っておられるプロを前にオペラのコメントを書くのは大変勇気がいり、いつもより時間がかかりました。頭と手が疲れたのでこれはいかんと多摩川を二子方面へジョギングしたところ今日は筋肉痛で足が痛く、とても若々しいエネルギーに充ち溢れるとは言い難い事態におちいっております。しかし「イタリアの演歌」はわかりやすい表現です。森進一の「おふくろさん」、石川さゆりの「津軽海峡冬景色」(ご存じないと思いますが)という歌、ああいうのが日本人の「泣きをいれる」世界でしょうか。カレーラスやカラスなら意外に歌えるかもしれません(無理か・・・)。
Trackbacks & Pingbacks
[…] この方法論は非常に画期的です。例えばこれは、田園交響曲の楽章ごとの細かい情景描写まで自分で書いているフランス人のエクトール・ベルリオーズが幻想交響曲で「恋人のテーマ」としてすぐに具現化しています。そしてベートーベンの信奉者であったリヒャルト・ワーグナーの「ライトモチーフ」という手法に遺伝していきます。登場人物や場面に特定のテーマ(旋律、和音)を割り振って聴衆に記憶させ、後にそのテーマだけで人物や場面を連想させる効果を駆使して彼は長大なドラマの錯綜した心理状況を立体的に描写できるようになりました。イタリア人のジャコモ・プッチーニにまでこの手法は遺伝しています(プッチーニ 「ラ・ボエーム」をご参照ください)。交響曲ではやはりフランス人のセザール・フランクの循環形式が生まれます。幻想交響曲は特殊な例であって、一般に交響曲は抽象音楽です。ストーリーや特定の人物、場面はありません。しかしそういう設定でも、あるテーマ(主題)を全曲で登場させて有機的な統一感を持たせる手法が循環形式です。 […]