新しい才能を発見(尾城杏奈さん)
2022 FEB 5 8:08:37 am by 東 賢太郎

きのう、ちょっと疲れていて、なんとなくベートーベンの27番のソナタをききたくなった。時は午前零時である。仕事部屋は3階、音楽室は地下だ。寒いだろう。youtubeでいいか・・。そんな偶然からこれを見つけた。
すぐアラウに切り替えるつもりだったが、やめた。いい。なんとも自然でしなやかにふくらんで包み込んでくれる感じがする。音楽のたたずまいに品格がある。もう一度聴いてしまった。知らない人だが、教わってできました的な生硬さが微塵もなく、これは人となりなんだろうなと思った。
なんといっても第2楽章だ。すばらしい。僕はどの大ピアニストも満足してない。シュナーベル、バックハウス、リヒテル、ポリーニ、だめだ。牛刀をもって鶏を割く観があり魂がこもってない、ルービンシュタインなど主題のくり返しが多いと文句を言ってる。そういう人にこのソナタが弾けると思わない。
関係ない世界の話で恐縮だが、一昨年のプロ野球キャンプのこと、オリックスの練習を見ていいピッチャーだなと思った新人がいた。あの感じを思い出す。2年後に19才で新人王になる宮城投手だった。剛球はないがああしたピッチングの勘は教わってもできない。現に何年もプロにいるベテランでもできてない。
こっちはさらに不思議なものがある。プロコフィエフの第8ソナタがこんなに「美しく」弾かれたのをきいた記憶がない。ギレリス、リヒテルの剛腕のイメージが強い音楽であれっという感じだ。
youtubeにユジャ・ワン、前々回のショパンコンクール以来僕が高く評価するケイト・リューの見事なライブがある(馬鹿者の着メロが鳴って気の毒)。尾城のは気迫は一歩譲るが、妙な言い方だが「頑張ってます感」がない。汗もかいてない感じだが弾かれるべきものに不足もないのだから、まだまだ破格のキャパ、伸びしろがありそうだ。第3楽章、僕の好きな所だが、短9度の下降音型のあと再現部までスクリャービンみたいな神秘的な感じになる。美しい。プロコフィエフはただばりばり弾いてうまいでしょという人が多いが、この人はそうでなく、バルトークを弾いても音楽が intellectual だ。ピアニストは指揮者と同じでそれが必須だと思う。
東大は天才がいて同じクラスだと分かる。何の苦労もなく勉強ができる人達だ。東京芸大にもそういう人がいるということだろう。youtubeにあるものは僕の好みの領域でもあり、全部聴いた。それだけでどうこう言うことはしないが、尾城杏奈さん、素晴らしい才能の持ち主だと思う。ぜひ欧州に留学し、西洋音楽を生んだ各国の文化、歴史、哲学、人間、そしていろんなアートやおいしい食べ物なんかを存分に楽しんで研鑽されれば明るい未来があると思う。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
ベームのベートーベン7番を聴く
2022 JAN 10 23:23:30 pm by 東 賢太郎

僕はカール・ベームを聴いていない。1975年3月のウィーン・フィルとの来日公演は3月20日の東大合格発表前後だから気もそぞろであり、FMで聴いた気もするがあまり覚えていない。とにかく年輩ファンの熱狂がものすごいと話題になり、絶叫大ブラボーの嵐が巻き起こり、カーテンコールでベームの足にすがりつく人、手を差し伸べて高級腕時計をプレゼントする人も現れたらしい。
ベームは77年も他のオファーを蹴って来日した。招聘元はカラヤン、チェリビダッケも引っぱり出して話題になった。ビートルズが女の子を失神させた、これはわかる。しかし、いいおじさん方がドイツのお爺ちゃんにキャンディーズみたいに熱狂するなんて尋常じゃない。でもあの人たち、もしかして安保反対で旗振ってたかもしれない、日本はやっぱり敗戦国なんだなあと思ったりした。
77年ごろの自分はというと大学3年、音楽はブーレーズの “一神教” 状態で、レパートリーは近現代に偏っていた。弦チェレやル・マルト・サン・メートルやピエロ・リュネールは知っていたが田園交響曲はあくびせずに第1楽章を聞き通すのに難儀していた。同様に退屈だったショパン、マーラー、ヴェルディは今に至るまでそのままだが、バッハ、モーツァルト、ベートーベンは留学へ行ってロンドン赴任するあたりで一気に目覚めの時が来る。
モーツァルトになくベートーベンにあるのはバッハの平均律の痕跡だ。フーガを含む四声体の対位法において旋律が、次いでリズムが小節線を超える。それがベートベンのへミオラに至る。ブラームスもバッハの起源まで見通して先達のそれをより控えめに使ったが、ストラヴィンスキーは起源を断ち切って原初的に使った。僕がエロイカに聴くのはリズム変異と短2度の軋みだが、それを最も先鋭に聞き取ったのはストラヴィンスキーだった。
ベートーベンには20世紀の前衛に進化する因子があった。トスカニーニ、レイボヴィッツの演奏には因子が裸で見える。フルトヴェングラー、カラヤンは大河の流れに埋没させて丸めてしまう。ベームの演奏はどちらでもなく、かといって折衷的でもない。昔の古臭い劇場型をより堅固な合奏力でモダンにしたものだ。本来がオペラ指揮者である彼がウィーン・フィルを振るというのは自然な流れだが、歌なしの交響楽だけで観るなら愛想ない頑固寿司の親父だったのが職人技の評価で最高級店の大将になっちまったみたいなもので、握りに洗練はないが味は保守本流、間違いないねというところだ。
この交響曲第7番はバイエルン放送交響楽団と「店」がちがう。しかし握るのはいつも同じ寿司だ。Mov1序奏部、流れの良さなど歯牙にもかけぬティンパニの打ち込み、腰の重さをしかとお聴きいただきたい。職人一同を自分のスタイルに染め上げた頑固一徹!誠に素晴らしい。喜々として陽光が差し込むようなフルートの第1主題が最高。BRSOの木管はうまく表情豊かで旋律を減速し歌うべきところは歌わせる。Mov2は祈るようなppから徐々に浮かんでくる対旋律を絶妙に活かしトゥッティのピークに持っていく膨らみが劇場的だが、山の裏側で伴奏のキザミは常に冷めて克明という職人技が隠れている。Mov3は曲が個人的に好きでないが、ミュンヘンのヘルクレスザールの残響が大変美しい。Mov4は速すぎぬいいテンポ、これがアレグロだ。7番は3番のようなインヴェンションは皆無であり、ベートーベンが意識して書いた最も大衆向けの曲である。それを更にあおってミーハー向けの演奏となると安手の二乗で聞くに堪えず、僕は知らない指揮者の演奏会で7番は金輪際聞かない。まあどこがどうというということは書かないが、今どき希少な気骨ある立派な交響曲を聴いたというずっしりした手ごたえが残る。カール・ベーム79才の成せる業である。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
クラシック徒然草《その後のケイト・リウ》
2021 OCT 26 14:14:16 pm by 東 賢太郎

先だってのショパン・コンクールはいま徐々に聴いている。その前に2015年の同コンクールで非常に印象に残った3位のケイト・リウからいこう。
5年前、僕は彼女のファイナルのピアノ協奏曲第1番をきいて勝手評価1位にしている。いまきき返しても評価は変わらない。
ショパン以外がききたい。シューベルト、シューマン、ブラームスなどだ。ばりばり弾き倒して鬼面人を驚かすタイプではない、あくまで深い抒情で時を支配して聴き手を自分のワールドに迎え入れ、包み込み、心の底から納得させてくれる稀有のアーティストである。
ラヴェルはどうかなと思ったら、youtubeに「道化師の朝の歌」があるではないか。
これは凄い、誰の真似でもない、14才にしてこの独自の解釈、技量・・・信じ難い才能だ。
16才の「スカルボ」だ。
決してばりばり弾けないわけではなく左手のコンチェルトも難なく弾けるであろう。しかし空虚なテクニシャンでもない。
これは2010年、ニューヨーク国際ピアノコンクール優勝時の「オンディーヌ」だ。ダフニスの夜明けの和音で ff に盛り上がるところの持っていき方など堂々たるもの。
しかしyoutubeに日本語のコメントがほとんどない。彼女は中国系シンガポーリアンで米国在住だが、どうも日本人はアジア系に関心が薄いようだ。才能に国籍なんてないのだが。
このインタビュー、修羅場をくぐった人とは思えぬほど明るくて優しそうだが、非常に知的な女性であることが分かる。
このインタビュー時のリサイタルだ(ヘンデル、ショパン、シューマン)。この5年、彼女は大きく進化している。何を僕が激賞してるか、じっくりお聴きいただければお判りいただけるかと思う。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
サンソン・フランソワの弾くドビッシーは
2021 MAR 9 0:00:33 am by 東 賢太郎

スイスのDE BAER(ディ・ベア)社による アナログターンテーブル「Topas(トパーズ)」の試聴機が来た。60kgと重量級。カートリッジはEMTがいまいちでオルトフォンのMC Anna Diamondをつけてもらったら多少良くなった。あと何時間レコードを聴けるかという年齢だ、意に添わない音で時間を費やすことはしたくない。
ハイエンドは一聴してこっちとはならず、楽しいが比較はけっこう疲れる。LPを取り出して片っ端からきく。ざっと30枚ぐらいか。ジャズ系は最高だ。熱が伝わる。マッコイ・タイナー絶頂期の数枚、 オスカー・ピーターソン・トリオの名盤We Get Requests、ラリー・カールトンStrikes Twiceなどをきく。
このへんでクラシックに移る。ピアノだけはCDの方が良いと思ってるが一応きいてみよう。ミケランジェリのドビッシー前奏曲、コンタルスキー兄弟のハンガリー舞曲、アンドラーシュ・シフのモーツァルト・ソナタ集、ゼルキン・セルのブラームス2番、グルダのワルトシュタインなど。
ここで遭遇したのがサンソン・フランソワの弾く「子供の領分」だった。
フランソワでいいと思ったのはラヴェルの2つのコンチェルトだけだ。どうも色モノのイメージしかないのが正直のところだ。ドイツ物は軽くていまいち、プロコフィエフは面白いが風変りで、ショパンはこっちが聴かない。まあそれは良しとしよう、いけなかったのは肝心かなめのラヴェル、ドビッシーである。
まずラヴェルのソロ名曲集、クープランの墓のフォルレーヌに音符の改変(記憶違い?)がある。EMIの録音レベルが低く音もさえない印象でがっかりである。ドビッシーもベルガマスク組曲の第1曲、10小節目の和音が変だ。第2曲にもあって幻滅である。こういう所でテキトーな人というイメージができ、以後ぜんぶお蔵入りになっていた。
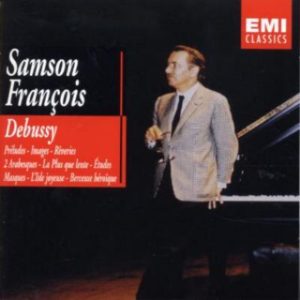 大きな間違いだった。気づかせてくれたDE BAERに感謝する。ドビッシー集のCDも取り出してみる。幻滅して以来だからブルメスターのプリで一度もきいてないが、良い装置だとラヴェル集よりずっと音が良いことを知った(僕のは1987年のフランス盤だ)。しかもだ、前奏曲集 第2巻!いったい何をきいてたんだろう、もう言葉がない、これはかつてきいた最高の演奏である。テンポもリズムもフレージングもフランソワ流で文句をつける人もあろうが、ここまで完全に咀嚼されるとひとつも不自然でない。はっとさせる驚きに満ち、むしろドビッシー自身が弾いたらこうなるのだろうとさえ思えてしまう。エチュードは7,8,10-12番しかない。無機的に響く演奏が多いがこんなにエロティックに響くのは初めてだ、驚くべきイマジネーションである。
大きな間違いだった。気づかせてくれたDE BAERに感謝する。ドビッシー集のCDも取り出してみる。幻滅して以来だからブルメスターのプリで一度もきいてないが、良い装置だとラヴェル集よりずっと音が良いことを知った(僕のは1987年のフランス盤だ)。しかもだ、前奏曲集 第2巻!いったい何をきいてたんだろう、もう言葉がない、これはかつてきいた最高の演奏である。テンポもリズムもフレージングもフランソワ流で文句をつける人もあろうが、ここまで完全に咀嚼されるとひとつも不自然でない。はっとさせる驚きに満ち、むしろドビッシー自身が弾いたらこうなるのだろうとさえ思えてしまう。エチュードは7,8,10-12番しかない。無機的に響く演奏が多いがこんなにエロティックに響くのは初めてだ、驚くべきイマジネーションである。
このドビッシーは最晩年の録音で、たしかコンサートで倒れてその頃は命も危なかったはずだ(だから全集が完成しなかったと記憶している)。それでも酒びたりと煙草はやめず、まぎれもなく不健康でデカダンな男だった。youtubeを探ったら亡くなる3年前にパリのジャズ・クラブで弾いているビデオを見つけた。こういう場所でドビッシーが響く、粋だねえ、なんてパリなんだろう。そんなことはドイツやアメリカでは絶対におきないね、日本じゃ100年たっても無理だ。半世紀前にサティ、ドビッシー、ピカソ、コクトーらがたむろしていたカフェ・コンセールのジャズ版がこれじゃないか。手前で聴いてるのはピアニストのアート・シモンズだ。
ベルガマスク組曲のパスピエ。気にいってたんだろう、そう、これはめちゃくちゃいい曲なんだ。彼はバド・パウエルが好きだった。わかる。このころ、定住する家はなくホテルを転々としてたらしい。歌わせてよと舞台に上がる女性シンガー、ナンシー・オロウェイとは仲が良かったとどこかに書いてあった。
60年代にはパリに多くのジャズメンがきてにぎわったようで、彼がクラブに入りびたっていたのは想像に難くない。酒、煙草、女、ジャズにクスリもあったのかどうか46の短命だった。たぶん男にしかわからないだろうが、野郎にはこんな生き方があっていい。僕は残念ながらそのどれもやらないが、精神構造とライフスタイルにおいて同じ種族であることに誇りすら覚える。ガリ勉のエリートは嫌いだ、あれはそれしかできないからそうなのであって、その人種が弾くドビッシーは死ぬほどつまらない。
今回いろいろ聴いてみたが、フランソワはなんでもすぐ耳コピ暗譜で弾けたんじゃないか。スクリャービンの3番(素晴らしい)やショパンのスケルツォなど譜面を追ってる風情が微塵もない天衣無縫である。バド・パウエルがさかりのついた猫みたいにアオアオいって弾いてる、あそこに楽譜なんて概念はありようもないのであって弾く音符はその刹那に頭で生まれてる、ひょっとしてフランソワもそうで、そうなれる曲しか弾かなかったんじゃないか。
ベルガマスクの和音?そう、違ってたかい?ちったあ構わねえだろ、俺は感じたまんまを弾いてんだぜ、インプロヴィゼーションというやつさ。
そんな声が聞こえる。そうだったのかもしれない。書いたドビッシーもいいんじゃないのってもんかもしれない。モーツァルトもベートーベンもインプロヴィゼーションの名人だったから変奏曲がすいすい作れたわけで、紙に印刷した音符ってのはクラシック音楽という名のジャンルに位置づけたいなんて作曲家が意図した代物であるわけがない。勝手に盗まれ演奏されてはカネが入らんからかなわんということで、ブツにして買ってもらってコピーライトをはっきりさせようってもんだったわけだ。
こういうビデオを見ると、クラシック音楽という世界で出来上がったというか、固まってしまった流儀がとても虚構に満ちたものに思えてくる。志村けんが「お笑い界の巨匠」なんて祭りあがって草葉の陰で笑ってるみたいなもんで、祭り上げて食ってる連中がいるってことである。音楽を書いた連中はたいがいデカダンでマニアックな変人の男であって、フツーの良家の子女や学校秀才がすましてやれるようなもんじゃない。ロック・アーティストがそうだ、連中の風体、生態を見てると多くの人はそう思えるだろうが、それが音楽ってもんの正体だ。燕尾服なぞでおめかしするクラシックというジャンルだけはそうじゃないことになってるのは実に不可思議である。
フランソワを色モノと断じていた僕も忌まわしいクラシック世界の呪術にかかっていたということだ。ずいぶん精神の自由を損していた。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
コロナの邪悪を追い払うヴァイオリン!
2020 DEC 8 16:16:10 pm by 東 賢太郎

廣津留すみれさんから久ぶりにご連絡をいただきました。今年の1月にソナーに来られたのが初めてで、3月末のリサイタルに行く予定でしたがコロナで中止になりました。
アメリカに帰れないので日本でご活躍であり、フジテレビの「セブンルール」でお母さまとの密着番組が放送されるそうです。2週もので、今夜(12月8日)23時~と来週15日の23時~だそうです。大分の公立高校からハーバードに入った秘密が明かされるのでしょうか、楽しみです。
このビデオも送ってくれました。
このところ憂さ晴らしに大編成の曲ばかり聴いてましたが、これは衝撃です。ヴァイオリン・ソロってこんなに美しかったのか!!
何度も聴いた曲ですが、こんな心にしみたことはありません。 コロナの邪悪がす~っと消えていくようです。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
ユジャ・ワンのプロコフィエフ3番
2020 JUL 8 14:14:22 pm by 東 賢太郎

ユジャ・ワンのプロコフィエフが僕は好きだ。3番はオハコですでにyoutubeに2つあるが、イスラエル・フィルとの新しいのを見つけた。
第1楽章アレグロ主部。疾走するオーケストラを脱兎の如く飛び出した彼女は追い越してしまう。とりあえず指揮者のテンポに収まるが要所要所でガンガンあおる。これ良さそうだぞと耳が集中するがするとパーカッショ二ストが例の5連符を2+3に叩いてる。おい、おっさん頼むよと文句を言ってあとで自演盤を聴いたら、なんと2+3である。おっさん正しいのか?当初はこうだったのか?不明。
再現部のアレグロはぺトレンコがワンのテンポに合わせて冒頭より速めで入る。コーダに至ってはピアノから入るから誰も止めようがない。独壇場の超速になり、興奮した聴衆が拍手してしまう。しかし自演盤もこうなんだ。
Mov1の再現部、白鍵と黒鍵の和音で半音階をかけ上がってくあそこ、プロコフィエフにはこういう主部と関係ない不思議なパッセージがポンと出てくる。悪魔の黒ミサみたいな妖しさで絶大な効果があってめちゃくちゃスリリングだ。3度目はペダルを踏まずスタッカートでお遊びに至るがこっちはもう異教の魔術にハマってる、ええい許しちまおう。Mov3の決然とした運指も打鍵もあっぱれ、陰影はさっぱりだがこの速さで決まってるのが問答無用の説得力になってる。なにせこの人、コンチェルトというとバルトークは3つ、ブラームスも2つ弾いちゃうのだから女流の常識をぶち壊している。コロナの憂さが吹き飛んだ。
もうひとつ。ガブリエル・タッキーノ盤(Vox)だ。18才でパリ音楽院のプルミエ・プリ。コンクールはヴィオッティ1位、ブゾーニ2位、カセルラ1位、ジュネーヴ2位、ロン・ティボー4位、しかも一時カラヤンに目もかけられた。それでいて「プーランクの唯一の弟子」だけってのは解せない。
この演奏、ワンのあとに聴くと熱がない。きれいに整っていてMov1はテンポも中庸で妖気漂う部分に狂気もない。プロコフィエフとも親交あった人だが、所々即興性をはらんだ作曲者の演奏に準じるかというとそうでもない。Mov2の瞑想部分は谷底のように深く、最後の変奏での高音部のきらめき、和音のブロックでの伴奏を克明に音楽的に聞かせることに腐心している。Mov3はおとなしめ部類で、木管との輝かしい交叉はラテン的、第2主題再現部はロマン派のごとく耽溺する。つまり、遅い部分に重点があり、高度な技術でスタンダード作品の真髄を記録しようと意図したかに思える対極的な演奏だ。
3番という曲を僕はなん百回聴いたろう?十代にワイセンベルク盤でハマったと思うが、次に買ったアルゲリッチが一段と強烈で、恐山の巫女みたいに髪振り乱すスタイルが代名詞になってしまった観がある(ワンはその継承者だ)。それが今も心をつかむのは書いた通りだが、プロコフィエフの音楽はそう一面的ではない。鬼押し出しや大涌谷の予期せぬ所からガスの噴出があるような、荒涼な景色の中で何に驚かされるかわからない怖さがあって、まったく表向きは共通項がないがモーツァルトに通じている。タッキーノ盤は平穏な観光風景にそんなものが潜んでいることを教える。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
ユリア・フィッシャーのモーツァルトを聴く
2020 JUN 25 1:01:03 am by 東 賢太郎

コンサートがないのでyoutubeを見てますが、ユリア・フィッシャーさんがモーツァルトのヴァイオリン協奏曲を語ってます。
1,2番はバロック的で3,4,5番はベートーベン世界に移行しつつある。モーツァルトがというよりコンチェルトという世界が移行していく時期に書かれた作品だ。同じ作曲家の曲をチクルスで通して弾くと同じ弾き方になりがちだが、モーツァルトの場合は曲ごとに弾き分けないといけない。最も注意深さを必要とする作曲家で、私は曲をすぐ覚えられるがこの5曲はそうはいかなかった、という趣旨を語っています。
余程のモーツァルト好きでなければ1,2番を諳んじていることはないでしょう。普通は3,5番なのです。こういう背景をふまえて、彼女は「ともすれば1,2番は学習者用の作品と思われていますが、私は子どもの時に3,5番しか弾かなかったので幸いでした」と述べています。こういうものの言い方は非常にハイレベルな知性と自信が無いと高慢に思われるだけでなかなかできません。僕が彼女に惹かれているのは、それが口だけでなく音にも出ているからだろうと、今回ビデオを見ていてそう確信しました。
性格なので致し方ないのですが、僕は知性を感じない演奏家は総じてだめです。まったく聞く気もしない。テクニックを素材として表現すべきは知性だと思ってるからです。どっちが無くても音楽になりませんが、テクニックで終わってる人が実に多いのはそれで満足する聴衆の責任でもある。譜面を伝統に照らして的確に読むのはテクニックの内です。そんなのはあたりまえである。そこからが演奏家の創造の世界であり個性の発露です。それが演奏の出発点といってもいいでしょう。
第2番ニ長調K.211です。
第2楽章は出だしが調までドヴォルザークのチェロ協奏曲第2楽章と全く同じで、中間部で魔笛に通じるナポリ6度がきこえます。第3楽章の出だしはピアノ協奏曲第21番 K.467の終楽章に顔を出します。そういうことまで見通して弾いているかどうか、会ってみた彼女はイメージ通り実に聡明そうな女性でしたからどうでしょう。まあいずれ学ぶでしょう、そうでなくても。
彼女は「注意深さを必要とする(彼女の英語で「attentiveであるべき」)」音楽に向いてますね。俗にいう回転がものすごく速い人で、抜群の記憶力と技術で人の2倍の速度で処理しながら絶対にミスしないし、苦労してできたという感じがなく、ひょいひょいとやってしまう。ワタシ失敗しないのでを地で行く人です。普通の演奏家が弾くだけで大変そうな高速の運指の場面でも一つひとつの音符に「注意」がこもってるのがひしひしと伝わる、それも神経質にでなく「楽興をのせる」という風にです。演奏を見るとわかりますが、音楽を心から楽しんでますから機械的に陥らないのです。
僕はクラシックファンは基本的には知性的と思っていますが、日本ではどういうわけかすぐれて「反知性主義」なところがあります。精神性、こころ、深みという言葉で形容される形而上的要素が必須とされ、欠いていると凡庸だと烙印を押され、それならば譜面を逸脱した狂乱の爆演の方がましだという風潮です。これは大きく間違っていますが、通ほどその傾向がある。通になるには何がしかの知性は必要ですが、その人が反知性主義であるという分裂がおきる文化は奇妙ですらある。
一般論として、左様な分裂の誘因として代表的なものは宗教による洗脳でしょう。通の教祖である昭和の評論家が精神性、こころ、深みを教義として広めた。僕自身「レコ芸」主筆クラスの評論で知識を得ましたが洗脳もされました。ただ、欧米に長く住んでその教義が英語、ドイツ語にならないことも知りました。ではあれは何だったかというと、結論だけ書きますが、評論家が通になるに至った自分の趣味の表明だった。それはそれで貴重な理解の土台にさせていただきましたし、英国、ドイツの通人と一緒に数多の演奏会を聴いて、日本の著名評論家各人の好みのベースの類型も理解しました。
趣味とは人の数だけあって要は好き嫌いなのです。「精神性」は洋物の鑑定に書いておけば反論されない、いわば業界の符牒としてのお墨付け用語だった。「この古伊万里は塗りに味がありますなあ」の「味」に相当する通だけがわかると認知された和風基準です。洋物を和風に味わってはいかんというのではありません。彼らはれっきとしたインテリ、知性派ですが、敗戦で和風知性を凌駕された米国知性への強烈な侮蔑と反感があったと思う、そこが問題でした。それイコール科学であり唯物論的知性だから、形而上的、非物質的知性に基軸が振れた。その象徴が「精神性」というワードであったと解釈しております。すぐれて終戦後的、昭和的な智の性向であったでしょう。
僕自身その空気を吸って育ちましたし非物質的知性に深く引かれる性格を持っていますが、まずは唯物論的知性で無用な澱を洗い流してみようという行動原理を持ってもいます。むしろ後者が強い。だから昭和的な智の性向は「澱」だったと気づき、自然と思考回路から完全に除去されました。その土台のうえに築かれたのが僕の音楽嗜好だったということです。嗜好は意図と無縁に醸成されるものですから食べ物や異性の好みに似ます。本質的に100%我が儘なものであり他人と違って当然であり、他人に押しつけるものでもありません。したがって、僕は彼らにおける精神性のような宗教ワードは忌避しますし、書いたことのご判断は読み手の知性に委ねることしか致しません。
僕がなぜユリア・フィッシャーの演奏が好きかというと、単に好みだからであり、それはなぜモーツァルトが好きかという問いの答えでもあります。モーツァルトに精神性のようなものなどかけらも感じないし、求めもしないし、彼は簡単でなかった人生その場その場で立ち現れた難事に抜群の回転の頭脳と天性の楽観性で立ち向かい、切りぬけた。その「あっぱれ感」がたまらず好きで、応援団であり自分の人生来し方に投影もしている。彼の音楽をどう演奏してほしいかについては、もう50年の歳月を経て確たる自己基準ができていて、それに照らして彼女の演奏姿勢は(出した音というよりも)とても共感するものがある。それが彼女の、テクニックから先の創造であり個性の発露と思うのです。
以前にもご紹介しましたこのビデオ、改めていいなあと思いました。ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364の第1楽章です。いかに楽しんでるかご覧ください、彼女の楽興がヴィオラに乗り移り、オケ全体にも電気のように伝わってます。
1分33秒あたりからオーケストラがクレッシェンドするワクワク感。モーツァルトですねえ。1分49秒でフォルテの頂点に達したと思うと1分57秒からまた不意に静まってあれあれと思うと、2分14秒からソロのふたりがピアニッシモで、聞こえるか聞こえないかぐらい、獲物に近寄る猫みたいにひっそりとユニゾンで入ってきてだんだんクレッシェンドします。なんていう効果だろう!
作曲当時、鍵盤楽器(ハープシコード)は音の強弱が出せず、オーケストラもフォルテとピアノの交替はあってもこんな「音量のグラデーションをつける」という発想はありませんでした。聴衆はびっくりしたでしょう。こんな新奇なことをモーツァルトもひょいひょいとやってしまう。ロッシーニはクレッシェンドの効果を盗んだし、ベートーベンは彼なりの劇的なやり方で第5交響曲の終楽章へのブリッジに使っています。
ユリア・フィッシャーさん、モーツァルトに会わせてみたいですね、ひょいっとできちゃう天才同士で何か起こりそうだ。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
スクリャービン 「法悦の詩」 (Le Poème de l’extase) 作品54
2020 JUN 13 16:16:02 pm by 東 賢太郎

この曲はスクリャービンの4番目の交響曲である。聴いたのは故ロリン・マゼールがN響を振ったときだけで、それもあまり印象にない。もっと前に、指揮者は忘れたが、N響は5番をスコア通りに「色付き」で演奏したことがあるがもう人生でお目にかかれないだろうから貴重だった。4番のレコードはブーレーズ、ストコフスキー、ムラヴィンスキー、モントゥー、グーセンス、シノーポリとあって最後の2つは気に入っている。特にグーセンスは一聴の価値がある。
一見複雑なテクスチュアの曲だが、メシアンを思わせる冒頭のフルート主題のこれと、
トランペットのこの主題を覚えておけば全曲がつかみやすい。
この譜面はコーダだが、トランペット主題は何度も出てきて耳に纏わりつく。ショスタコーヴィチの5番Mov1の主題にも聞こえ、最後はセザール・フランクの交響曲ニ短調と瓜二つの終結を導く。
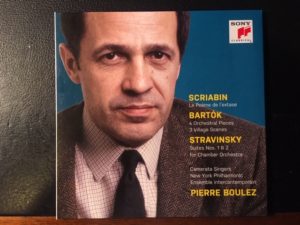 先に挙げた演奏のうち、異彩を放つのがピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルのCBS盤だ。シカゴ響との新録音(DG)はどれもそうだがやっぱり丸くなっていて僕は採らない。音は変わらず分解能の高い精緻なものだが、ウィーン・フィルでブルックナーを振る敬虔なキリスト教徒のものだ。神を否定したかに見えた60年代の彼ではなく一般に理解される方法とメディアによって異教徒だった頃の残像を残そうとした試みに過ぎない。全共闘や革マルの戦士が大企業の役員になって品行方正づらでHPに載っているようであり、70年代を共に生きた僕には堕落以外の何物でもない。
先に挙げた演奏のうち、異彩を放つのがピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルのCBS盤だ。シカゴ響との新録音(DG)はどれもそうだがやっぱり丸くなっていて僕は採らない。音は変わらず分解能の高い精緻なものだが、ウィーン・フィルでブルックナーを振る敬虔なキリスト教徒のものだ。神を否定したかに見えた60年代の彼ではなく一般に理解される方法とメディアによって異教徒だった頃の残像を残そうとした試みに過ぎない。全共闘や革マルの戦士が大企業の役員になって品行方正づらでHPに載っているようであり、70年代を共に生きた僕には堕落以外の何物でもない。
彼の録音の “主戦場” だった音楽は20世紀初頭のものだ。欧州最初にして最大の狂気であった第1次大戦に向けて社会ごと狂っていく時代、後にその寸前を良き時代(ベル・エポック)と呼びたくなるほど酷い時代の精神風土を映しとった作品たちである。ブーレーズはその空気を吸って育ち60年代にアヴァンギャルドの戦士になったが、彼が壊しにかかった古典は「戦前の前衛」であり、壊すことは時代の「先へ進む動力」であった。ベートーベンもワーグナーもドビッシーも各々の時代でそれをした。革命という言葉が破壊と同時に新生のニュアンスを含むとすると、それこそがブーレーズの作品群だ。彼は演奏家である前に作曲家であり、彼のCBS録音はアヴァンギャルド(前衛部隊)で戦う若き彼のリアルタイムのブロマイドとして永遠の価値がある。
DG録音群は、20世紀後半に前衛は死に絶え、音楽が動力を失い、作曲される傍からクラシック音楽という埃をかぶった懐古的ジャンルに封じ込められる運命にあることを象徴したものだ。第2次大戦後、今に至る「戦後」が始まる。ストラヴィンスキー、シェーンベルク、バルトークらの打ち立てた戦前の前衛の音楽語法が戦争という無尽蔵の破壊力をもった狂気からインスピレーションを得たということは重要だ。テクノロジーの世界で火薬、船、トラック、飛行機、インターネット等は戦争による軍事技術として進化した。それと同じことだ。十二音技法が生まれる素地は「戦前」の空気にあったのであり、その作曲技法(語法)が戦後の前衛の在り方のインフラとなったのは必然だった。
そうしてアヴァンギャルド(前衛)なる言葉自体が戦前の遺物と化してしまった。それを破壊し革命を起こすほどの新たな社会的動力はなく、作曲という記号論理の中だけで進化を促す動力も見られない。”前衛風に” 響く音楽は生産されているが、「クラシック音楽」なる金色の額縁に収まるか否かの価値観で計られる壁は高い。一方で元来音楽は消費財であり、現代はゲーム、アニメのBGMと競う運命にもある。ドラえもん組曲やエヴァンゲリオン交響曲がコンサート・レパートリーに加わる日は来ても不思議でないが受け入れる聴衆は未来の人だろう。
ブーレーズ戦士時代の録音である「法悦の詩」をほめた人はあまりいないように思う。スクリャービンはテオソフィー(神智学)を信奉しておりエクスタシーはそれと関係がある。神智学は「真理にまさる宗教はない」とし、「偉大な魂」による古代の智慧の開示を通じて諸宗教の対立を超えた「古代の智慧」「根源的な神的叡智」への回帰をめざすとされるが、wikipediaの英文(しかない)を読む限り特異な概念である。エクスタシーだからセックスの絶頂ですよという単純なものではなさそうだが、この曲に多くの聴衆が求める快感はそのようなものだろう。ブーレーズCBS盤のもたらす透明感、立体感はさようなドロドロと無縁であり、彼が録音した意図に戸惑いを覚える人が多かったのではないだろうか。
僕の場合はエクスタシーはどうでもよく、この頃のブーレーズがやはりドロドロだった春の祭典を怪しげな呪術から解き放って自分の美感で再構築した詩的なリアリストであることが魅力のすべてだった。この法悦の詩はトリスタンのオマージュにきこえてならない。彼がバイロイトで指揮したワーグナーを聴くと、トリスタンに魅入られてワグネリアンで出発し後に否定したドビッシーの音楽がクロスオーバーする地平で響いていることに気づくが、それと同じ響きがここにもあるのだ(冒頭の雰囲気などドビッシー「遊戯」そのもの)。和声が解決しない調性音楽であり、内声がクロマティックに動いて属七を基軸に和声が変転するがバスが明瞭で構造的に複雑ではないのに複雑に聞こえる。凝った装飾で副次主題がからみ錯綜したポリリズムを形成するからだ。このスコアを二手で弾くのは不可能。四手でも難しい。ブーレーズはそれを分解し、磨きをかけ、最適なバランスでドビッシーのように詩的な透明感を与えて音化しているのである。
全くの余談だが、久々にこれを聴いて脳が若返る気がした。以前書いたが受験時代にブーレーズが夢に出るほど没入していて、ハマればハマるほど数学の成績が上がって全国1位を取ったから因果関係があったと本気で信じている。クラシック音楽は脳に「効く」漢方薬だ。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
無観客のケンぺ指揮チャイコフスキー5番
2020 MAY 26 11:11:35 am by 東 賢太郎

この演奏は一度ブログにしてます(ケンペのチャイコフスキー5番)。同じCDを扱うのは、先日聴きなおしてさらに思うところがあったからです。
これをFM放送できいたのは45年も前ですが、第4楽章のティンパニを強打した頑強な骨組みの音楽に魅入られ、一音も逃すまいとスピーカーににじり寄って聴いたのです。その場面を、ティンパニは右チャンネルから聴こえていたことを含めてはっきりと覚えていて、勿論、その日のその前後の記憶などまったくないのですから余程の衝撃だったのでしょう。
それまでもっぱら聴いていたオーマンディー(CBS)のレコードはいま聴いても素晴らしいもので後に同曲の実演も接したのですが、あれはアメリカの音、こっちがドイツの音と、非常にプリミティブではありましたが、僕の中に仕分けの箱ができたという意味で自分史の重大事件でした。前稿は2013~4年、会社の存続が大変な時期でそこで偶然うまくいったから今がありますが、精神史として読み返すと痛々しくもあります。
さてFMで衝撃を受けて忘れられなかったケンぺの5番ですが、放送録音らしく正規盤が見つかりませんでした。仕方なく翌年にEMIの正規録音であるBPO盤を買いましたがどうも熱量が足りず、悪くはない(1つ星を付けてる)のですがどうしてもそれが忘れられずにいました。以来ずっと海賊盤を探し続けていて、ついに2002年に石丸電気でそれと思われるCDを発見した喜びがひとしおだったのはご想像いただけるでしょうか。これです。
今回、6年前執筆時よりは僕の精神も安定しているのでしょう、感慨を新たにしました。なんてドイツドイツしてるんだろう!これをアップしたらすぐ外国の方が「(この演奏を)ソ連のオケと思ってました」とコメントをくれましたが、自分も前稿でナチスの行進もかくやと書いております。さように両端楽章で主題を威風堂々奏するところ、トランペットの鳴り具合とティンパニの迫力はそれがチャイコフスキーの書いた最も「自己肯定的」な音楽であることを知覚させます。ロマンと陶酔でムード音楽のようにあっけらかんとした快楽主義の5番が横溢する中で、ケンぺの解釈は強烈な存在感を主張します。
後に彼はこの曲に否定的な評価をして見せるようになりましたが、4番で分裂症的になり、5番で立ち直り、6番で破綻した。各々に白鳥の湖、眠れる森の美女、くるみ割り人形が呼応している様は彼の精神史そのものです。否定的だったのは「実は俺は立ち直っていない、ふりだけだ」という自己嫌悪の現れだったように思います。私見ではチャイコフスキーにはドッペルゲンガーの側面があると考えています。その段に至った彼はケンぺの演奏を嫌ったかもしれませんが、書いたスコアは雄弁にこの解釈(男性的なもの)を志向しており、だから否定的姿勢をとるしかなかった。分裂的なのです。
それをカムフラージュするロマンへの逃避(女性的なもの)は同じく精神を病んだラフマニノフが踏襲しましたが、近年の演奏家の両者の楽曲解釈はというと、大衆の口にあう後者をリッチに描きエンディングで男性性を復帰させて盛り上げるという安直なポピュリズムの横行で、そちらに寄るならポップスでよしと若者はクラシックからますます遠ざかることを危惧するしかありません。ケンぺを絶対視するわけではありませんが、かくも剛直に自己のイズムを貫徹させる指揮者は本当に絶滅危惧種になりました。後述しますが、指揮者が絶対君主たりえない時代のリーダーシップの在り方の問題と同根でありましょう。ケンぺは僕が渡欧して接した歴史的演奏家たちのぎりぎりひと世代前であり残念でした。
Mov2のホルン・ソロの、レガートのない垢ぬけなさは録音当時世界を席巻していたカラヤンを否定してかかるが如しで、ケンぺの気骨を感じます。この委細妥協せぬ圧巻のユニークさは、それを聴いていただきたくてアップしたレオポルド・ルートヴィヒのくるみ割り人形組曲(同じオケ、66年録音)に匹敵するもので、こっちのホルンもとてもチャイコフスキーとは思えません。これです。
ケンぺ盤にあらためて発見するのは音色だけではありません。オケの内部を聴くと第2楽章はテンポが曲想ごとに動くのがスリリングでさえあります。ラフマニノフがP協2番の緩徐楽章に取り入れた出だしの弦合奏は森のように暗く深く、その陰鬱が支配しているのですが木管が明滅する第2主題は水の流れのようで木霊が飛び交うよう。爆発に至るエネルギーの溜めが大きく、リタルダンドして頂点でティンパニの一撃を伴ってバーンと行く様はクラシック音楽がカタルシスを解消し人を感動させる摂理の奥儀を見せてくれます。
意外にアンサンブルが乱れるところもあります。VnよりVc、Cbが微妙に先走って低弦が自発的な衝動で速めたように聴こえ、メロディーは何事もなかったように即座に反応してそっちに揃うわけですが、棒が許容した自発性にVnがついていかなかったのか弦楽合奏の中でこういうことはあまり遭遇したことがありません。第2楽章の全体としてのテンポの流動性はケンぺの指示に相違ないでしょうが、セクションのドライブに委ねる遊びがあって、それが奏者の共感するテンポへの自発性を誘発したかもしれません。何が理由かは知る由もなしですが、この演奏の内的なパッションは稀有なものです。それを呼び覚ましたのはこういう部分かもしれないとこの楽章をヘッドホンで聴きましたが、指揮者の棒がどちらだったのか興味ある瞬間でした。
ただ、そういう乱れはスタジオ録音では修正されますからこれはライブです。しかし客席の気配がない。想像になりますがゲネプロ(本番直前のいわば「無観客試合」)ではないでしょうか。にもかかわらず「低弦の自発的な衝動」のようなものが楽員のそこかしこにみなぎっている感じが生々しく伝わってくるのはライブであれ正規録音であれ極めて稀です。フィラデルフィア管の定期が大雪でほぼ無観客でやったチャイコフスキー4番の快演はそれに近いものでしたが(クラシック徒然草-ファイラデルフィアO.のチャイコフスキー4番-)、指揮者(ムーティ)も楽員も、交通手段が途絶えるなか万難を排して会場に来てくれた少数の客をエンターテインしようという気迫と集中力が観ていてわかるほどで、天下のフィラデルフィア管弦楽団が本気で燃えた一期一会の名演を生んだわけで、人間ドラマとしての演奏行為とは実に奥が深く面白いものです。
さように演奏者の自発性というのは大事です。その有無でコンサートの印象は大きく変わります。ウィーン・フィルが地元の作品をやる場合にそれを感じることが多くありますが、しかしこのオケが常時そうかというと否で、違う姿を何度も見て幻滅もしています。プロとして恥ずかしくない演奏を常にくりひろげてはくれますが、一次元ちがう「燃えた」演奏が極めて稀にあることを知ってしまうともうそれだけでは満足できない。人生、なかなか難儀なものです。
百人の人間の集団がリーダーに心服してついてくるか否かという深遠な問いについてここでは述べませんが、僕は経験的にそれにあまり肯定的ではなく、選挙にせよアンケート調査にせよ企業経営にせよ全会一致は疑念を持たれるほど異例でありましょう。プロの楽団は指揮者への心服の有無に何ら関わらず一定水準の演奏を仕上げられる実力があるから「プロ」なのであって、心服したアマチュアの演奏会の方が感動的という経験も何度かございます。今回聴きなおしたケンぺの5番はそれがプロの高い技術で提示されたものという印象であり、20才でたまたまラジオでこれを聴けたことは幸運でした。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
わが命の音楽、ブラームスの4番
2020 MAY 7 19:19:55 pm by 東 賢太郎

コロナ疲れはありますが、きのう放映されていた聖マリの救命救急センターの戦場のようなビデオでそんな言葉は吹っ飛びました。医療現場のみなさま、心からの敬意と感謝あるのみです。みなさまの姿に勇気づけられました。
なかなか安らぎませんし、音楽も特にほしいことがありません。クナッパーツブッシュ(以下、”クナ”)のブラームス4番をきいてみようと思い立ち、youtubeに上げてあったブレーメンじゃなくてケルンのほうですが、あらためて感じ入りました。これは凄い。ガツンとやられました。こちらです。
youtubeに好きな録音を現在108本上げていますが、第1号が正式録音を残さなかったクラウス・テンシュテットの同曲ライブでした。アクセス数トップはカルロス・クライバー / ベルリン・フィルで5万6千ほどです。4番は僕にとってあらゆる音楽のなかで別格中の別格、もはや人生です。どれだけ聴いたか。ロンドンのころ第1楽章を毎日ピアノで弾いていて、長女は言葉をしゃべるまえにこの曲を覚えました。
ケルンとブレーメン、クナの4番について記しておきます。4番は知るかぎりこの2種しか残っておらず、出来は甲乙つけがたし。彼は変幻自在の即興のイメージがあり、練習を “はしょった” という逸話ばかり有名になっていますが、深く楽譜を読み込んでいるので解釈はほぼ同じです。彼はブラームスと親交があったフリッツ・シュタインバッハの弟子で、習ったのがケルン音楽院なんですね。幾分オケの技量が勝るのと一期一会のような気迫においてケルン放送交響楽団盤に分があるかもしれません。気迫ということではクライバーBPOに勝るものはないと思いますが、それを勘案してもケルン盤はすごいものです。
しかも幾つかあるリリースのなか(全部聴いたわけではありませんが)このウラニア盤は音がいい。彼の解釈の命脈である弦のうねりがはっきりとらえられています。1953年のライブでモノラルですが、奏者の内面から湧き出る熱と質量を伝えており、音質うんぬんよりそうしたスペックにならないものが伝わることを評価します。Mov1、あっさりはじまります。ロマン派めいてなよなよしない。お涙頂戴が多いのはフルトヴェングラーの影響かもしれませんが、この曲はそうじゃない、悲愴交響曲の死や哀感のごときテーマのない純粋無垢の絶対音楽の仕立てですからクナの開始に賛同します。初稿では短い前奏があったのをブラームスは削除してモーツァルト40番のようにソナタの第1主題から開始した。いきなり泣きというのはブラームスの意図ではないと思います。コーダ突入前の主題のトゥッティの壮絶な強奏をきいてください、なよなよ始まったらその発展形としてここに呼応する印象が鮮明に出ない、実に立体的に設計、構築された見事な解釈です。
クナは本質的に女々しさの対極の人でお世辞にも整ってなく、オケのサウンドと質感は荒っぽい。きれいに聞かせようなんて気はさらさらないですね、気に入らねえなら帰れというがんこ一徹の骨っぽさです。流れやうねりの造り方には徹底的にこだわっても細部は、アンサンブルは、あえていうなら放縦ですね。この点については思うことがあって、ピエール・ブーレーズはオーケストラの一糸乱れぬ合奏はアメリカで始まった、だからバルトークはクーセヴィツキーにボストン響用に書いてくれと委嘱された折に、アメリカのオケの合奏力をフルに聴かせる「管弦楽のための協奏曲」を書いたと言ってます。
とするとブラームス当時の合奏はボストン響みたいな高性能ではなかったでしょう。フルトヴェングラーはベルリンフィルに出だしの弦のアインザッツをわざとずらしすためにあいまいな棒を振ったといわれますが、その真偽はともかくアンサンブルが整然と揃いすぎると「らしくない」という美学が19世紀生まれの指揮者にはあったように思います。ワーグナーを磨きぬいた合奏でやることは、そもそもバイロイトのオケは寄せ集めであって前提ではなかったでしょう。クナは無手勝流なのではなく、当たり前のごそごそ感だった可能性があります。ちなみに一時流行した古楽器演奏には懐疑的ですが、楽器だけオーセンティックでもアインザッツは現代風にぴっちり揃ってる。コンセプトに矛盾があると思います。
現代の指揮者にこの美感が継承されてないのは残念ですが現代のコンサートホールでごそごそ型をやったら下手くそと言われるでしょう。聴衆の耳も変わってしまって、アメリカ起源のヴィルトゥオーゾの技術を愛でに会場へ来る人がたくさんいます。そうした快感やスリル追求型の鑑賞もあっていいし名曲の楽しみは多面的ではありますが、やはりブラームス4番という作品はそれだけでは魅力の半分も味わえないでしょう。このクナのブラームスを評価する方は多いし、オンライン鑑賞の世になっても語り継がれてほしいと思います。本当のオーセンティックは楽器ではなく美学にあるべきで、それはけっして博物館に展示される遺物ではありません。人間が作り、人間が感じるものですから、何世紀になろうと不変なものは不変。人を感動させるパワーが永遠にあるものだと思います。
Mov1のコーダにはアッチェレランドがあって、それをティンパニ4発でぐっと落とす。楽譜にないのですが、たとえばウィーンで買ってきたモーツァルトやシューベルトの自筆譜ファクシミリと現代の印刷譜を見比べるといろんなことに気づきます。修正跡とか書きぶり(筆致、筆跡etc)とか印刷譜にない情報がたくさんあります。ブラームスは表示記号をマーラーやチャイコフスキーみたいに細かく書きこまないほうでそれは古典派の精神を継承した姿勢と思われますが、自作を弾くとずいぶん熱くて振幅の大きい演奏をしたと証言が残ってます。楽譜にはないのですがクナのあまりの千両役者ぶりにひょっとしてこれがブラームス直伝かとさえ思えますが、C・クライバーは “まったくのイン・テンポ” だったんです。加速という麻薬を使わないであの熱と質量を出してみせた彼のオーラは忘れられません。
Mov2は遅めのテンポで曲想にはまりきって変幻自在、一個の巨大なドラマであります。弦がとことん歌うのです。後半、ティンパニを地獄の仕置きのように打ちまくったあとの一瞬の静寂をおいて血の色の弦合奏がフォルテに近い音圧で鳴り渡るところ、こんな音を作った指揮者がほかのどこにいたか?楽譜を読むとはこういうことです。Mov2にこんな小宇宙が来てしまうと全曲のバランスがおかしくなりますが、些末なことはいっさいお構いなし。我が道を行くほんとうに見事な男ぶりであります。
Mov3はどうしてもクライバーが耳に君臨しています。録音でも何が起きたんだというばかりの荒れ狂った嵐にびっくりされるでしょう。あれに対抗できるのはこのケルン盤ぐらいかもしれません。こっちのほうが遅いですが、これを会場で聴いたら完全にノックアウトだったと思うのは、クライバーの音、ベルリンのフィルハーモニーに響き渡ったあの音響がCDになるとこう聞こえると知ったからです。それを逆算するとああなる。ということは、このクナ盤を実演できいた音響は・・・と推測してしまうわけです。時の人類最高レベルの奏者たちがクライバーという指揮者に心酔して心底燃えまくって4番をやるとこうなるのかという奇跡のような体験でしたが、ケルンの聴衆もそういうものを感じたと思います。
Mov4、テンポも強弱も自由自在、フレーズが生き物のごとく脈動し、ティンパニが鉄槌のように打ち込まれブラスがさく裂し、弦は切れば血が噴き出すテンション。遅めのコーダ!最後の和音は譜面どおりさっと打ち切られます。この楽章、クライバーは疾風怒濤のごとく恐るべきエネルギー放射で駆け抜け、実演ではしばらく会話もできないほど圧倒されましたが、クナのほうはフルートソロ直前のppの弦の魂のふるえから渾身のffの咆哮まで密度と陰影が深いテンポのギアチェンジで生々流転、ぐっと歩みを遅めて居住まいを正すように迫ってくる最後の審判のようなコーダはまさにこれという絶対の説得力を感じてしまい、いまはこちらを採りたいと思います。
クナのケルン盤は数ある4番の録音の中でこのクライバー盤と共に1,2を争う文化遺産と思います。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。








